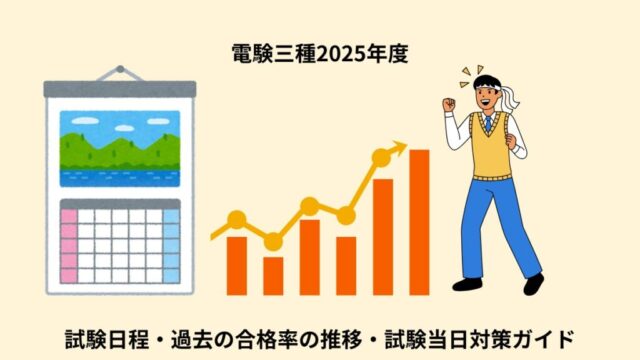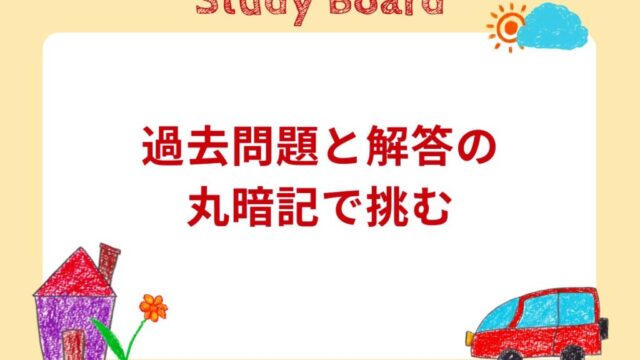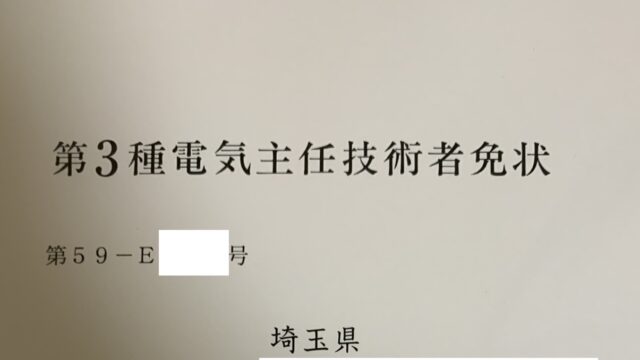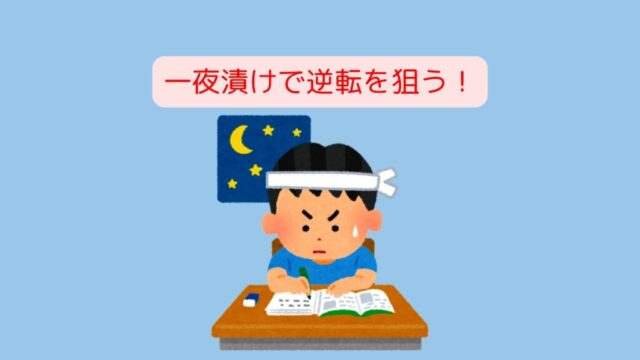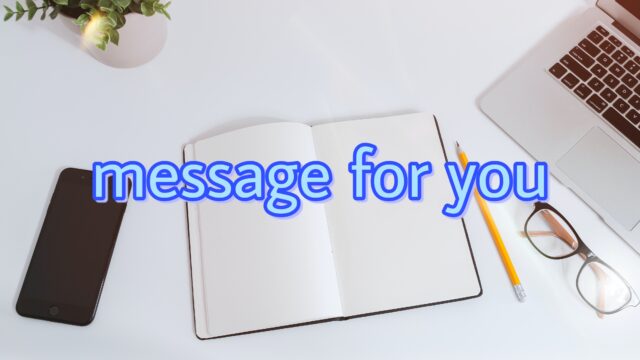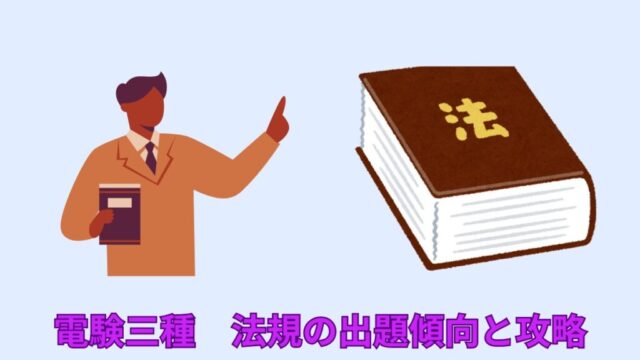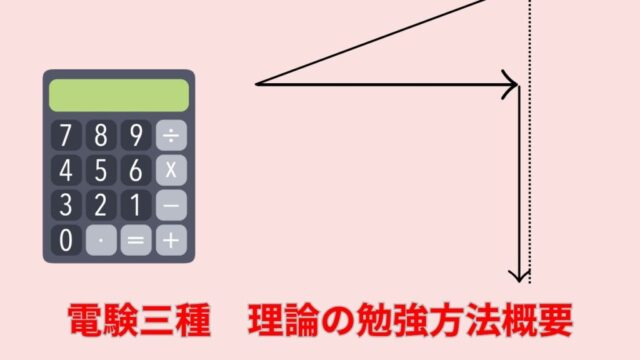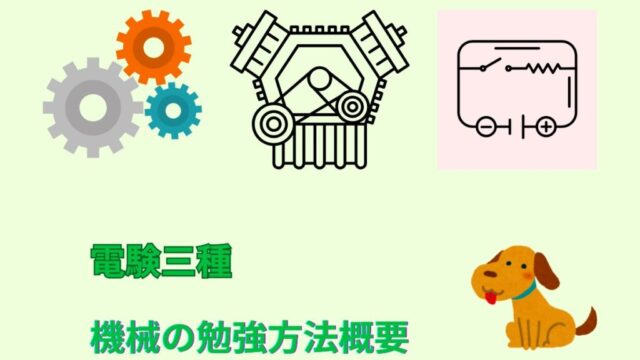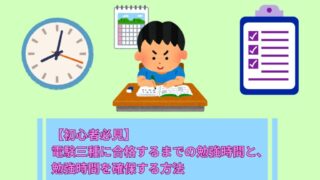【初心者用】電験三種 法規の勉強方法概要

- 今から電験三種「法規」の合格を目指している
- 試験で唯一の暗記科目で、どうやって勉強すればいいのか分からない
- 暗記が苦手で、つい法規の勉強を後回しにしてしまった
- 気がつけば試験日まであとわずか
- 最後の追い込みでなんとか合格したい!
電験三種の中でも「法規」は、他の科目と違って計算問題がほとんどなく、条文や法律、制度などの暗記が中心。
理系出身の方にとっては、「とにかく覚えるだけの勉強」がどうしても苦手で、後回しにしてしまいがちな科目でもあります。
実際、私自身も理系出身で、法規だけ勉強に身が入りませんでした。
私は電験三種の合格を目指す者として、初心者の立場からスタートしました。3年8ヶ月と4回の受験を経て、合格を勝ち取りました。しかしその3年8ヶ月の間、勉強方法について悩み様々な方法を実践し、たくさんの遠回りをしてきました。
試行錯誤の中でたどり着いた、初心者でも効率よく法規を攻略する方法をこの記事にまとめています。
この記事では、ゼロから法規の勉強を始める初心者にありがちな悩みについての解決方法、効率的な勉強の進め方を解説しています。この記事を読めば、法規の勉強を始める初心者が直面する悩みを解決することが出来ます。
私が合格するまでに実践した電験三種 法規の勉強方法のノウハウを凝縮しました。初心者が電験三種 法規を勉強する際に直面する悩みの解決方法を知りたい方は、最後まで読んで下さい。
1.【知識問題】(A問題) 初心者のための勉強法
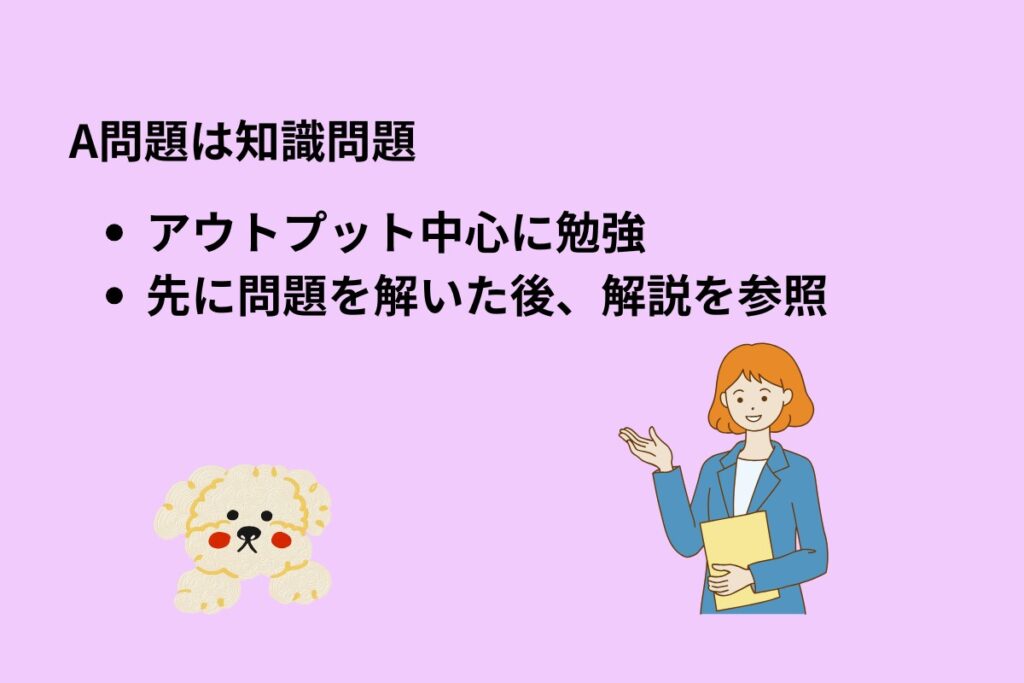
- 法規はどの参考書も文字ばかりで眠くなるんだけど…
- 眠くならずに集中して勉強する方法を教えて
法規の勉強を試みたが、他の科目と違い暗記であり仕事の疲れもあってウトウトしてしまい、合格出来る気がしない。そんな方へ、法規の勉強方法をお教えします。
1⁻1.アウトプット中心に勉強
アウトプット中心に勉強しましょう。
アウトプットすることで交感神経を優位にし、脳を活性化させることが出来ます。つまり、戦闘態勢に入ることが出来ます。
参考書を読むと法律の条文が記載してあります。難しい言葉で書かれた文章の羅列は、思考停止に陥ります。考えながら問題を解くことによって脳が活性化し、集中して勉強することが出来るでしょう。
1⁻2.先に問題を解いた後、解説を参照する
記憶の定着率をアップさせるため、以下の手順で勉強しましょう。
- 過去問を解く
- 過去問解説を読む
- 過去問の記載箇所を参考書で確認する
交感神経優位に働き、集中して勉強することが出来ます。
ところで…
- 解いたことのない問題でいきなりアウトプットってどうやるの?
- 初めての勉強で過去問から解くなんて出来るの?
あなたのお考えの通り、最初から正解することは出来ません。おすすめの市販されている教材を繰り返し勉強し、過去問を記憶に定着させます。
幸いなことに、現在電験三種は過去問中心の出題となっています。アウトプット中心で勉強し過去問題をマスターしましょう。
あなたの電験三種 法規科目の合格が見えてくるでしょう。
2.【計算問題】(B問題) 初心者のための勉強法
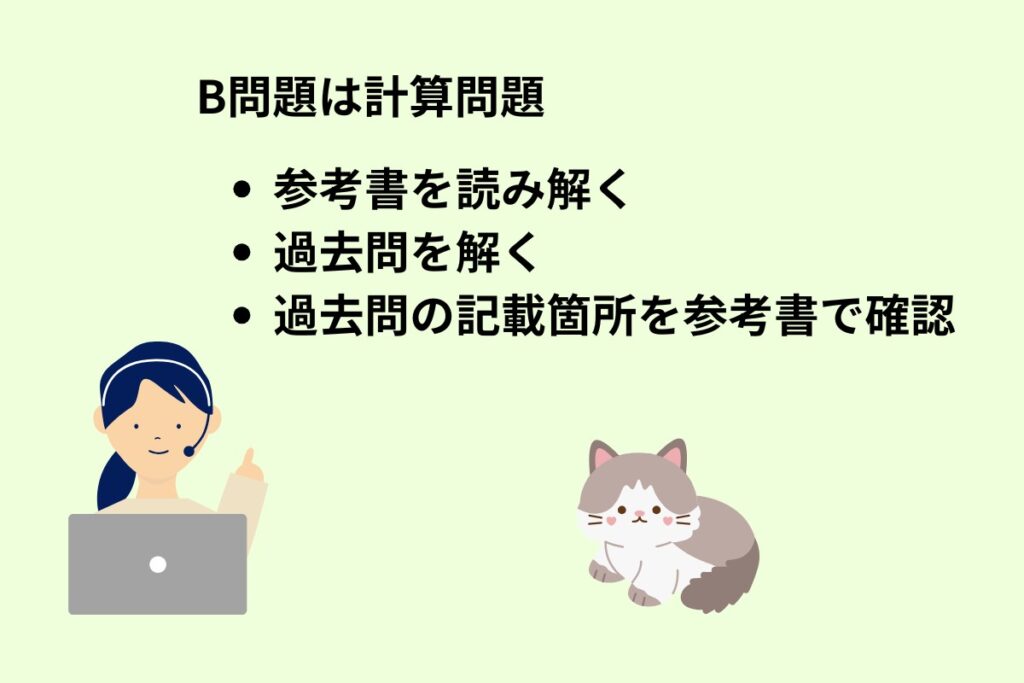
- 計算問題はどう勉強するの?
- 他の3科目と同じ勉強法でいいのかな
- 合格点の取れる方法を教えて
法規、計算問題の勉強方法をお教えします。
- 参考書を読み解く:公式は、ペンを取ってノートに書き理解すること。
- 過去問を解く
- 過去問の記載箇所を参考書で確認する
理論や電力で勉強した知識を必要とする問題も出題されます。法規を最後に勉強した方が良いと多くの方が考えている理由です。
私の知り合いで、法規が難関であったと言われている2019年、合格基準点が49点 だった時に、文系で暗記が得意だからと法規のみ勉強し、法規のみ合格した方がいました。(法規を最後に勉強した方が良いと一概には言えないと考えています。)
3.初心者の最初の悩みである教材の選び方
- 本屋に行ったけれど、参考書が沢山あってどれを選んだらいいの?
- 法規はどの参考書も文字ばかりで眠くなるんだけど…
- 眠くならずに集中して勉強出来る教材を教えて
15年分以上の過去問題を繰り返し解くことにより、合格に大いに近づきます!

| おすすめ順 | 過去問題集 | おすすめ度 |
| 1 | 「電験三種 法規の20年間」 | ★★★★★ |
| 2 | 「みんなが欲しかった!電験三種の10年過去問題集」 | ★★★★ |
3-1.「電験三種 法規の20年間」(電気書院)を攻略する
私自身、こちらの過去問題集を10回以上繰り返しています。分野別にまとめられているので、弱点の克服に最適な教材となっています。
1⃣分野別にまとめられている過去問題集
この教材は分野別に過去問題をまとめて提供しています。特定の分野について集中的に学習を進めることができます。苦手分野の克服には最適な教材と言えるでしょう。
2⃣過去問の解説が詳細
過去問の解説が詳細に記載されており、問題の理解を深めるのに役立ちます。
電気書院の過去問シリーズの「法規」科目に嬉しい変更点があります。
- 2025年版まで: 15年分収録
- 2026年版から: 20年分収録にパワーアップ!
法規のカバー範囲がぐんと広がり、さらに頼れる一冊に進化しています。
3-2.「みんなが欲しかった! 電験三種の10年過去問題集」(TAC出版)を攻略する
本を切り離しで分冊できる便利な形式です。移動時間などを活用して学習することができます。
構成は
- 過去問題集
- 理論(解答解説編)
- 電力(解答解説編)
- 機械(解答解説編)
- 法規(解答解説編)
計5冊に分冊できます。
1⃣解答解説編
②③④⑤の解答解説編には、小さな文字ですが問題文は記載してあります。勉強したい分野1冊を持ち歩いて学習することが可能です。
2⃣過去問題集
過去問題集を利用し、時間内に問題を解き、自己採点を行い、自分の実力を評価しましょう。
答案用紙の記入シートも付属しており、本番さながらの状況で実際に問題を解くことができます。
※私は答案用紙の記入シートをコピーして使用しました。
3⃣分冊形式教材の有効活用
電験三種の学習において、この分冊形式教材は効率的で便利な選択肢と言えるでしょう。
- 移動時間やスキマ時間を活用して、効果的な学習を実現しましょう。
- 出題傾向を理解し、合格に向けて自信をつけていきましょう。
2026年度版は2024年12月24日より販売予定です。Amazon、楽天市場、Yahoo! ショッピングにて予約受付中です。
お急ぎの方は、2025年度版も販売しています。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
おすすめのテキストの選び方につきましては【初心者向け】電験三種参考書&問題集の選び方と使い方完全ガイドで説明しています。リンクを貼っておきますのでこちらをご参考にして下さい。
4.法規試験の点数配分
電験三種 法規の点数配分です。
| 電験三種 法規 | 配点 |
| A問題 暗記問題(10問) | 60点 |
| B問題 計算問題(3問×2) | 40点 |
合計100点の配点となっています。
※ B問題は、まれに暗記問題が出題される場合もあります。
5.計算問題から仕上げる
計算問題はパターンが決まっていて、パターンの数も多くはないので計算問題から仕上げましょう。
試験問題の内容次第では、計算問題は満点を狙えます。
6.解説を読んでも理解できない計算問題の場合、解き方をそのまま覚える
解説を読んでも理解できない場合の対処方法についてお伝えします。
私が勉強していた時も実際に解説を確認した時に、なんでこうなるのか理由の分からない問題がいくつかありました。解説を読んでも理解出来ない場合、解き方をそのまま覚えてしまいましょう。
勿論、基本は理解した方が良いです。しかし理解できない場合でも過去問と同じ構成の問題であれば、この方法で対処できます。
合格することが目的ですので、解説が理解できない場合、解き方をそのまま覚える方法で勉強していきましょう。
7.知識問題も過去問はパーフェクトを目指そう
B問題の計算を満点(40点)目指して勉強すればなんとかなると言った情報をよく目にしていました。確かにB問題で満点(40点)とれば、A問題で点数が半分(30点)だったとしても70点になります。
合計60点で合格ですので、この計算で行けば余裕を持って合格出来ます。
私は、令和3年の試験ではこの情報を鵜呑みにし、計算の勉強はしっかり対策し臨みました。
結果、計算問題は1問落とし33点/40点でした。暗記問題は10問中3問しか解けず、18点/60点となってしまい、51点で不合格となりました。
計算問題は満点目指すのは前提ですが、暗記科目も満点目指すつもりで勉強しましょう。最近の傾向として過去問題からの出題が中心となっているので、暗記科目も得点しやすくなっていると言えます。
8.年度別にまとまっている過去問も学習しよう(①の分野別と②の年度別、両方学習する)
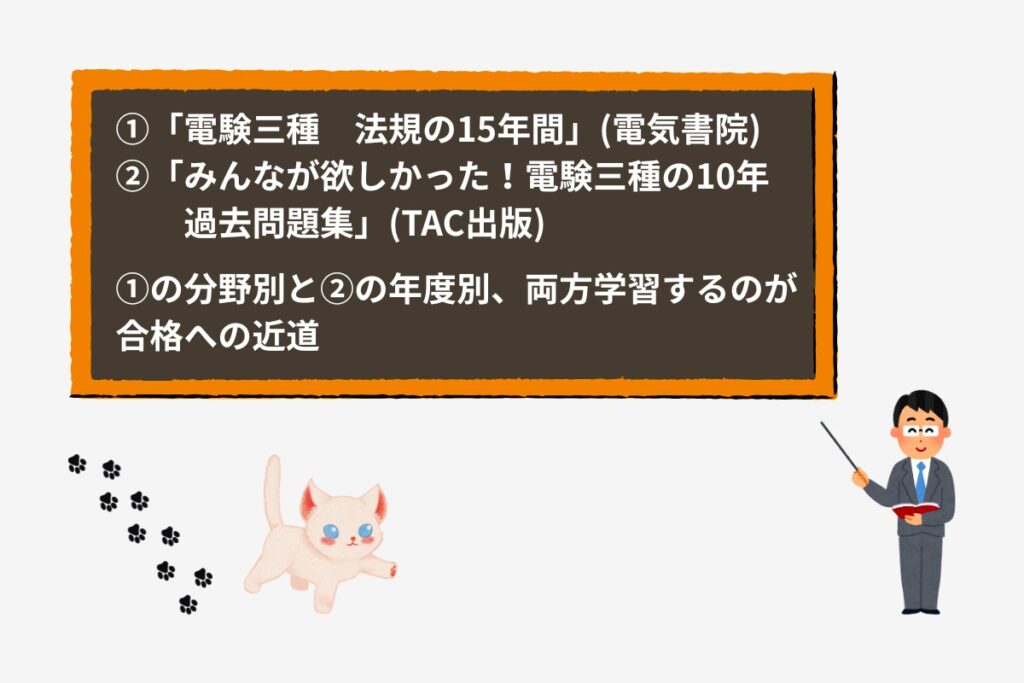
先ほどご説明した過去問題集についておさらいします。
- 「電験三種 法規の20年間」(電気書院)
- 「みんなが欲しかった! 電験三種の10年過去問題集」(TAC出版)
こちらのテキストを繰り返すことにより、合格に向かって大きく前進します。
過去問対策は、①の分野別と②の年度別、両方学習するのが合格への近道です。「出題傾向別での学習」と「実戦形式の学習」の両面から力をつけましょう。
同じ過去問なのに、やる必要あるのだろうかとお考えですか。年度別の過去問題集を取り組む理由について考察していきましょう。
8‐1.出題の仕方が分かる
例えばA問題の1問目と2問目には電気事業法が出題される確率が高いなど、何問目にどの分野が出題される確率が高いのかが分かります。
出題傾向が分かれば、対策が立てやすくなります。
8‐2.時間配分や問題を解く順番を考えることが出来る
試験本番前までに、時間配分・解く順番を決めておくことが出来ます。
私の場合は計算問題から先に解きました。得意な分野から先に解き、苦手な暗記問題を後回しにして、残りの時間で考えながら解く方法を取りました。
8‐3.同じ問題でも、解説の内容が違う可能性がある
過去問題集を複数冊使用することにより他の角度からの見方も考えることにより、知識の理解度が高まります。
9.暗記しづらい公式は、こじつけの語呂合わせで覚えよう

暗記の得意な方はそのまま暗記して頂きたいと思いますが、例えば電線のたるみなど、暗記する必要のある公式でなかなか覚えづらいものがあります。
D=WS²/(8T)
D:電線のたるみ(m) W: 電線1mあたりの合成荷重(N/m) S: 経間(m) T: 電線の水平張力(N)
電線のたるみの公式につきましては、私の覚えた方法は正直お伝えしづらいですが、ここは勇気を持ってご報告します。
(電線のたるみの上で)ハト(8T)がダブル(W)で2回せいこう(S²)した
※せいこうはあえて平仮名で書かせて頂きますので、漢字の変換はご想像にお任せします。
覚えづらい公式は、ご自身で覚えやすい語呂合わせを考えてみましょう。
10.まとめ
勉強の仕方のイメージは湧きましたか。
どのように勉強していこうか構成を考えることは大切です。どの順序でどのように勉強したら良いのか考えがまとまりましたら、勉強を開始しましょう。
令和4年度(2022年度)から年2回の試験になり、令和5年度(2023年度)からCBT方式が導入されました。試験の難易度を等しくする必要があるので、過去問中心の試験問題になっているものと考えられます。
電験三種を取得するチャンスが広がりました。繰り返し学習し、電験三種の合格を勝ち取りましょう。
この記事が、少しでも皆様のお勉強のご参考になれたら幸いです。
電気の初心者が電験三種を取得するまで、どのように悩み勉強してきたか、合格までの道のりを記載してある記事のリンクを貼っておきます。電験三種を合格するに当たりご参考になるかと思いますので、是非ご覧になって下さい。