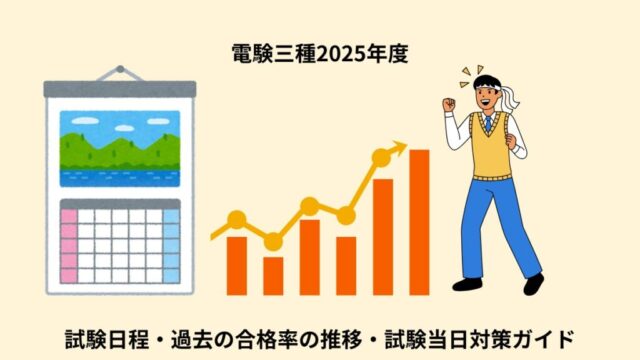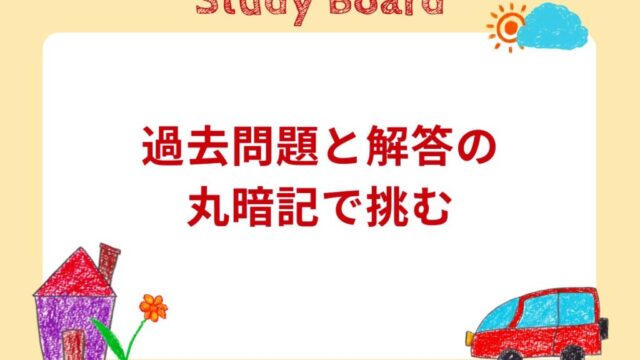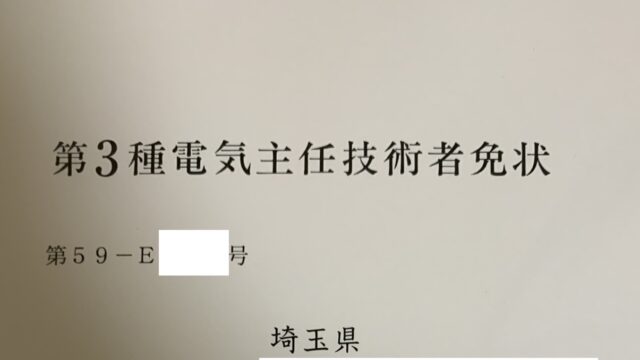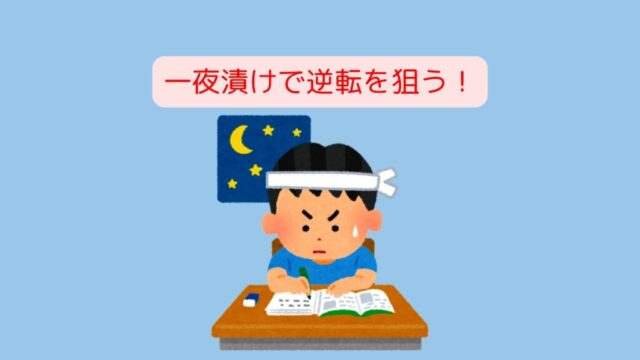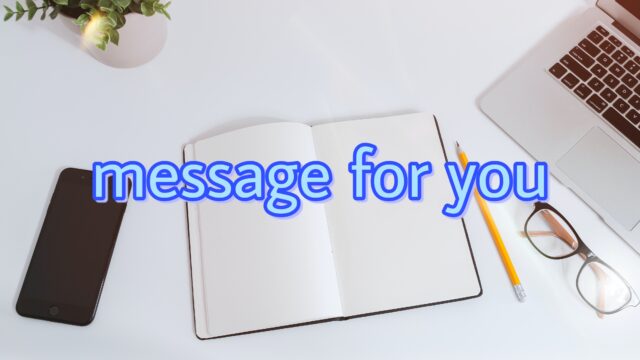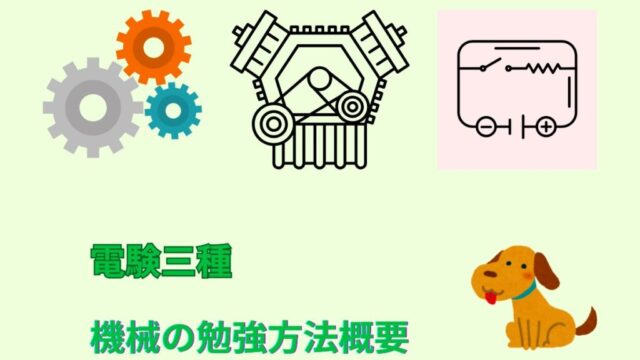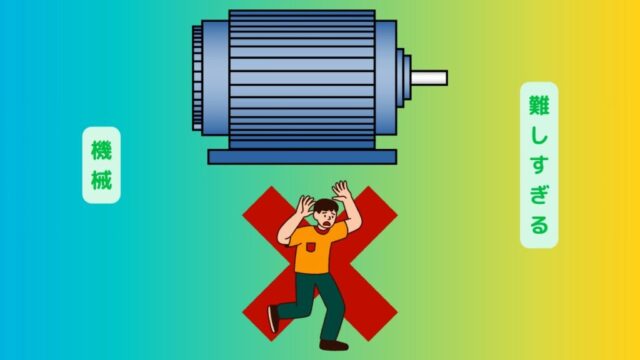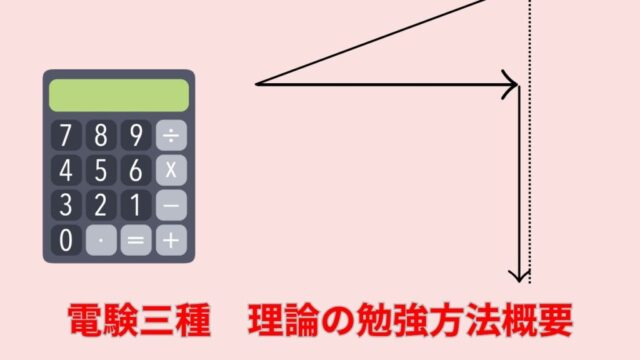【初心者用】電験三種 電力の出題傾向と攻略

- 今から電験三種 電力の合格を目指して勉強するんだけど
- 電気の勉強が初心者でどうやって勉強したらいいのか分からない
- 電力の出題傾向と攻略法が知りたい
- 勉強をコツコツと頑張るから、電力科目の合格出来る方法を教えて
電力の勉強を始めようとした初心者が、参考書・問題集を手に取ってみたものの何から始めたらいいのか分からずに挫折してしまうケースは非常に多いです。
私は電験三種の合格を目指す者として、初心者の立場からスタートしました。3年8ヶ月と4回の受験を経て、合格を勝ち取りました。しかしその3年8ヶ月の間、勉強方法について悩み様々な方法を実践し、たくさんの遠回りをしてきました。
この記事では、初心者向けに電験三種の電力の出題傾向と効果的な攻略法を解説します。電力の出題内容は幅広く、発電、変電、送電、配電など多岐にわたります。
出題傾向を分析することにより、合格へ大いに近づくことができます。合格に向けたステップをスムーズに踏み出せるよう、詳しく解説していきます。
電験三種試験を初めて受験する方に向けた役立つ情報を提供し、合格への第一歩を踏み出す手助けをします。電力の出題傾向と攻略方法を知りたい方は、最後まで読んで下さい。
1.電力の出題傾向

初心者にとっては、試験の出題傾向を理解し、戦略的に学習することが合格への第一歩です。毎年の分野別の大よその出題傾向になります。
出題分野と出題数になります。
| 分野 | 出題数 |
| 水力発電 | 1~3 |
| 汽力発電 | 2~4 |
| 原子力発電 | 約1 |
| その他発電 | 約1 |
| 変電 | 1~3 |
| 送電 | 1~3 |
| 地中送電 | 1~3 |
| 配電 | 1~6 |
| 電気材料 | 約1 |
| その他 |
電力の出題傾向を理解し、効果的な対策を講じることは、非常に大切です。
- 出題分野と出題数は分かったけれど、それからどうしたらいいの?
- どのように対策をしたらいいのか分からない。
- 電力の具体的な攻略方法を教えて。
電力攻略の要点。出題傾向を把握したあとやるべき事!
- 出題数の多い分野から勉強する。
- 計画的な学習を行う。
- テキストを使用して試験範囲を把握し、過去問題集で試験形式を理解する。
- 定期的な復習と過去問題の解答を通じて知識を固め、幅広い視点から学ぶ。
試験対策として適切な準備を行い、試験日に自信を持って臨みましょう。
計画的な学習と実践が合格への近道です。合格を目指して、着実にステップを進めていきましょう。
次に、出題傾向に対する主な分野についての具体的な攻略を解説します。お手元の参考書と照らし合わせながら内容を確認してみましょう。
具体的な公式・解法については、ご自身の教材で勉強してください。
合格のためのおすすめのテキストが知りたい方はこちらの記事を読んで下さい ⇒ 【電験三種】合格のためのおすすめ参考書・問題集・過去問題集
2.電力の攻略

電力科目の対策として、過去問題の活用が非常に重要です。
電力科目は、文章問題約5割、計算問題約5割です。特に文章問題はイメージしやすいものが多いです。電気の勉強が初心者の方でも、取り組みやすい科目です。現在は過去問題から多くの問題が出題されます。難易度が高い問題でも、過去問をしっかり対策すれば対応可能です。
過去問題に取り組むことで、出題傾向をつかみやすくなり、理解が深まります。もし過去問を解いていて、どうしても理解出来ない問題があった場合は、問題と解答をセットで覚えてしまいましょう。確実に点を取れる部分を増やすことが大切です。
現在では過去問題から多くの問題が出題されるため、全ての過去問題を解けるように準備しておくことが大切です。難易度の高い問題も含めて対策を続けて行きましょう。
出題傾向に対する主な分野についての具体的な攻略を解説します。お手元の参考書と照らし合わせながら内容を確認してみましょう。
具体的な公式・解法については、ご自身の教材でご確認ください。
2-1.水力発電
①水力発電の種類の理解
水力発電は多彩な形態を持ち、水路式、ダム式、ダム水路式があります。特性と原理を熟知し、試験範囲内での重要事項を掌握しましょう。
②ベルヌーイの原理
流体の速度、圧力、高さの相互関係を理解します。
ベルヌーイの定理は、流体力学の基本的な原理で、流体の位置エネルギー、圧力エネルギー、運動エネルギーの間の関係を表す式です。水車やタービンによって水流から運動エネルギーが取り出され、このエネルギーが発電機で電力に変換されます。
ベルヌーイの定理は以下の式で表されます。
ここで、各項の意味は以下の通りです。
h+p/(ρg)+v²/(2g)=const(一定)
h:高さ(m)
p:圧力(Pa)
ρ:密度(㎏/㎥)
g:重力加速度(m/s²)
v:速度(m/s)
この式は、流体が静止している地点から流れている地点までのエネルギー保存の原理を示しており、流体力学や水力発電において非常に重要な概念です。試験では、この式を理解し、実際の問題に応用できることが求められます。
電力科目は、公式に代入すれば求まる問題がほとんどです。単位のミスは失点の原因になりますのでしっかり把握しておきましょう。
③揚水発電所
揚水発電所のエネルギー変換プロセスに重点を置き、効率向上について学びます。揚水ポンプの電動機出力と発電機出力の計算問題が出題されることがあります。
違いを理解し、使いこなせるようにしましょう。
④水車の多様性
ペルトン車、フランシス車、カプラン車などの水車のタイプと、それぞれの特性について理解を深めましょう。
⑤自動調速機
自動調速機は水力発電所で使用され、水車またはタービンの回転速度を制御する装置です。
自動調速機の計算問題は、公式があらかじめ問題文に記載されており、与えられた数値を代入すれば求まる問題がほとんどです。
※ただし、計算ミスしやすいので1つずつ整理しながら解きましょう。
2-2.汽力発電
①熱サイクルと火力発電の基本
燃料を燃やして発生させた蒸気を利用して電力を生み出す仕組みです。火力発電の基本を理解しましょう。
(例)汽力発電、内燃力発電、ガスタービン、コンバインドサイクルの特徴やランキンサイクル(汽力発電の流れ)など、その他用語の理解
②燃料の役割
石炭、ガス、石油などを燃焼させ、熱エネルギーを発生させます。化学式を用いた計算問題を解けるようにしましょう。
③汽力発電の効率計算
発電端電力、送電端電力、所内率、効率(ボイラー効率、タービン効率、タービン室効率、発電機効率、発電端効率、送電端効率)について公式を理解しましょう。
※計算問題が出題されます。過去問を通して、解き方を覚えましょう。
④ボイラーと蒸気
ボイラーは燃料の熱エネルギーを利用して蒸気を生み出し、この蒸気がタービンを駆動して電力を供給します。ボイラーに関する用語を覚え、理解しましょう。
(例)節炭器、空気予熱器、加熱器、再熱器、ドラムなどの用語の理解
⑤ランキンサイクル
ランキンサイクルは、蒸気を使ってエネルギーを作り出す仕組みのことです。
ランキンサイクルを理解するために、図やグラフを使って確認しましょう。
ランキンサイクルの図とP-V線図・T-S線図は、エネルギーの変化を視覚的に理解するのに役立ちます。
2-3.原子力発電
①PWRとBWR
- PWR(加圧水型)とBWR(沸騰水型)の特徴をそれぞれ理解しましょう。
- 原子炉内の名称、仕組みをきちんと覚えましょう。
②核分裂エネルギー
E=mⅽ²
E:エネルギー(J) m:質量欠損(㎏) c:光の速さ(m/s)
公式と単位を暗記し、数値を公式に代入し解けるようにしましょう。
2-4.その他発電
太陽光発電、風力発電、地熱発電、バイオマス発電などについても参考書を熟読し、過去問で出題されたものについて解けるようにしましょう。
2-5.変電
変電所、変圧器、避雷器についての問題はよく出題され、変電は一部計算問題も含まれますが、ほとんどが知識問題です。時々、長文問題が出題され、知識の理解が求められます。
したがって、参考書で内容を把握したら、過去の問題を綿密に説いて知識を確実に身につけましょう。
2-6.送電
送電線に関連する機材の名称や雷害についての比較(誘導雷、直撃雷、フラッシュオーバー、逆フラッシュオーバーなど)、コロナ放電とその対策、そして静電誘導と電磁誘導の違いなど、さまざまな用語に関する知識が問われます。
参考書を通じてこれらの用語や概念を習得したら、過去の試験問題を解いて知識を定着させましょう。正確な知識と理解が成功への鍵となります。
2-7.地中送電
地中ケーブルの種類(CVケーブル、OFケーブル、CVTケーブルなど)や地中ケーブルの敷設方式(直接埋設式、管路式、暗きょ式)は理解し覚えましょう。
地中送電は覚えづらい用語など多いですが、地道に勉強し過去問を通じて克服しましょう。
2-8.配電
①配電系の構成機材
配電系の構成機材について、用語を覚えましょう。
引き込み線、ケッチヒューズ、支持物、支線、中条変圧器、避雷器、高圧カットアウトなどがあります。
②配電方式
配電方式とその仕組みを理解しましょう。放射状方式、ループ方式、バンキング方式、スポットネットワーク方式などがあります。
③電圧降下、電力損失
電圧降下や電力損失に関する計算問題も出題されます。あなたのテキストを利用して公式を理解し、過去問を通じて問題に慣れましょう。
公式を使いこなせるようになるまで繰り返し問題を解く練習をしましょう。計算ミスには要注意です。
電圧降下の公式は、単相2線、単相3線、三相3線それぞれの公式について理解しましょう。
2-9.電気材料
①導電材料
導電材料について、その定義と条件を理解しましょう。導電材料の温度変化に関する計算問題が出題されることがあります。
これらの問題のほとんどは公式を使えば解けますが、公式がやや長いことに注意し、計算ミスを避けましょう。
②絶縁材料
絶縁材料(固体、液体、気体)の特性や違いについて理解しましょう。
気体絶縁材料の一つである六フッ化硫黄(SF₆)に関する問題が時折出題されますので、特徴をよく覚えておきましょう。
③磁性材料
磁性材料の種類や特性について理解しましょう。
ヒステリシスループに関する問題は時々出題されます。ヒステリシス曲線を自分で描きながら、残留磁気や保持力が何を意味するのかを覚えましょう。
2-10.その他
その他の問題も過去問題集は全て解いて、知識を深めておきましょう。

合格のためのおすすめのテキストが知りたい方はこちらの記事を読んで下さい ⇒ 【電験三種】合格のためのおすすめ参考書・問題集・過去問題集
3.電力の出題傾向と対策のまとめ
最初は難しい部分もあるかもしれませんが、じっくりと基礎から進んでいけば、問題が解けるようになります。様々な分野が出題されますが、一つひとつじっくりと理解していくことが大切です。
テキストや過去問題集を積極的に活用し、自信をつけていただけたらと願っています。電力の勉強は、進むにつれて学ぶ楽しさの魅力を感じることができるでしょう。
あなたの合格へのお力添えができればと思います。