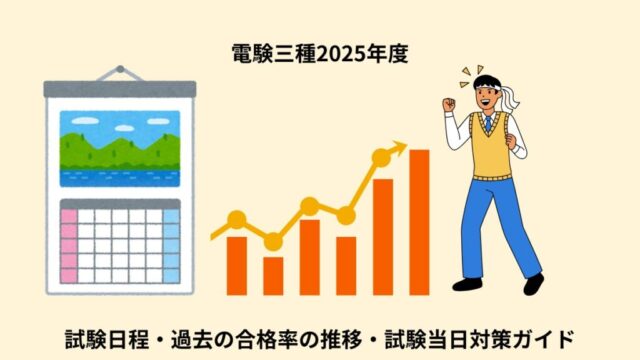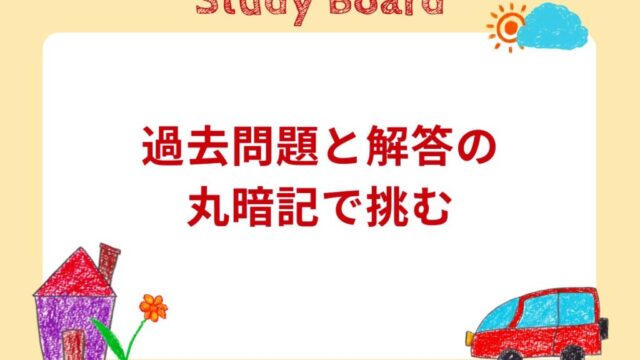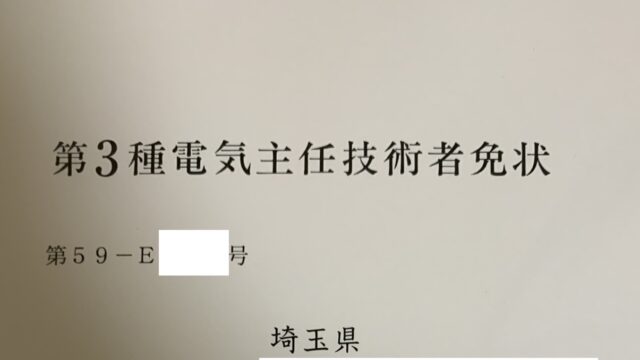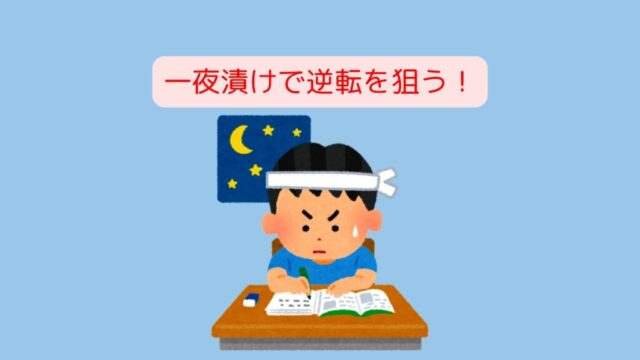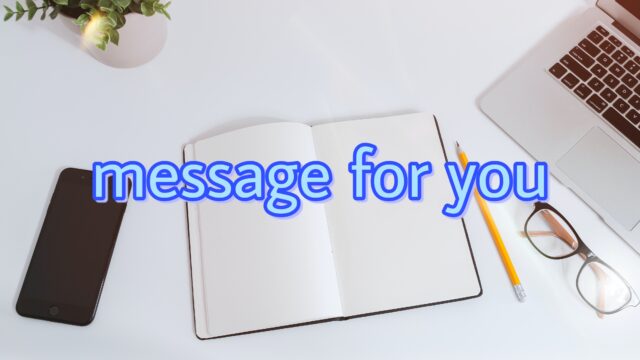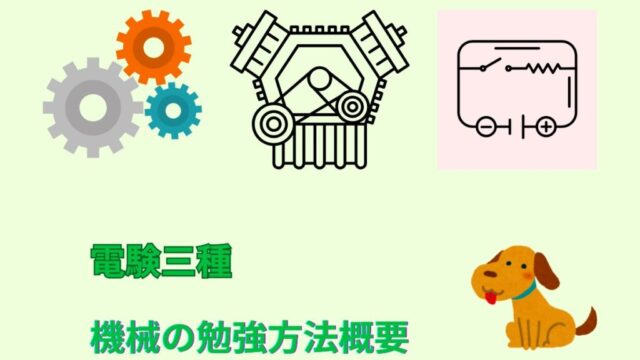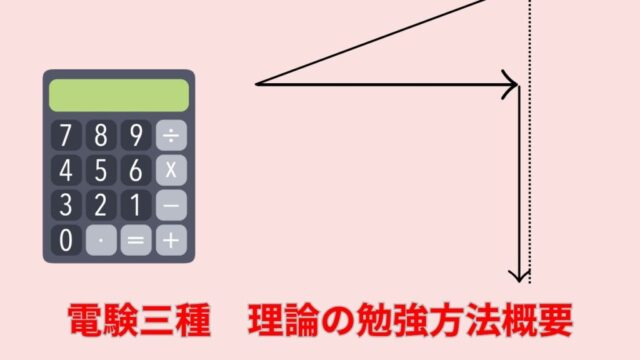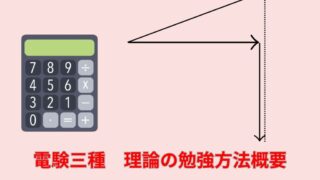【初心者用】電験三種 電力の勉強方法概要

- 教材やネット情報が多すぎて、教材の選び方や勉強法が分からない
- 電力科目は取り掛かりやすそうに見えるが、実際の難易度が気になる
- コツコツ勉強するため、合格までの具体的な方法を知りたい
電力の勉強を始めようとした初心者が、市販の参考書・問題集を確認すると、理論より勉強し易そうと感じる方が多いです。では実際のところ、どのようにすれば電力科目に合格することが出来るのだろうか。
私は電験三種の合格を目指す者として、初心者の立場からスタートしました。3年8ヶ月と4回の受験を経て、合格を勝ち取りました。しかしその3年8ヶ月の間、勉強方法について悩み様々な方法を実践し、たくさんの遠回りをしてきました。
この記事では、ゼロから電力の勉強を始める初心者にありがちな悩みについての解決方法、効率的な勉強の進め方を解説しています。この記事を読めば、電力の勉強を始める初心者の、最初に直面する悩みを解決することが出来ます。
私が合格するまでに実践した電験三種 電力の勉強方法のノウハウを凝縮しました。電験三種 電力を勉強する際、最初に直面する悩みの解決方法を知りたい方は、最後まで読んで下さい。
1.初心者のための勉強法

- ダムや水車の種類、火力発電や原子力発電の仕組みなどイメージはしやすそう
- 鉄塔も見たことあるからイメージは出来る
- でも用語を覚えるのは苦手なんだけど
知識問題、計算問題共に、以下の手順で繰り返し勉強しましょう。
- 参考書を読み解く
- 過去問を解く
- 過去問の記載箇所を参考書で確認する
用語、覚えられるかな。そもそも繰り返し勉強するのが苦手なんだけど…
まずは勉強の計画を立てましょう。
- 具体的な目標を決める
- 短期目標・長期目標を設定し、繰り返し勉強する
- 柔軟性を持たせ、達成できる目標を設定する
合格のためのおすすめのテキストが知りたい方はこちらの記事を読んで下さい ⇒ 【初心者向け】電験三種参考書&問題集の選び方と使い方完全ガイド|【初心者用】電験三種 合格への手引き
2.効率的に勉強できる教材と特徴
効率的に合格を目指しましょう。私がもし今から勉強をはじめるとしたら、こちらの教材を使用します。私は電験三種試験合格までにいくつもの教材を使用しました。この記事を読んでいるあなたには最短距離で合格して頂きたいと考えています。
こちらの教材で勉強し、最短距離で合格を目指しましょう。
2-1.「電験三種 はじめの一歩(TAC出版)」で、基礎力不足を克服

電力の参考書・問題集を勉強していて理解出来ない場合、計算問題の基礎力が不足している可能性があります。基礎力が不足していると、いくら勉強しても理解することが出来ません。
電力科目では電気計算の基礎が必要不可欠です。中学生・高校生の時に数学の勉強が苦手で勉強してこなかった場合、電力の問題を解くための前提知識が足りていない可能性があり、電力のテキストを読んでも理解することが出来ません。
理解出来ないものをいくら読んでも、効率が悪いです。あなた自身の実力に合った勉強をしましょう。
電力の問題が難しく感じるなら、まずは基礎力を固めることが重要です。焦らずに段階を踏んで学習を進めましょう。基礎がしっかりしていれば、電力の問題もスムーズに理解できるようになります。
自分のレベルに合った教材を使い、基礎固めから始めることで、着実に合格へと近づけます。
私が実際に使用したおすすめのテキストです。こちらを使用して勉強しましょう。無理なく基礎力をつけることが出来ます。
2-2.「みんなが欲しかった!電験三種 電力の教科書&問題集(TAC出版)」で、過去問題を解ける力を身に付けよう

あなたの現在の実力より難易度の高い教材を利用しても、内容を理解することが出来ません。あなたのレベルにあった教材を利用しましょう。基礎的な教材を使い、段階的にレベルアップすることが重要です。
教材のレベルが自分に合っていないと、理解するのに時間がかかるだけでなく、モチベーションの低下につながります。特に電験三種のような専門性の高い試験では、基礎をしっかり固めることが合格への近道です。
私も、難易度の高い参考書を購入し勉強した経験があります。しかし、専門用語が多く、公式の意味もよく分からず、やった気にはなるのですが全然理解出来ていませんでした。
私が使用したのは有名な参考書だったのですが、自身の能力に合っていない参考書を使用したことが失敗の原因でした。
参考書の内容が理解出来ないのであれば、まずは電気計算の基礎力を身に付けることが先決です。電気計算の基礎力が身についたら、「みんなが欲しかった!電力の教科書&問題集」(TAC出版)を使用し勉強をして下さい。みんなが欲しかったシリーズは、図解が豊富で理解しやすい内容となっています。
学習する際、理解しやすい教材を利用して勉強することはとても大切なことです。私も実際に「みんなが欲しかった!電力の教科書&問題集」(TAC出版)を使用して合格しました。
自分のレベルに合った教材を選ぶことが、電験三種の合格への第一歩です。基礎計算を固めた上で、分かりやすい教材を活用し、段階的にレベルアップしていきましょう。無理に難しい教材を使わず、確実に理解を深めることが大切です。
真剣に悩んで、この記事を読んでいるあなたなら大丈夫。きっと合格できます。計算力をつけた後はこのテキストで勉強し、電力の知識を学んで下さい。
2-3.「電験三種 電力の20年間」と「みんなが欲しかった!電験三種の10年過去問題集」で総仕上げ

| おすすめ順 | 過去問題集 | おすすめ度 |
| 1 | 「電験三種 電力の20年間」 | ★★★★★ |
| 2 | 「みんなが欲しかった!電験三種の10年過去問題集」 | ★★★★ |
1.「電験三種 電力の20年間」(電気書院)を攻略する
私自身、こちらの過去問題集を10回以上繰り返しています。分野別にまとめられているので、弱点の克服に最適な教材となっています。
1⃣分野別にまとめられている過去問題集
この教材は分野別に過去問題をまとめて提供しています。特定の分野について集中的に学習を進めることができます。苦手分野の克服には最適な教材と言えるでしょう。
2⃣過去問の解説が詳細
過去問の解説が詳細に記載されており、問題の理解を深めるのに役立ちます。
2.「みんなが欲しかった! 電験三種の10年過去問題集」(TAC出版)を攻略する
本を切り離しで分冊できる便利な形式です。移動時間などを活用して学習することができます。
構成は
- 過去問題集
- 理論(解答解説編)
- 電力(解答解説編)
- 機械(解答解説編)
- 法規(解答解説編)
計5冊に分冊できます。
1⃣解答解説編
②③④⑤の解答解説編には、小さな文字ですが問題文は記載してあります。勉強したい分野1冊を持ち歩いて学習することが可能です。
2⃣過去問題集
過去問題集を利用し、時間内に問題を解き、自己採点を行い、自分の実力を評価しましょう。
答案用紙の記入シートも付属しており、本番さながらの状況で実際に問題を解くことができます。
※私は答案用紙の記入シートをコピーして使用しました。
3⃣分冊形式教材の有効活用
電験三種の学習において、この分冊形式教材は効率的で便利な選択肢と言えるでしょう。
- 移動時間やスキマ時間を活用して、効果的な学習を実現しましょう。
- 出題傾向を理解し、合格に向けて自信をつけていきましょう。
2026年度版は2024年12月24日より販売予定です。Amazon、楽天市場、Yahoo! ショッピングにて予約受付中です。
お急ぎの方は、2025年度版も販売しています。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
お勧めの参考書・問題集などにつきましては「【初心者向け】電験三種参考書&問題集の選び方と使い方完全ガイド」の記事で詳しく解説しています。リンクを貼っておきますのでこちらをご参考にして下さい。

3.電力科目の特徴
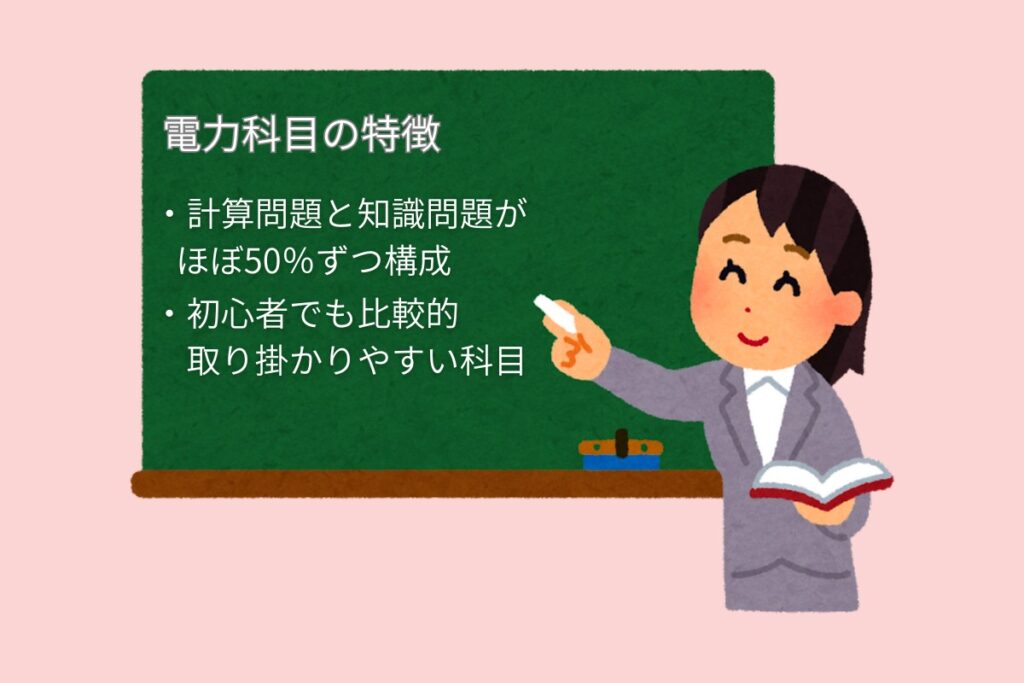
- 計算問題と知識問題がほぼ50%ずつ構成されている
- 初心者でも比較的取り掛かりやすい科目
理論や機械よりもイメージしやすく、楽しみながら学べる分野です。
発電・送電・配電といったテーマは、日常生活とも関わりが深く、図や写真でイメージしやすいからです。また、送電線の構造や発電所の種類など、視覚的な情報と結び付けて覚えられる知識問題が多く、理解や暗記のハードルが低くなります。
例えば、送電線の支持物の名称(鉄塔や電柱の部品名)は図解と一緒に学べば記憶に残りやすく、読んでいて楽しい分野です。さらに水力発電・火力発電・原子力発電といった発電方式は、ニュースや学校で聞いたことがあるテーマのため、初心者でも興味を持ちやすい傾向があります。興味が湧くテーマから順に学習を進めれば、自然と知識が定着します。
このように、電力科目は学びやすく興味を持ちやすい内容が多いため、初心者が最初に着手する科目としてもおすすめです。計算と知識の両面をバランスよく学び、興味を持ったテーマから攻めることで、効率よく得点力を伸ばせます。
学習が面白いと思えれば自然と知識も身についてきます。
4.電力科目の計算問題と知識問題

4-1.計算問題
計算は、高校数学の物理の知識が必要になります。電力の学習では公式をそのまま覚えたものもいくつかありました。但し試験で覚えた公式が使えないと意味がないので、公式を使いこなせるようになるまで勉強しましょう。
どの公式は本質を理解し、どの公式は暗記すればいいのか、難しい部分ではあります。公式の導き方が参考書に記載されている事項または過去問で問われたものに関しては導き方から理解し、記載のない公式はそのまま覚えてよいと思います。
また、単位は必ず覚えましょう。
単位を間違えやすい公式を一つご紹介します。
E=mc²
E:エネルギー(J) m:質量欠損(㎏) c:光の速さ(m/s)
原子力発電の分野で出題される公式です。質量欠損(m)の単位は㎏であり、エネルギー(E)の単位はJ(kはつきません)です。忘れやすいので要注意です。
光の速さC=3×10⁸(m/s)は、問題文に与えられない場合もありますので、暗記しておきましょう。代入すれば答えの出る問題もありますが、単位をミスするとその時点で失点します。
また、公式の通り光の速さCは二乗しなければなりません。落ち着いて計算することが大切です。
この公式を使用する過去問題をご紹介します。

「出典:平成23年第三種電気主任技術者 電力科目 A問題 問4」
解説は割愛しますが、答えは(1)です。
電験三種の計算問題は、間違えて答える可能性のある解答欄が、マークシート解答の選択一覧にあることが多々あります。単位を覚えていないと失点します。
単位の暗記は超重要です。解き方は分かっていたのに、単位の変換をミスして5点失ったら悔しいですし、単位のミスが合否を分ける場合もあります。
4-2.知識問題
参考書を読む時は、読書する時よりスローペースの感覚で、一行ずつ読み解いていきましょう。参考書を最初に読んだ段階で100%暗記しようとせずに1冊の参考書を読破しましょう。そして1度で理解するのは難しいこともありますので、出来れば3回繰り返し読みましょう。
暗記しづらい問題に関しては、実物をイメージしながら解きましょう。
例えば、以下の問題について考えます。

「出典:平成24年第三種電気主任技術者 電力科目 A問題 問2」
正式な解法は過去問題集などを確認して頂きたいと思いますが、私の覚え方で実物をイメージする方法の例をご紹介します。
気力発電所のタービン発電機と、水車発電機をイメージして下さい。
感覚的に水車発電機の方が、回転速度がゆっくりだと感じませんか。
タービン発電機の方が回転速度は高いですので、(1)、(3)、(5)のどれかになります。
次に、(1)、(3)、(5)は(エ)と(オ)は答えが同じですので、(イ)と(ウ)を考えることにより答えが導き出せることになります。
次に(ウ)を考えていきます。
タービン発電機は、水車発電機に比べて、くるくると早く回転する感じがしませんか。
くるくると早く回転するので、円筒形だから答えは(3)になります。
正式な解答を理解して覚えるのが一番良いですが、なかなか覚えられない場合、こうしてイメージしながら暗記していく方法も手段の一つである考えています。
但し実際に過去問題集の解説を読む時は、(ア)~(オ)の全ての問いについての解法の考え方について読み解いて下さい。
5.楽しみながら勉強する

楽しみながら勉強することで集中力は上がりますし、勉強の吸収力もアップします。
4-2でお話したように、イメージしながら覚えていくと楽しいです。ただ単に参考書とにらめっこしていても、覚えることはたくさんありますし眠くなります。
私はノートを使用し図や計算式を書きながら覚えました。(ノートは30冊以上使用しましたが、勉強量や勉強時間につきましては、今後記事にしていきたいと思います。)
実物を見たことないものについてはイメージしづらいものもあります。
イメージ出来ない時はYouTubeで検索すると大抵のものは見つかります。4-2でお話しした問題にもありましたタービン発電機や水車発電機も、検索すると分かりやすい動画がヒットします。
動画も見すぎると時間があっと言う間に過ぎてしまいますが、楽しいし理解も深まるので、是非YouTubeも有効活用しましょう。
6.過去問を反復し知識の定着を図る
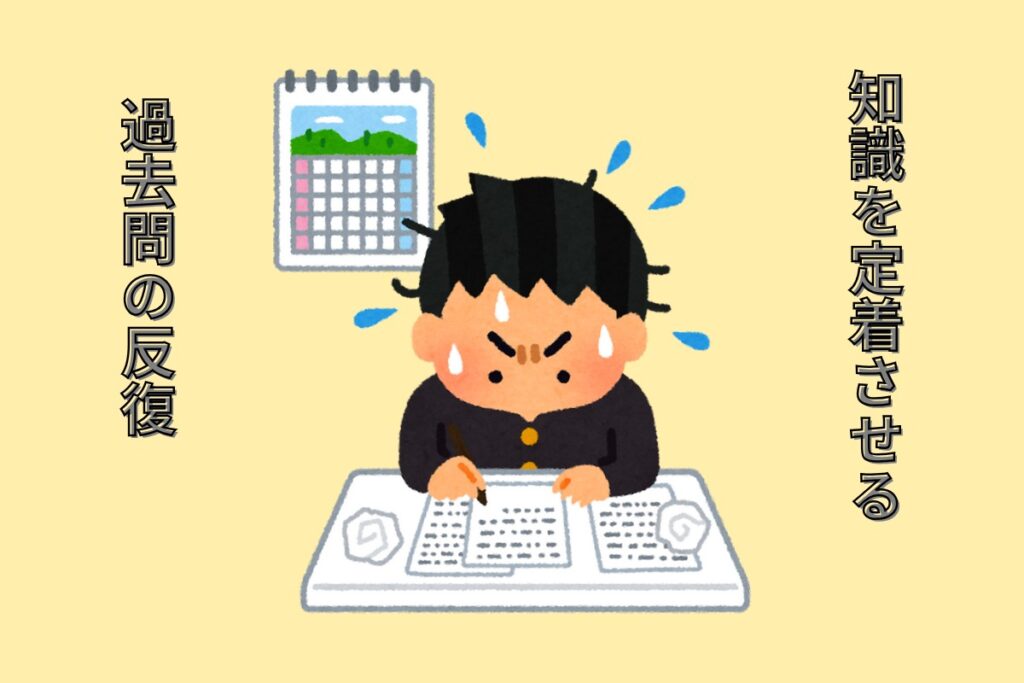
2023年(令和5年)上期の電験三種試験では、過去問から多く出題されました。過去問を多く解くことが合格への道であろうと、皆様方考えているでしょう。
基礎力が身についた後は過去問を繰り返し解きましょう。出来れば過去15年分から20年分解いた方がよいでしょう。
過去問を暗記できればそれに越したことはないですが、量が膨大です。
参考書を熟読しある程度理解した後に過去問題集を読み解き、解説が理解出来なかったら参考書へ戻り、また問題を解いていく方法がベターでしょう。
参考書⇒過去問⇒参考書 を繰り返す。
アウトプット中心で勉強することにより、知識の定着を図ります。
7.電力の勉強をされる方へ応援メッセージ
これから電力の勉強をはじめるあなたへ、勉強方法のイメージは湧きましたか。
電験三種に合格すれば、会社によっては資格手当がつき、職場での評価も上がる可能性があります。
コツコツ勉強し、是非合格を勝ち取って頂きたいです。
これから学習していくに当たり、この記事が少しでもご参考になりましたら幸いです。
電気の初心者が電験三種を取得するまで、どのように悩み勉強してきたか、合格までの道のりを記載してある記事のリンクを貼っておきます。電験三種を合格するに当たりご参考になるかと思いますので、是非ご覧になって下さい。
リンクはこちら⇒【電験三種】合格体験記で学ぶ!電気の勉強が初心者でも合格できる!