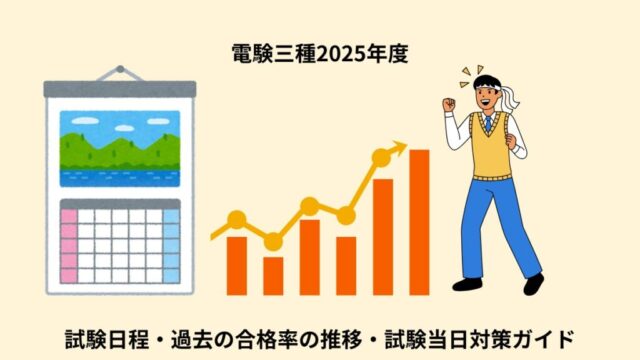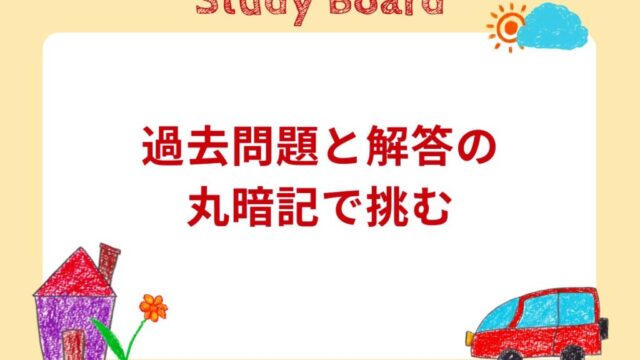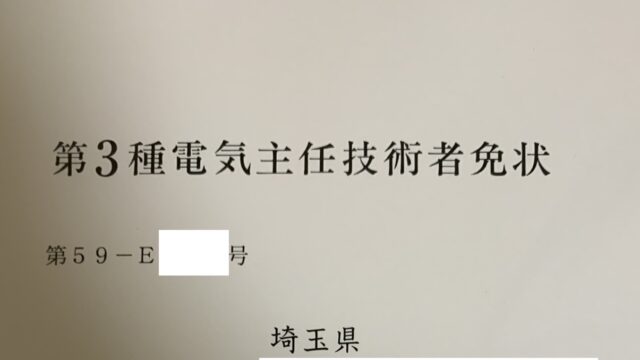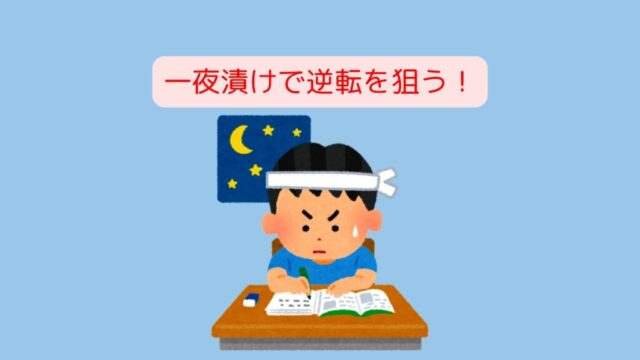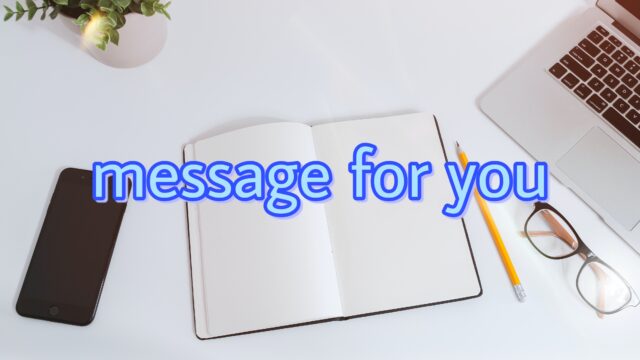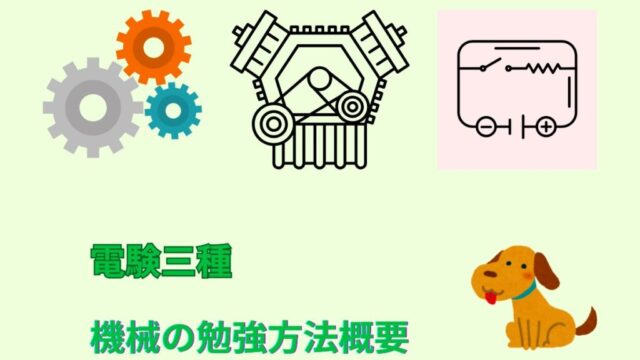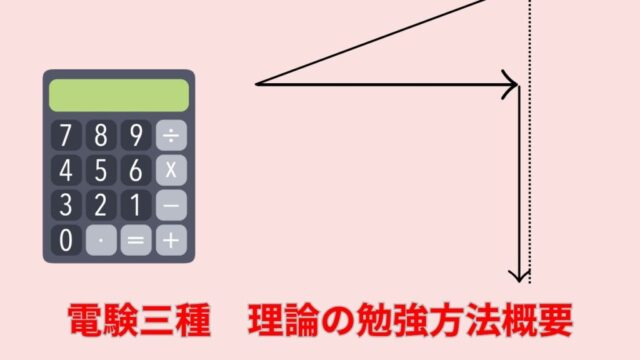【電験三種】機械の勉強が難しすぎて諦めようと思った時に読む記事
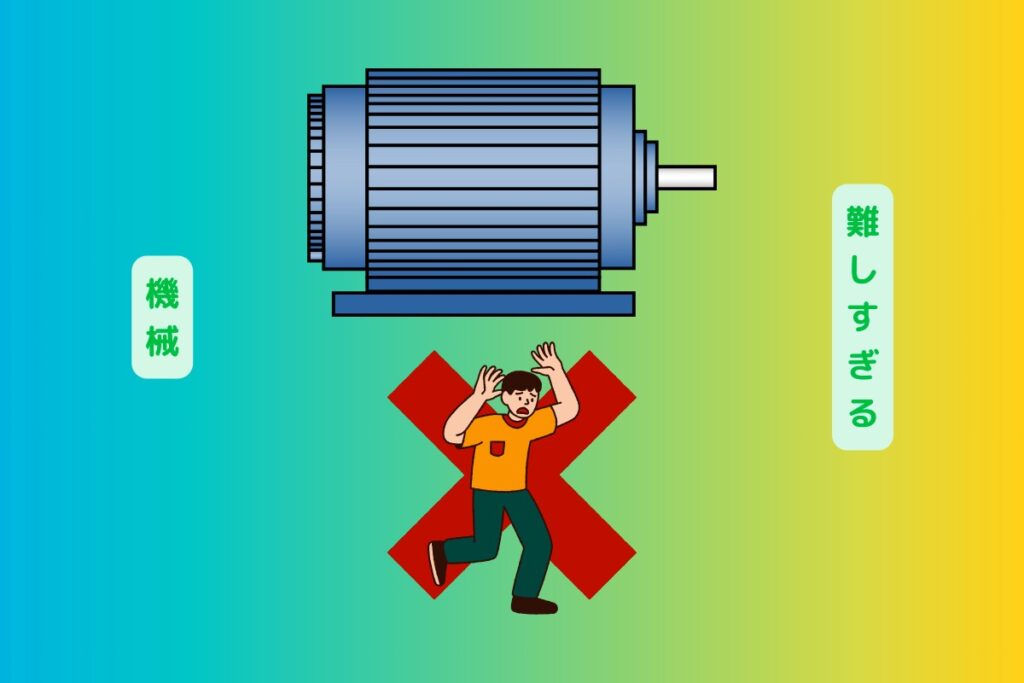
- 機械の勉強をはじめたけれど、まるで暗号にしか見えない…
- 理論よりもずっと難しくて、何をどう勉強すればいいかわからない…
- 4科目全部合格なんて、本当に可能なの?
そう感じているのは、決してあなた一人ではありません。
電験三種の機械科目は、多くの受験生がつまずく最難関の科目です。特に、教材を勉強してもモーターの動きをイメージするのが難しく、問題を解く以前に「教材を読んでも何が書いてあるのか分からない」と感じる人も少なくありません。
実は、私も同じ経験をしました。
私は電験三種の合格を目指す者として、初心者の立場からスタートしました。3年8ヶ月と4回の受験を経て、合格を勝ち取りました。しかしその3年8ヶ月の間、勉強方法について悩み様々な方法を実践し、たくさんの遠回りをしてきました。
機械科目を苦手と感じる人の気持ちは、痛いほど良く分かります。私も最初、機械は本当に苦手でした。難解だと思っていた理論よりも、機械は更に難しいと感じました。そもそも何が書いてあるのか分かりませんでした。
そんな私でも最終的には合格することが出来ました。なぜなら、正しい勉強法を知り、実践し続けたからです。
この記事では、私の経験をもとに、電験三種の機械科目の勉強が思うように進まない時の対処方法をお教えします。機械科目が難しすぎて諦めようと思っているあなた、諦める前にこの記事を最後まで読んで下さい。
1.計算力不足の場合、電気計算の勉強をする

電験三種の勉強を進めていて、
- 機械の問題が解けない…
- 計算の仕方が分からない…
- 公式を覚えても、問題を解こうとすると手が止まる…
このように感じるなら、まず電気計算の勉強からやり直すべきです。
1-1.電気計算を勉強して基礎力をつける
「電気計算はすでにやったけれど、計算の方法が分からない」という場合も、もう一度復習することで計算力がつき、問題が解けるようになります。
計算力を鍛えることは、電験三種のすべての科目に役立ちます。教材を読んで理解出来る箇所が増え、スムーズに学習を進めることができるようになります。
電験三種の試験では、計算問題が多く出題されます。これらの問題を解くには、電気計算の基礎がしっかりできていることが前提です。計算がスムーズにできない場合、電気計算の基礎が不十分である可能性が高いです。
また、機械科目ではベクトル計算や複素数の計算も頻出します。そのため、電気計算の力をつけることは試験対策の基本であり、「計算が苦手」と感じる人ほど、電気計算をしっかり学ぶことが重要なのです。
電験三種の勉強で計算力が不足していると、問題が解けないばかりか、解説を読んでも理解出来ず苦労します。しかし、電気計算の基礎をしっかり固めることで、問題の理解度が大幅にアップし、スムーズに学習を進められるようになります。
- まずは電気計算を徹底的に学ぶ
- 計算力を鍛えれば、機械の教材を読んで理解出来るようになる
私が実際に使用したおすすめのテキストです。こちらを使用して勉強しましょう。無理なく基礎力をつけることが出来ます。
計算力をつけることにより、機械の勉強も理解しやすくなります。
1-2.どの科目から勉強すればいいの?
- 電気計算
- 理論
- 電力(または機械)
- 機械(または電力)
- 法規
この順番で勉強しましょう。電力と機械は、どちらからはじめても問題ありません。
機械と電力、どちらから勉強を始めるか迷ったとき、私は電力から手をつけることにしました。その理由は、電力の方が圧倒的にイメージしやすかったからです。参考書に載っている発電所の写真などを見ているうちに、「これは楽しそうだな」と感じ、スムーズに学習に入ることができました。
「計算が苦手…」と感じる人ほど、まずは 電気計算の基礎を徹底的に学ぶことが大切です。一歩ずつ、確実に計算力をつけていきましょう。
2.機械は図を書いて解く
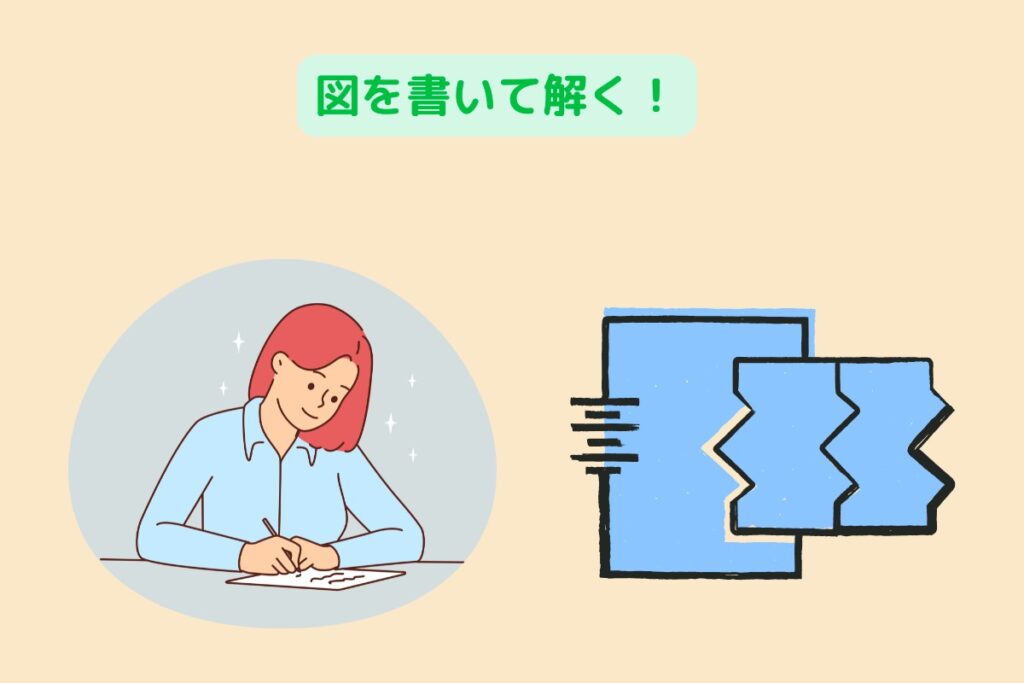
機械は図を書いて解きましょう。図を書けるようにならないと、機械の問題を解くことは難しいです。
例えば、直流電動機、直流発電機の問題を解く場合、問題を読んで等価回路図を書けるようになりましょう。また、電圧変動率の問題を解く時はベクトル図を書けるようにしましょう。
問題を読みながら図に落とし込んでいく練習をすることが、機械科目の問題を解けるようになる近道です。
機械科目は、最初は難しいです。しかし、機械科目は継続して勉強することにより、得意科目になる可能性があります。問題の姿かたちが変わったとしても、問われている内容の中身は実質同じだからです。
2⁻1.機械科目は図を書いて解くのが鉄則
電験三種の「機械」科目が苦手な人の多くが、
- 問題を読んでもイメージが湧かない…
- 解説を読んでも、何をやっているのか分からない…
- 計算はできても、途中でつまずいてしまう…
こうした悩みを抱えています。しかし、機械科目の問題は「図を書く習慣」をつけることで、圧倒的に解きやすくなります。
例えば、直流電動機・直流発電機の問題では、問題文を読んで回路図を自分で書けるようになることが重要です。また、電圧変動率の計算ではベクトル図を描くことで、計算がスムーズになります。
機械の問題は文章だけではイメージしにくいため、図を描くことで視覚的に理解する必要があります。「文章だけで解こう」とせず、図を書くことを習慣化することで、機械の問題が驚くほど解きやすくなります。
2-2.機械科目を攻略する具体的な方法
①「図を書く習慣」をつける
最初は手間に感じるかもしれませんが、続けることで図を書くスピードが速くなり、問題が解きやすくなるので、ぜひ習慣化してください。
②解説を読むときも、必ず図を描く
参考書の解説を読むときに図を「見て終わり」にしないことが重要です。「自分の手で描き直す」ことで、理解が深まるので、解説の図を 紙に描きながら読むようにしましょう。
また、問題集を解くときもいきなり計算に入らず、まず図を書いてから解くことで、情報整理がしやすくなります。
③おすすめの教材を活用する
私が実際に使用し機械の苦手意識を克服できた教材になります。
「みんなが欲しかった!機械の教科書&問題集」(TAC出版)
この教材は、
- 解説が分かりやすく、初学者でも理解しやすい
- 図解が豊富なので、視覚的に学習できる
- 問題演習を通じて、実践的な力が身につく
といった特徴があり、機械科目の苦手意識をなくすのに最適な教材です。
この教材を何度も繰り返し、図を書く習慣をつけることで、機械科目の理解が一気に深まります。
2⁻3.機械科目を得意科目にする方法
機械科目は、最初は難しく感じるかもしれません。しかし、図を書く習慣をつけることで、確実に理解しやすくなります。
- 問題を解くときは必ず図を描く
- 解説を読むときも、自分で図を書き直す
- ベクトル図や回路図を活用する
この3つを意識すれば、機械科目は確実に得意科目になります。
さらに、問題の形が変わっても、本質的に問われている内容は変わらないため、繰り返し学習することで応用力も身につきます。
2-4.基礎力がついたら過去問を攻略する

| おすすめ順 | 過去問題集 | おすすめ度 |
| 1 | 「電験三種 機械の20年間」 | ★★★★★ |
| 2 | 「みんなが欲しかった!電験三種の10年過去問題集」 | ★★★★ |
1.「電験三種 機械の20年間」(電気書院)を攻略する
私自身、こちらの過去問題集を10回以上繰り返しています。分野別にまとめられているので、弱点の克服に最適な教材となっています。
1⃣分野別にまとめられている過去問題集
この教材は分野別に過去問題をまとめて提供しています。特定の分野について集中的に学習を進めることができます。苦手分野の克服には最適な教材と言えるでしょう。
2⃣過去問の解説が詳細
過去問の解説が詳細に記載されており、問題の理解を深めるのに役立ちます。
2.「みんなが欲しかった! 電験三種の10年過去問題集」(TAC出版)を攻略する
本を切り離しで分冊できる便利な形式です。移動時間などを活用して学習することができます。
構成は
- 過去問題集
- 理論(解答解説編)
- 電力(解答解説編)
- 機械(解答解説編)
- 法規(解答解説編)
計5冊に分冊できます。
1⃣解答解説編
②③④⑤の解答解説編には、小さな文字ですが問題文は記載してあります。勉強したい分野1冊を持ち歩いて学習することが可能です。
2⃣過去問題集
過去問題集を利用し、時間内に問題を解き、自己採点を行い、自分の実力を評価しましょう。
答案用紙の記入シートも付属しており、本番さながらの状況で実際に問題を解くことができます。
※私は答案用紙の記入シートをコピーして使用しました。
3⃣分冊形式教材の有効活用
電験三種の学習において、この分冊形式教材は効率的で便利な選択肢と言えるでしょう。
- 移動時間やスキマ時間を活用して、効果的な学習を実現しましょう。
- 出題傾向を理解し、合格に向けて自信をつけていきましょう。
2026年度版は2024年12月24日より販売予定です。Amazon、楽天市場、Yahoo! ショッピングにて予約受付中です。
お急ぎの方は、2025年度版も販売しています。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
落ちたら、あとは上がるだけ!
諦めずに、コツコツと図を書きながら勉強を続けていきましょう。
3.最初は取り掛かり辛いが、やり続けると得意科目になりやすい
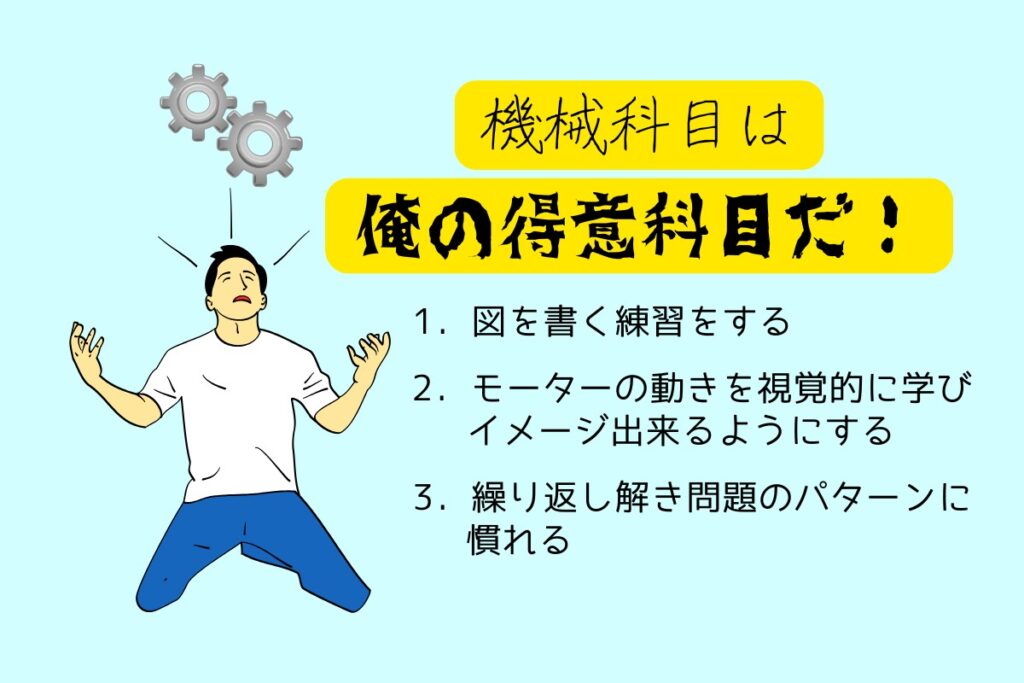
機械科目は、最初は取っ付きにくいです。私がはじめて機械の勉強をした時、何書いてあるのか分からないと言う印象でした。モーターの動きをイメージすることが難しいからです。しかし問題のパターンが決まっているため、慣れれば得意科目にすることも可能です。
機械科目は四機(直流機、変圧器、誘導機、同期機)+パワエレが試験の約7割を占めます。モーターはそのうちの四機の中の直流機、誘導機、同期機のことを言います。そのため、モーターの問題が解けないと、合格は難しくなります。
3-1.機械科目は、最初は取り掛かりづらい
機械科目は、最初に勉強を始めたとき「何を書いてあるのか分からない」という印象を受ける人が多いです。私自身、機械の勉強を始めたとき、まったく意味が分からず、困惑しました。
特に、モーターの動きがイメージしにくいことが大きな壁となります。文章で読んでも、モーターがどのように動作しているのかを想像しづらく、その結果、勉強が進みにくくなります。
しかし、機械の知識をつけることで、電験三種の合格がぐっと近づきます。では、どのようにすれば 取り掛かりやすくなるのかを解説します。
3⁻2.機械科目が取り掛かりづらい理由
機械科目が難しく感じる理由には、次のようなものがあります。
①モーターの動きをイメージすることが難しい
機械では、直流機(直流電動機、直流発電機)、同期機、誘導機と言った、さまざまな種類のモーターが登場します。
それぞれの動作原理を文章だけで理解しようとすると、頭の中でイメージすることが難しく、教材書いてある内容について、そもそも何が書いてあるのか分からなくなります。
②問題を解くためには図が必要になる
機械科目の問題は、図を書かないと解けないものが多いです。例えば、直流電動機や直流発電機の問題では等価回路図を描く必要がありますし、電圧変動率の問題ではベクトル図を活用することが求められます。
しかし、最初はどのように図を描けばいいのか分からないため、手が止まってしまい、問題を解くことができません。
3-3.取り掛かりやすくするための勉強法
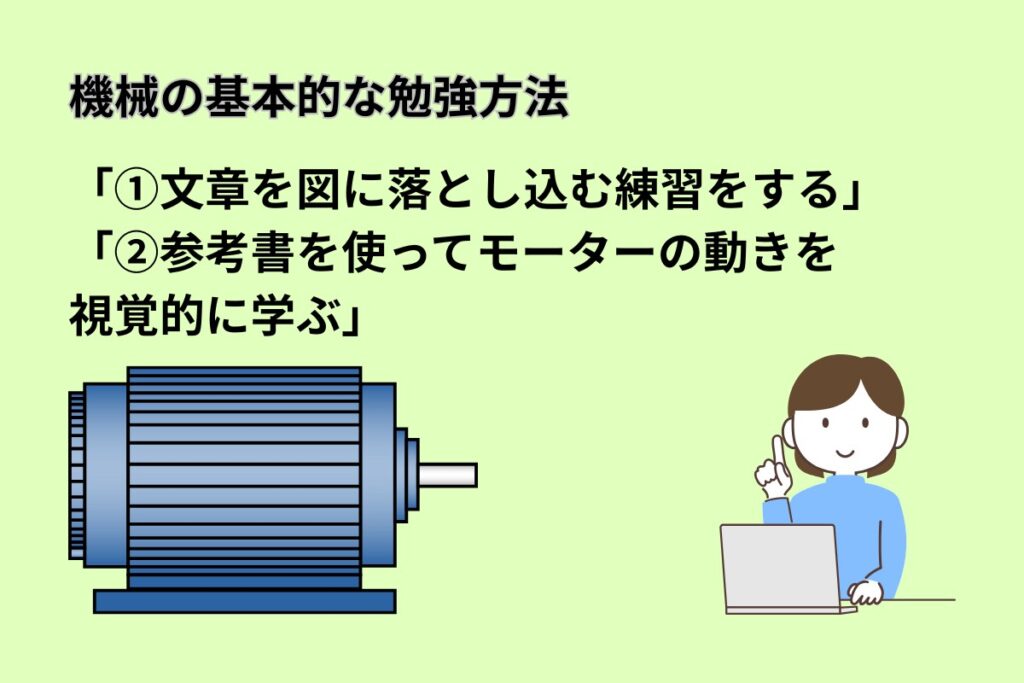
機械科目の勉強は、「①文章を図に落とし込む練習をする」「②参考書を使ってモーターの動きを視覚的に学ぶ」ことによりスムーズに進めることが出来ます。勉強を重ね、問題を解くのに慣れた時には得意科目となっているでしょう。
①「図を書く練習」をする
機械の問題は、文章だけを読んで解こうとすると理解が進みません。問題文を読んだら、すぐに図を描く習慣をつけましょう。
②参考書を使ってモーターの動きを視覚的に学ぶ
文章だけでは理解しづらい部分は、写真や図の多い参考書を活用すると、イメージがつかみやすくなります。
私が実際に使用した本の中で、「モーター技術のすべてが分かる本」は、写真が豊富で、モーターの動きを視覚的に理解するのに役立ちました。
ただし、「モーター技術のすべてが分かる本」は内容が難しいため、初心者にはおすすめしません。ある程度、機械科目の基礎を理解した後に読むと、より理解が深まるでしょう。
ある程度レベルアップしてきたら、こちらの本を読んでみましょう。モーターの知識が深まります。
私が実際に使用した「モーター技術のすべてが分かる本」になります。図解が豊富で詳しく解説してあります。機械の基礎知識が身についてから勉強しましょう。
③問題のパターンを知るために繰り返し解く
機械科目の問題は、一見すると違うように見えても、実は同じことを聞いていることが多いです。つまり、過去問や問題集を繰り返し解くことで、問題のパターンをつかめるようになるのです。
私自身、最初はまったく分からなかった機械科目も、繰り返し問題を解くことで、次第に「あ、このパターンはこう解くんだな」という感覚がつかめるようになりました。
3-4.最初は難しいが、継続すれば得意科目になる
最初は難しく感じる機械科目も、図を書く練習をしながら、継続して勉強すれば、必ず理解できるようになります。
特に、問題のパターンが決まっているため、慣れれば得意科目にすることも可能です。私自身、最初は苦手でしたが、継続して勉強することで機械科目が得点源になりました。
やり続ければ、結果はついてきます。合格するまで勉強をやり続けましょう。
「努力すれば報われる?そうじゃないだろ。報われるまで努力するんだ」(メッシ)
4.理論の勉強が未実施の場合、理論から勉強する

機械科目を勉強していると言うことは、理論科目は合格しているか、もしくは理論の勉強を一通り終えていることかと思います。
もし理論の勉強を終えてなかったら、まずは理論の勉強からはじめましょう。理論は、電験三種の他の科目の基礎です。勉強は基礎をやってから段々と積みあがっていくものです。
4-1.理論は電験三種の基礎
機械科目を勉強しているということは、すでに理論を学習済み、もしくは合格済みであることが前提になることが多いです。もし理論の勉強がまだ終わっていない場合は、まずは理論から学習しましょう。
なぜなら、理論は電験三種のすべての科目の土台となる基礎科目だからです。しっかりとした基礎があった方が機械科目を理解するのに有利になります。
「木は本から」と言われるように、どんなに立派な建物を建てようとしても、基盤がぐらついていたら崩れてしまいます。
そのため、理論を盤石にすることが、電験三種合格へ向けて非常に大切なことです。
4-2.理論を先に勉強するべき理由
理論を先に勉強すべき理由は、以下の3つが挙げられます。
①電験三種のすべての科目の基礎になる
電験三種には、理論、電力、機械、法規の4科目がありますが、どの科目も理論の知識が土台になっています。理論の理解が不十分だと、機械科目を解こうとしても、なぜその計算をするのかが分からなくなります。
②計算問題に強くなる
電験三種は計算問題の比率が高い試験です。
理論をしっかり学んでおくことで計算力がつきます。計算に対する抵抗感がなくなることで他の科目の問題もスムーズに解けるようになり、得点が伸びるようになります。
③理論を後回しにすると、結局勉強が進まなくなる
もし理論をやらずに機械から勉強しようとすると、途中で「あれ?これってどうやって計算するんだっけ?」と手が止まる場面が出てきます。結果として、結局理論に戻らなければならなくなり、勉強の進みが遅くなってしまうのです。
そのため、最初に理論を固めておくことが、結果的に効率の良い勉強方法になります。
4-3.理論の勉強を進める方法
①まずは「電気計算」に取り組む
理論の基礎となるのが電気計算です。電気計算の理解なしに理論を学んでも、途中でつまずいてしまいます。
②おすすめの参考書を使って勉強する
理論の勉強を進める際におすすめの参考書として、「みんなが欲しかった!電験三種 理論の教科書&問題集」(TAC出版)があります。
この本は、初心者にも分かりやすく、丁寧な解説と豊富な例題が掲載されています。実際に私も使いましたが、非常に理解しやすかったです。
③計算問題を繰り返し解く
理論は、単に知識を覚えるだけではなく、実際に手を動かして計算することが重要です。
4-4.理論をしっかり固めれば、合格に大きく近づく
理論は電験三種のすべての科目の基礎になるため、しっかりと勉強することで合格に大きく近づきます。
逆に、理論をおろそかにしてしまうと、他の科目の勉強が進まず、結果として遠回りになってしまいます。
「木は本から」:何事も基礎が大切である
しっかりとした基盤を作ることが、電験三種合格への確実な一歩です。もし理論の勉強が未完了なら、まずは理論の勉強からスタートしましょう。
5.勉強の順番を理解したら勉強をやり続ける
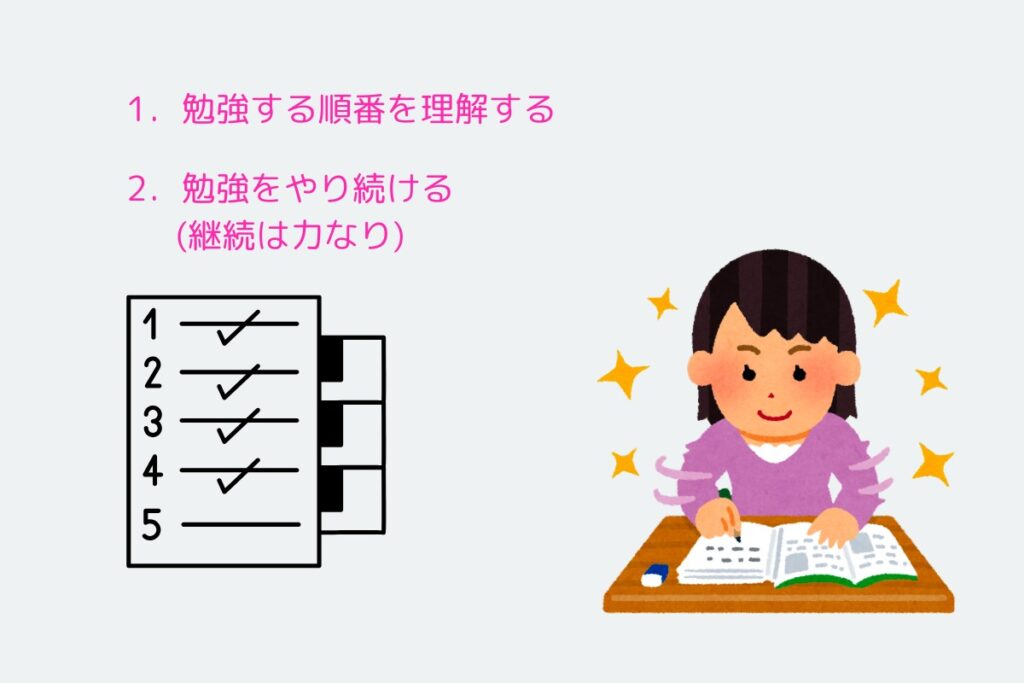
勉強する順番を理解したら、あとは勉強を継続するのみです。時間を作って毎日勉強をやり続けましょう。継続して勉強することが、合格するための近道です。
5-1.合格のために最も重要なのは「勉強を継続すること」
電験三種の合格には、適切な勉強の順番を理解することが重要です。
- 電気計算
- 理論
- 電力or機械
- 機械or電力
- 法規
このような学習順序で進めることで、基礎から応用へとスムーズに知識を積み上げられます。しかし、勉強の順番を知っているだけでは合格できません。
最も大切なのは、その順番で学習を継続し、習慣化することです。「時間がない」「モチベーションが続かない」と悩むこともありますが、勉強の継続が合格への最短ルートです。
5-2.勉強を継続することが重要な理由
①継続しないと知識が定着しない
電験三種は、覚える内容が多く、計算問題も複雑です。1日や2日勉強しただけでは、すぐに忘れてしまいます。
しかし、毎日少しずつでも継続して勉強すれば、知識が定着しやすくなります。「エビングハウスの忘却曲線」にも示されている通り、人間の脳は忘れやすいため、繰り返し学習することで記憶が強化されます。
- 1日休むと取り戻すのに3日かかる
- 短時間でもいいので毎日勉強を続ける
- 継続することで理解が深まり、試験本番で使える知識になる
②モチベーションの波に左右されず、習慣化することが大事
「今日は気分が乗らないから休もう」と思うこともありますが、モチベーションに頼った勉強では長続きしません。勉強を習慣化できれば、モチベーションに関係なく勉強できるようになります。
例えば、歯磨きをするのに「やる気」は必要ありませんよね。それと同じように、勉強も「やるのが当たり前」という状態にすることが理想です。
- モチベーションがなくても勉強できる仕組みを作る
- 「やる気があるからやる」ではなく、「やるのが当たり前」にする
- 1日のルーティンに勉強を組み込む
③「やらない日」を作ると、再開するのに労力が必要となる
一度勉強をサボると、「今日もいいか」とズルズルと勉強しなくなることがあります。1日休むと、それを取り戻すのに3日かかるとも言われています。
これを防ぐためにも、どんなに忙しくても、1分でもいいから勉強をする習慣をつけましょう。
5-3.忙しくても勉強時間を確保する工夫をする
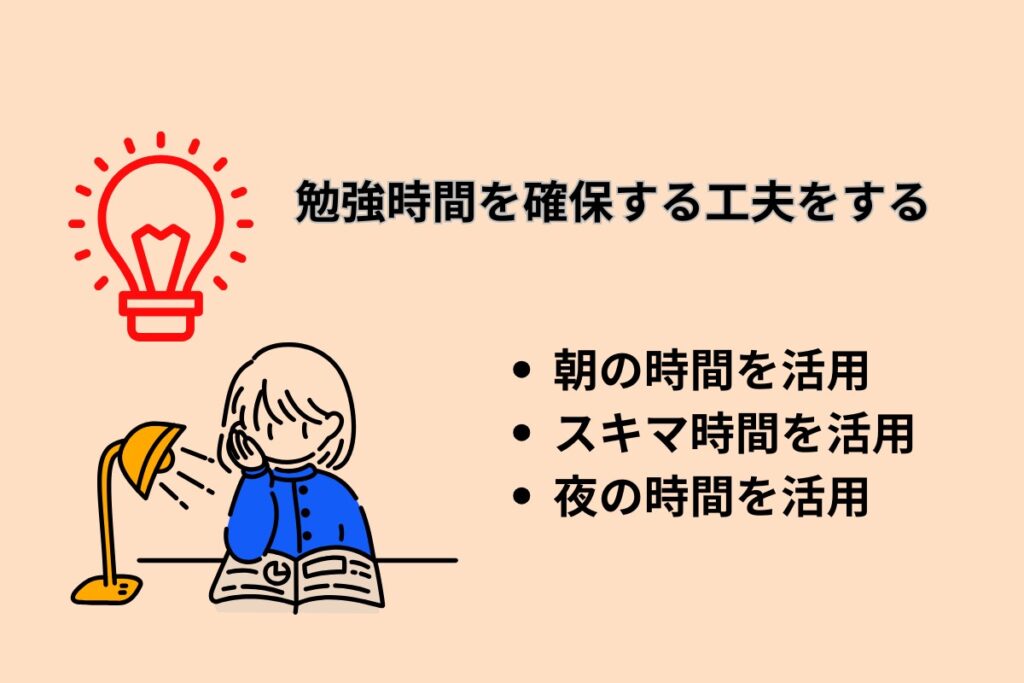
- 朝1時間早起きして勉強する
- 仕事の休憩時間に10分でも勉強する
- 仕事を終えて帰ったら、夜の時間を利用して勉強する
「仕事や家事で忙しくて勉強時間が取れない…」と悩む人も多いですが、工夫次第で毎日勉強を続けることは可能です。
①朝の時間を活用する
「朝1時間早起きして勉強する」
朝は疲れていないため、集中しやすい時間帯です。1日の予定に左右されずに勉強できるので、安定した学習時間を確保できます。
おすすめの朝勉強ルーティン
- 6:00 起床 → コーヒーを飲んで目を覚ます
- 6:10 ~ 6:40 計算問題を解く
- 6:40 ~ 7:00 テキストを読みながら知識をインプット
②隙間時間を活用する
「仕事の休憩時間に10分でも勉強する」
昼休みや移動時間など、短い時間でも有効に活用できます。
隙間時間にできる勉強
- スマホのアプリで過去問を解く
- 公式を暗記する
- 教科書をざっと読む
小さな積み重ねが、大きな学習量につながります。
③夜の時間を活用する
「仕事終わりに夜の時間を使って勉強する」
仕事が終わって家に帰ったら、30分でも勉強する時間を確保しましょう。
おすすめの夜勉強ルーティン
- 帰宅後すぐに勉強を開始する(ダラダラしない)
- 21:00~21:30 過去問を解く
- 21:30~22:00 間違えた問題を復習
夜は疲れがたまっているため、問題演習よりも復習に使うと効果的です。
例えば、朝1時間早起きして勉強する習慣をつけることで、仕事の前に集中した時間を確保できます。これにより、日中の仕事や家事で忙しい時間を避けて効率的に勉強できます。さらに、仕事の休憩時間に10分でも勉強することで、隙間時間を有効に活用できます。仕事終わりには、夜の時間を使って復習や問題演習を行うと、1日の勉強時間を最大限に活用できます。
5-4.勉強を継続できれば、合格は確実に近づく
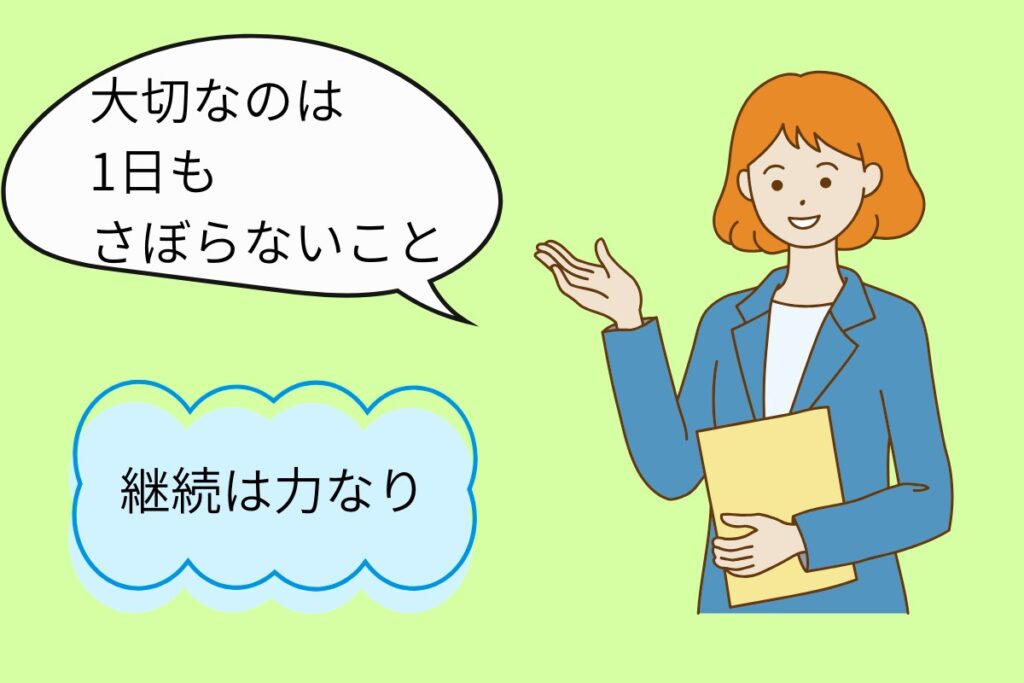
電験三種の合格は、毎日の積み重ねの結果です。「今日はいいや…」を繰り返すと、気づいた時には勉強が進んでいません。
大切なのは、1日も勉強をサボらないこと。
- 1分でもいいので毎日机に向かう
- 勉強を「やるのが当たり前」にする
- 忙しくても隙間時間を活用する
「継続は力なり」
勉強の継続が合格への最短距離です。勉強を続けることで、必ず合格に近づきます。あなたが今取り組んでいる勉強は、決して無駄にはなりません。
試験合格を目指す上で最も重要なのは、毎日コツコツと勉強を続けることです。最後まで諦めず、コツコツと努力を積み重ねましょう。
日々少しずつでも勉強時間を確保し、毎日続けることで、最終的に試験に合格する力が身につきます。1日のうちに1分も勉強しない日は、極力作らないようにしましょう。
1日休むと取り戻すのに3日かかると言います。毎日継続して勉強しましょう。
6.まとめ
機械科目の勉強は、最初は非常に難しく感じるものの、適切なアプローチを取れば必ず克服できます。計算力の強化、図を描く習慣、理論の復習、勉強の順番の理解、そして継続することが成功するためには重要です。
6⁻1.機械科目で挫折する理由
多くの受験生が機械科目で挫折する理由は、大きく分けて以下の5つに集約されます。
- 計算力の不足 → 電気計算の復習が不十分。
- イメージの難しさ → モーターや発電機の動作が理解しにくい。
- 基礎知識の欠如 → 理論の勉強が不足している。
- 勉強の進め方が分からない → 正しい順序で学習できていない。
- 継続ができない → 途中で諦めてしまう。
これらの課題を解決することで、機械科目の得点を伸ばすことができます。
私自身も、最初は機械科目を「暗号」にしか思えませんでした。しかし、以下の方法を実践することで、最終的に合格できました。
6⁻2.合格するために実践するべきこと
①電気計算を徹底的に復習
電気計算ができると、機械科目の計算問題のハードルが大幅に下がります。まずは「基本公式を丸暗記」ではなく、「なぜその公式が成り立つのか?」を理解することが重要です。
②図を書く習慣をつける
直流電動機や変圧器の問題は、文章だけを読んで理解しようとすると混乱します。実際に紙に等価回路図やベクトル図を描きながら考えることで、問題の本質を捉えやすくなります。
③理論の復習を優先する
もし理論の知識が不十分であれば、機械の問題を解くのは難しくなります。「理論→電力→機械→法規」の流れで勉強することで、理解がスムーズになります。
④毎日勉強を継続する工夫をする
「1日休むと3日分の遅れを取る」と言われるように、勉強の継続が重要です。スキマ時間を活用し、習慣化しましょう。
機械科目は、適切な勉強法を実践すれば必ず克服できます。特に以下の5つを意識してください。
- 計算力をつけるために電気計算を復習する
- 図を書くことで問題を視覚的に理解する
- 理論を復習し、基礎を固める
- 勉強の正しい順序を意識する
- 毎日少しずつでも勉強を継続する
あなたがもし「機械科目は無理かも」と思っているなら、諦めるのはまだ早いです。正しい方法で学べば、必ず理解できるようになります。
落ちたら、あとは上がるだけ。諦めずに、少しずつ前に進んでいきましょう。