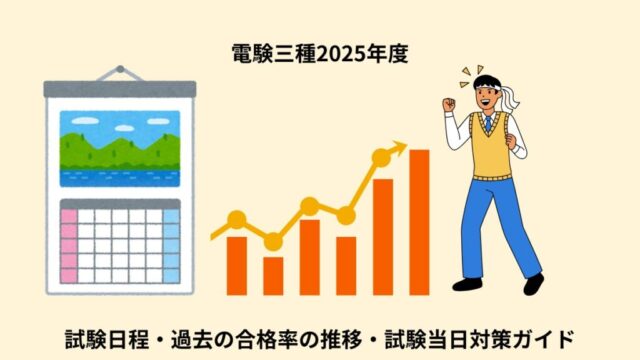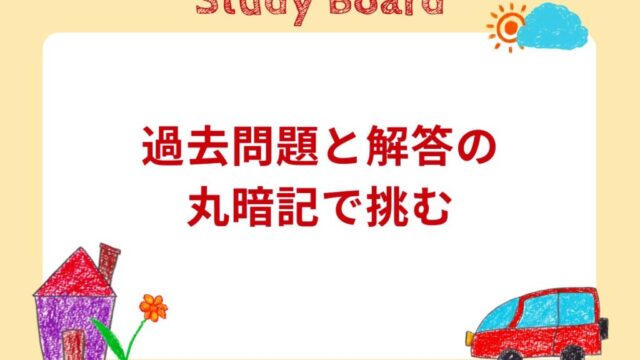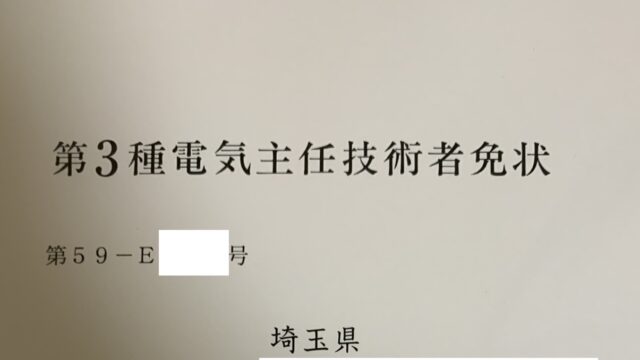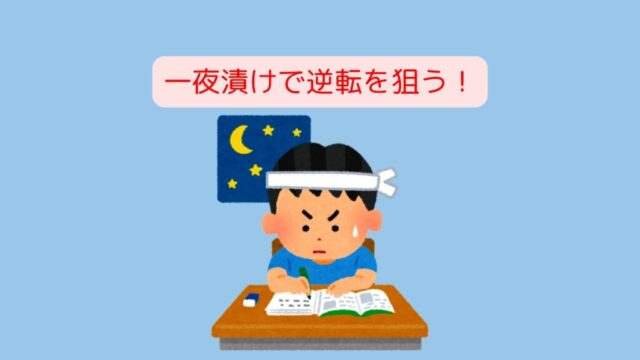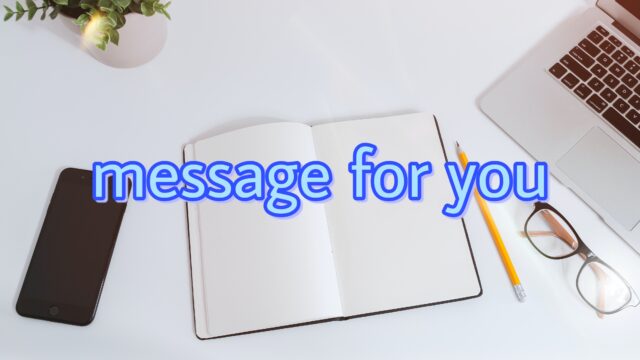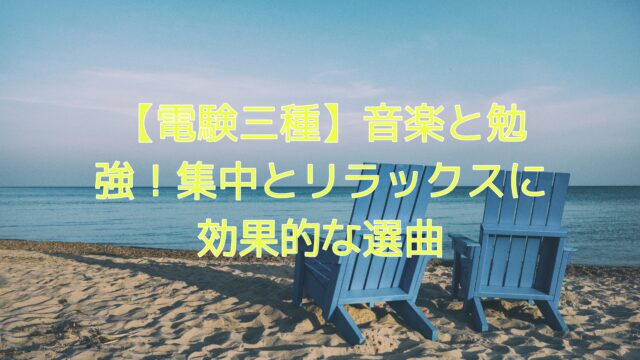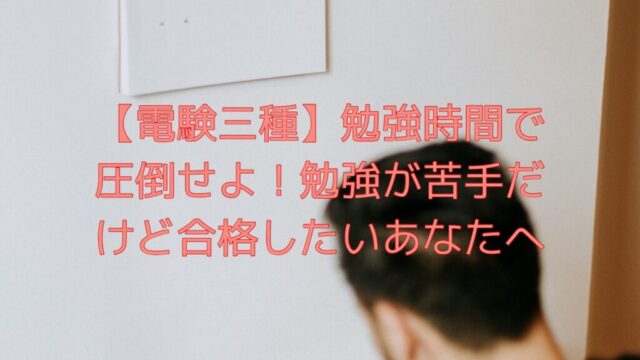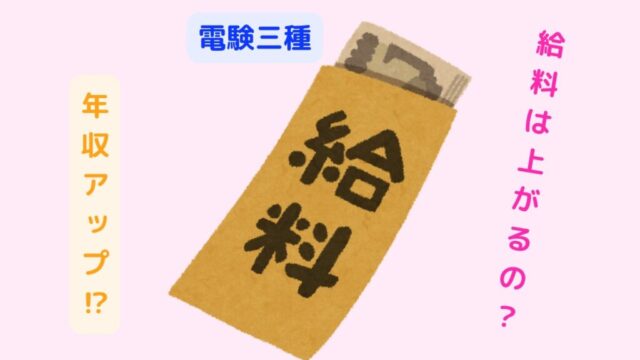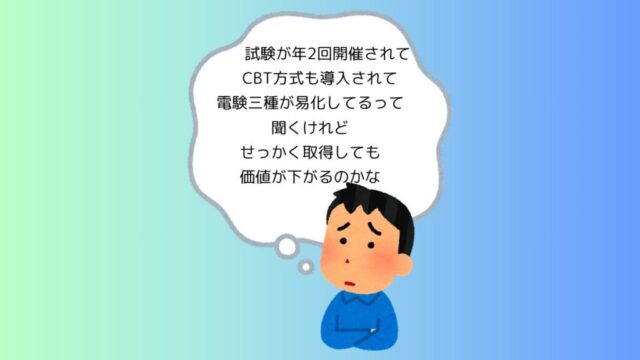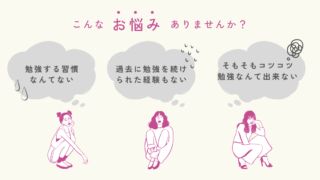電験三種は本当に難しい?ビルメン資格との難易度比較【ランキング付き】

- 電験三種の資格が欲しいけれど
- 目指したところで合格出来るのだろうか
- 電験三種ってどれくらい難しいの?
電験三種を受験しようと思ってはみたものの、他の資格と比較してどれくらいの難易度なのか気になる方は非常に多いです。これから電験三種試験の受験をお考えのあなたが、電験三種試験の難易度が他のビルメン資格と比べてどれくらい難しいのか知っておきたいと考えることは自然なことです。
そこで、電験三種(第三種電気主任技術者試験)の難易度について、エネルギー管理士、建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)、ビルメン4点セットとの比較を通じて、詳しく解説します。
「電験三種ってどれくらい難しいの?」と気になる方に向けて、各資格との比較を通じてその難易度を考察していきます。
この記事を読めば、電験三種の難易度が客観的に理解出来ます。この電験三種がどれほど難しいのか、他の資格と比較した内容を知りたい方は最後まで読んで下さい。
1.電験三種の難易度は非常に高い 難易度★★★★★
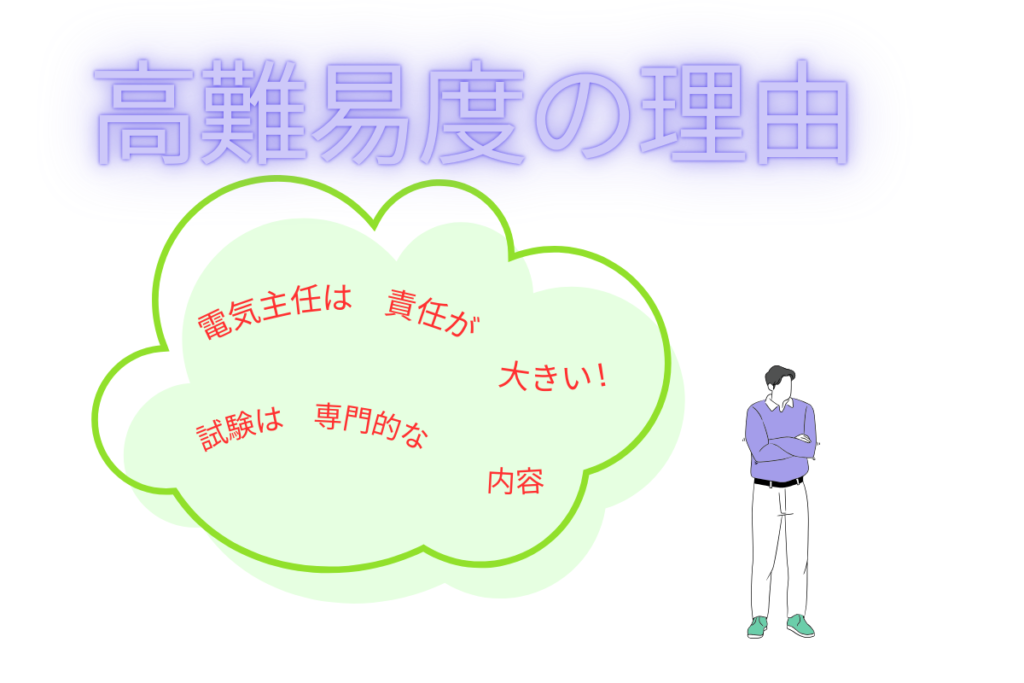
まず初めに、電験三種がなぜ「難関資格」として位置づけられているのかを理解しましょう。
事業用電気工作物の設置者には、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、電気主任技術者を選任しなくてはならないことが電気事業法で義務付けられています。
特に、電気主任技術者として施設の電気設備を管理し、事故やトラブルを未然に防ぐ役割を担うため、その責任は非常に大きいです。
電験三種は4つの科目、すなわち「理論」「電力」「機械」「法規」に分かれており、各科目がそれぞれ専門的な内容を含みます。
各科目の合格点は60点以上(100点満点中)で、科目合格制度が設けられており、電験三種の資格を取得するには、3年以内に4科目合格することが必要となります。
電気主任技術者は専門性が高く事故やトラブルを未然に防ぐ役割も担うため責任が大きいので、試験は専門的な内容となっており、電験三種試験は高難易度となってると考えられます。
2.電験三種が高難易度である具体的な要因
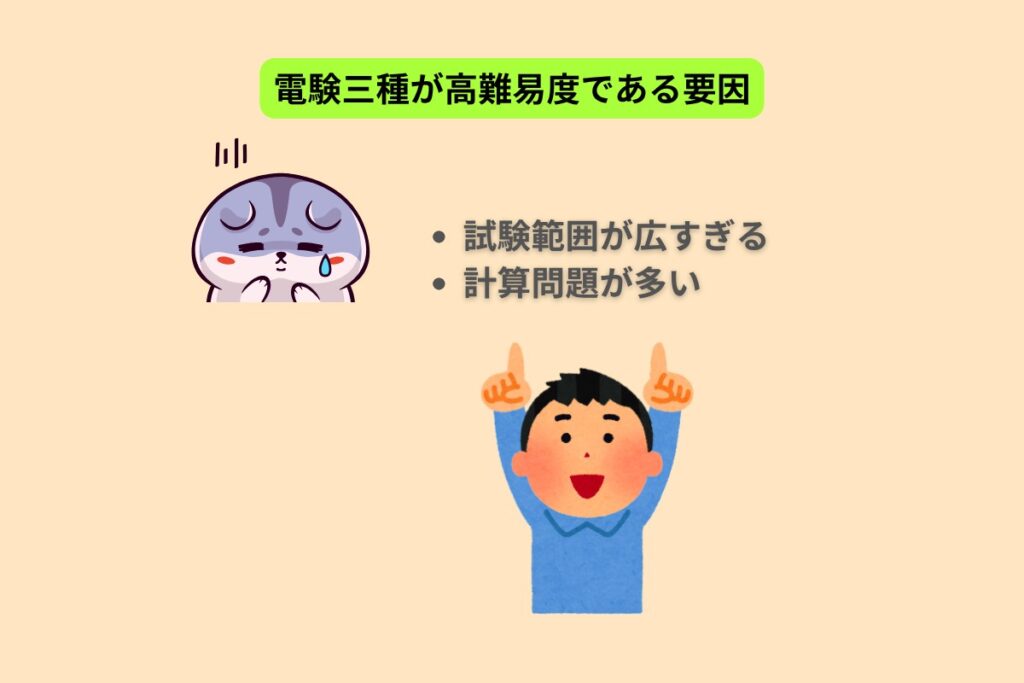
2-1.試験範囲の広さ
電験三種の試験範囲は非常に広範囲です。その上難易度も高いのでいくら勉強してもなかなか進まず、私自身、途中で挫折しかけたことが何度もありました。電験三種の試験範囲の広さには骨が折れます。
※具体的な試験内容につきましては、こちらの記事をお読みください。
2-2.計算問題の多さ
電験三種の試験には計算問題が多く出題されます。特に「理論」や「機械」の科目では、複雑な数式を使った問題が多く、数値のミスが失点につながります。
私がはじめて電験三種の勉強をしたときは、そもそもテキストに何が書いてあるのか分からないということが時々ありました。正しい参考書・問題集を使用し、コツコツ毎日勉強を続けることが電験三種試験攻略への近道となります。
理系の知識があまりない人にとっては、特に苦戦する部分となります。
3.電験三種の合格率は上昇
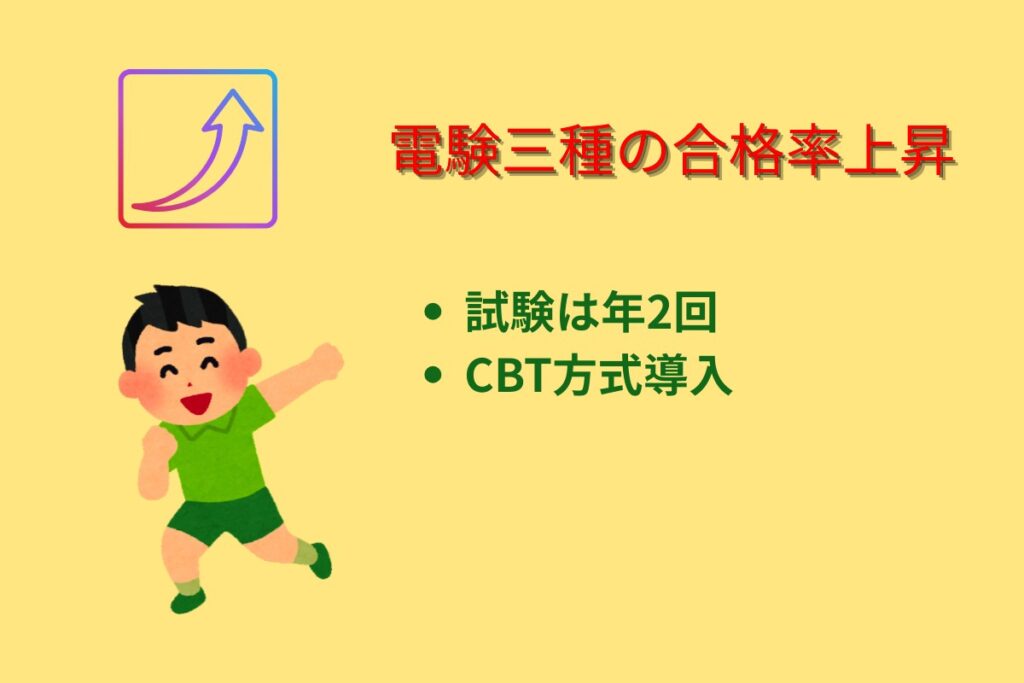
2021年度までは電験三種の合格率は例年10%前後と非常に低く、この低い合格率は、試験の難易度が高いことを如実に物語っていました。
2022年度から電験三種試験が年2回となり、2023年にはCBT方式も追加となり、合格率が上昇してきました。
近年では、以前に比べると合格しやすくなってきています。電験三種の資格がどうしても欲しいあなたにはチャンスとなっています。
とは言え、きっちり勉強しないと合格出来ません。
合格率の推移をお知りになりたい方はこちらの記事をお読みください。
4.電験三種と他の資格をランキング形式で難易度比較
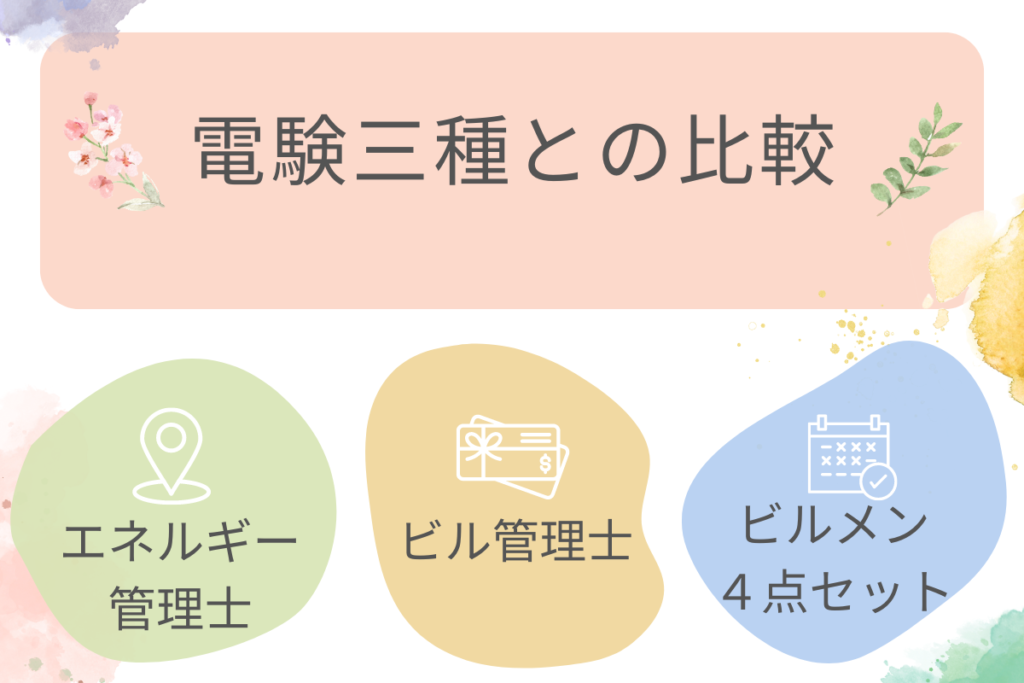
次に、電験三種の難易度を他の関連資格と比較してみましょう。
ここでは、エネルギー管理士、ビル管理士、そしてビルメン4点セット(第三種冷凍機械責任者、第二種電気工事士、危険物取扱者乙種四類、二級ボイラー技士)と比較していきます。
| ランキング | 資格 | 難易度 |
| 1 | 電験三種 | ★★★★★ |
| 2 | エネルギー管理士 | ★★★★ |
| 3 | 建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) | ★★★ |
| 4 | 第三種冷凍機械責任者 | ★★ |
| 4 | 第二種電気工事士 | ★★ |
| 6 | 危険物取扱者乙種第四類 | ★ |
| 6 | 二級ボイラー技士 | ★ |
※「第三種冷凍機械責任者」「第二種電気工事士」と「危険物取扱者乙種第四類」「二級ボイラー技士」は同じ順位(ランキング)としました。
ビルメン業界で“三種の神器”と呼ばれている電験三種・ビル管理士・エネルギー管理士の3つの上位資格について知りたい方は、こちらの記事を読んで下さい。
5.エネルギー管理士との比較 難易度★★★★

5‐1.エネルギー管理士
エネルギー管理士は、省エネ法によりエネルギー管理指定工場において、エネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから選任する必要があります。
※エネルギー管理士の選任者の人数は、年間の原油換算使用料により異なります。
エネルギー管理士は、エネルギーの効率的な使用を管理するための資格です。一定規模以上の工場などで、エネルギー消費を最適化する役割を担います。
※試験は「電気」または「熱」の分野に分かれています。
5⁻2.電験三種とエネルギー管理士との難易度の比較
エネルギー管理士(電気)は試験内容が過去問中心となっています。しっかり過去問対策をしている人にとっては合格しやすい資格とされています。
但し、エネルギー管理士(電気)の試験は、電験三種に合格出来る程度の基礎力がある人は過去問対策のみの試験対策でも十分ですが、数学に自信のない人はまず基礎力をつけることから勉強をはじめる必要があります。
※電気に関する基礎力の有無により、合格するまでの時間、難易度は変わってきます。
電験三種は、エネルギー管理士よりも理論的な理解が求められ、試験範囲も広いため、難易度が高いと言えるでしょう。
近年の傾向としては電験三種試験も過去問中心となっていますが、私自身、電験三種を取得する方が苦戦しましたので、エネルギー管理士の難易度は★★★★と、電験三種の方が難易度の高い評価としました。
※私はエネルギー管理士(電気)で受験しましたので、エネルギー管理士(電気)での評価としています。
※エネルギー管理士に受験資格はありませんが、免状申請を行うには実務経験1年以上が必要とされています。
6.建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)との比較 難易度★★★

6⁻1.建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)は、特定建築物で選任が義務付けられた国家資格です。
電気分野に特化した電験三種とは内容の異なる試験です。
※特定建築物とは、興行場・百貨店・店舗・事務所・学校等の用に供される建築物で、相当程度の規模を有するもの
6⁻2.電験三種と建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)との難易度の比較
ビル管理士の試験範囲は広範囲に及びますが、各分野の内容の深さは比較的浅いです。
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)の資格は、試験は暗記問題が中心であり、計算問題も少ないため、暗記が得意な人にとって難易度はそれほど高くありません。
※実際に建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)を受験する方は、計算問題の難易度は低めです。過去問題に出題されている計算問題については、全て解けるようにしましょう。
ビルメンテナンスの資格では上位資格の位置づけですが、私は3カ月の勉強で一発合格できましたので、難易度は★★★としました。
※建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)は、申し込みの時点において実務経験2年必要です。
7.ビルメン4点セットとの比較 難易度★ or ★★

ビルメン4点セット
- 「第三種冷凍機械責任者」 難易度 ★★
- 「第二種電気工事士」 難易度 ★★
- 「危険物取扱者乙種第四類」 難易度 ★
- 「二級ボイラー技士」 難易度 ★
※私は最初から第二種冷凍機械責任者を受けたため、第三種冷凍機械責任者は取得していません。
7⁻1.ビルメン4点セット
ビルメン4点セットは、ビル管理業務に携わる上で必要な4つの資格、すなわち「第二種電気工事士」「危険物取扱者乙種第四類」「二級ボイラー技士」「第三種冷凍機械責任者」を指します。
「第二種電気工事士」「危険物取扱者乙種第四類」「二級ボイラー技士」「第三種冷凍機械責任者」の資格は、ビルの設備管理に必要な基本的な知識と技能を証明するものです。
7⁻2.電験三種とビルメン4点セットとの難易度の比較
ビルメン4点セットは各資格がそれぞれ特定の分野に特化しており、試験範囲はそれほど広くありません。ビルメン4点セットの資格は特定の設備管理に必要な基礎知識が問われるため、学習内容は比較的分かりやすいです。
試験の合格率も高めであり、短期間での資格取得が可能です。
一方、電験三種は広範囲かつ深い専門知識を要求され、計算問題も多いため、ビルメン4点セットの試験と比べて遥かに難易度が高いです。特に、理論に関する理解が合格の鍵となるため、理工系出身者でも苦戦することが少なくありません。
8.まとめ
電験三種は、エネルギー管理士やビル管理士、ビルメン4点セットと比較しても難易度が高い資格です。
電験三種試験の難易度の高さは、試験範囲の広さ、計算問題の難しさなどが要因となっています。
電験三種に合格するためには、長期間にわたる学習と強い意志が必要です。しかし、電験三種を取得することで得られるキャリアの可能性や収入の向上を考えると、電験三種への挑戦は十分に価値があります。
電気技術者としてのスキルを証明するこの資格を手にすることで、あなたの未来が広がり、電気業界でのさらなる成長が期待できるでしょう。
電験三種に挑戦し、その難関を乗り越えた先には、達成感とともに新たなキャリアの扉が開かれます。電験三種は確かに難しい資格ですが、その難しさを乗り越えることで、あなた自身の技術力と可能性を広げることができます。
毎日コツコツ勉強し、電験三種試験の合格を勝ち取りましょう。
電験三種試験の教材選びについてお悩みの方はこちらの記事を読んで下さい。
電験三種の通信講座と独学のメリット・デメリットについて知りたい方はこちらの記事を読んで下さい。