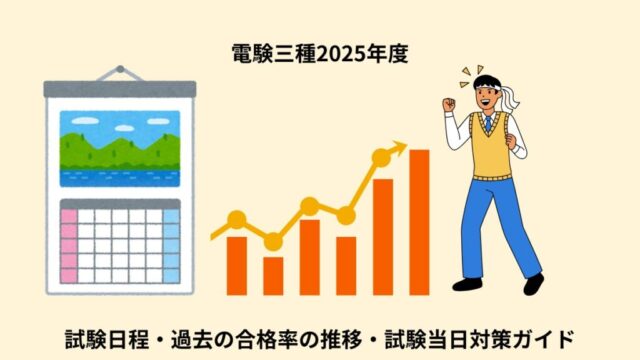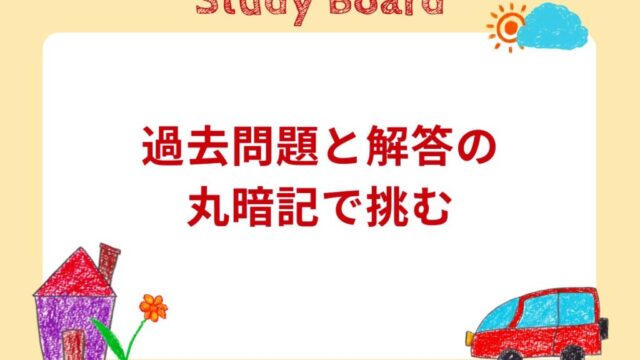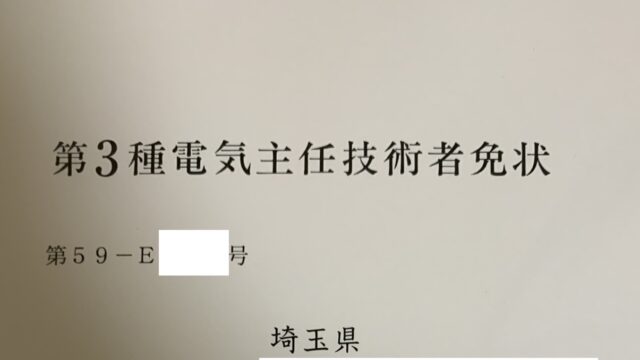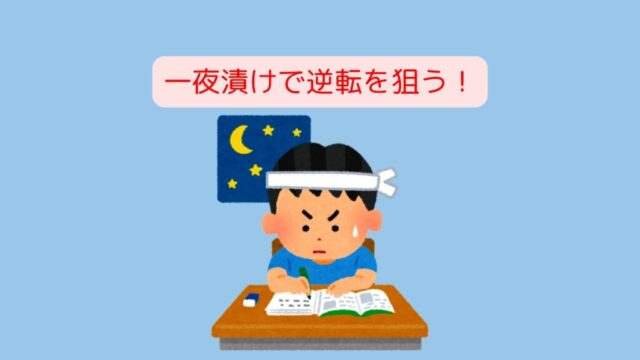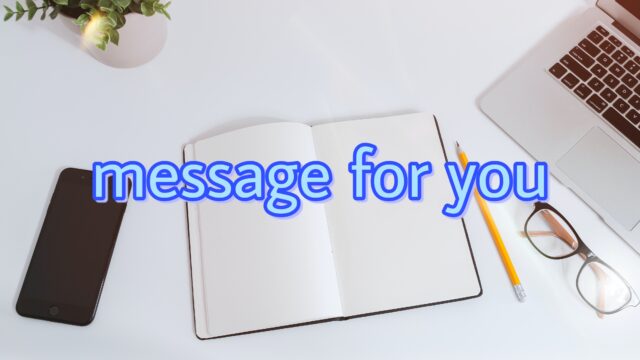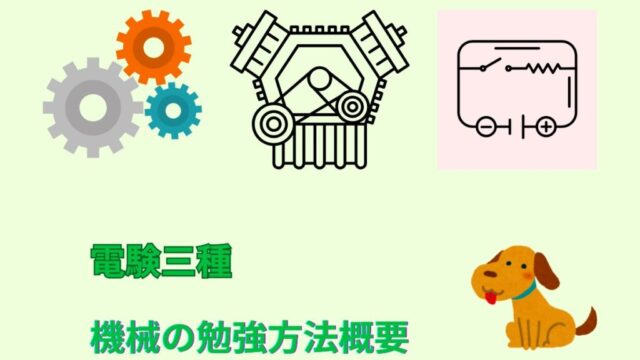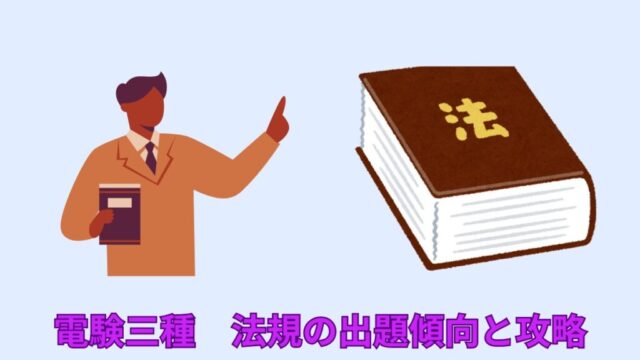【電験三種】初心者用 各科目のA問題、B問題の違いと具体的な対策方法!
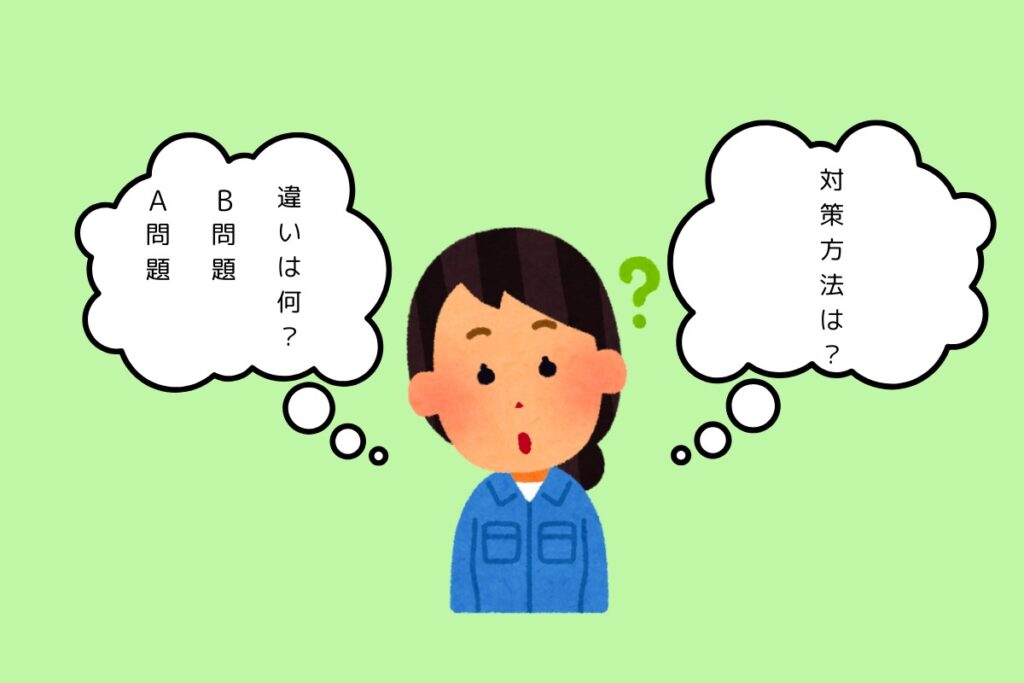
- 電験三種の勉強をはじめたけど
- 各科目にA問題、B問題ってあるんだけど
- 何がどう違うのか教えて欲しい
A問題、B問題ってあるけれど、具体的にどう違うのだろう。自分で調べるのは時間がかかるし、手っ取り早く内容が知りたいと思うことは、電験三種の合格を目指すにあたり良くあることです。
私は電験三種の合格を目指す者として、初心者の立場からスタートしました。3年8ヶ月と4回の受験を経て、合格を勝ち取りました。しかしその3年8ヶ月の間、勉強方法について悩み様々な方法を実践し、たくさんの遠回りをしてきました。
私も電験三種の勉強をはじめたころ、「A問題とB問題?なんだ。このおしゃれな名前の問題たちは…」と混乱したものです。A問題とB問題の違いが分からないまま勉強し、受験していました。しかし対策不足ですと合格することはなかなか難しいです。「猪突猛進」では対応できない場合もあります。
でも安心してください。A問題とB問題の違いを知ることで、勉強の効率がぐんとアップし、合格出来る確率が上がります。
この記事では、初心者向けにA問題、B問題とはどういうものなのか詳しく解説します。試験問題の特性を理解し内容を詳しく知ることにより、合格へ大いに近づきます。A問題、B問題について詳しく知りたい方はこの記事を最後まで読んでください。
1.A問題とB問題の大きな違いは難易度

電験三種の試験では、A問題とB問題の違いは難易度にあります。
- A問題は基本問題
- B問題は難易度の高い問題
まずは、A問題を解けるようにしましょう。最初のうちは、難しく感じたらB問題は飛ばしても問題ありません。
B問題は、解説を読んで理解出来るのであれば解けない問題があっても構いません。難易度が高いと言っても、基本の組み合わせで成り立っています。B問題も、そのうち解説を見なくても自力で解けるようになりますので、何度も繰り返し解いていきましょう。
A問題は基本問題です。
- 基本を押さえる:公式や概念をしっかり理解することで、A問題の得点率を上げることができます。
- 解説を読む:問題集の解説を活用して、なぜその解法になるのかを理解しましょう。
B問題は難易度の高い問題です。
- まずは(a)の得点を狙う:理論・電力・機械のB問題は大問ごとに(a)と(b)がありますが、(a)が解けるだけでも5点得点できます(法規では、B問題の配点は問11,問12(a)6点(b)7点、問13(a)7点(b)7点となっています)。
- 繰り返し練習:過去問を繰り返し解くことで、応用力が養われます。
2.出題形式が異なる
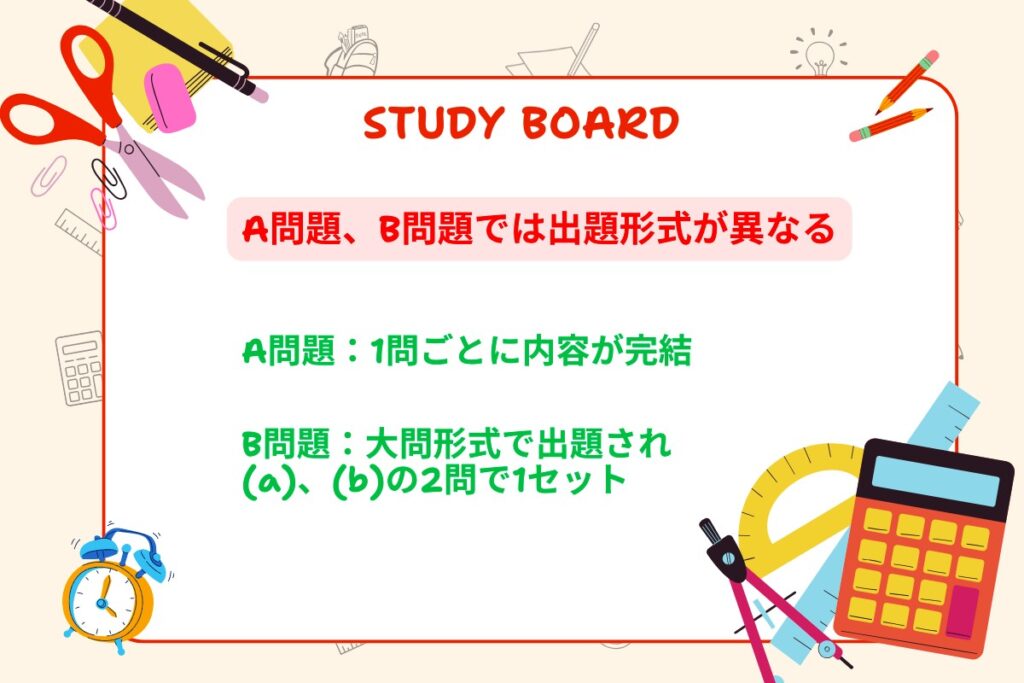
A問題、B問題では出題形式が異なります。
- A問題:問題1問ごとに内容が完結しています。
- B問題:大問があり、大問に対して(a)、(b)各2問、問題があります。(a)が解けないと(b)も解けない問題が多数です。
理論・電力・機械は各5点であり、A問題も、B問題も同じ配点です。B問題は、(a)配点5点、(b)配点5点となっています。
法規はA問題が各6点で10問(A問題:60点満点)、B問題は問11,問12は(a)6点(b)7点、問13は(a)7点(b)7点(B問題:40点満点)となっています。
試験形式の知識の有無は、合否に直結します。試験形式は、各科目とも、しっかり頭に叩き込んで置きましょう。
- 1問ごとに内容が完結しており、短時間で解答できる問題が多いです。
- 理論・電力・機械は各問題の配点が5点ずつで、科目全体で70点満点となります。
- 法規は各問題の配点が6点ずつで、科目全体で60点満点となります。
- 大問形式で出題され、(a)、(b)の2問で1セットになっています。
- (a)が解けないと(b)も解けない場合が多い構造です。
- 配点は(a)、(b)それぞれ5点ずつで、科目全体で30点満点です。
試験形式を理解することで、問題を解く順番や時間配分を計画的に進められるようになります。
3.B問題の対策
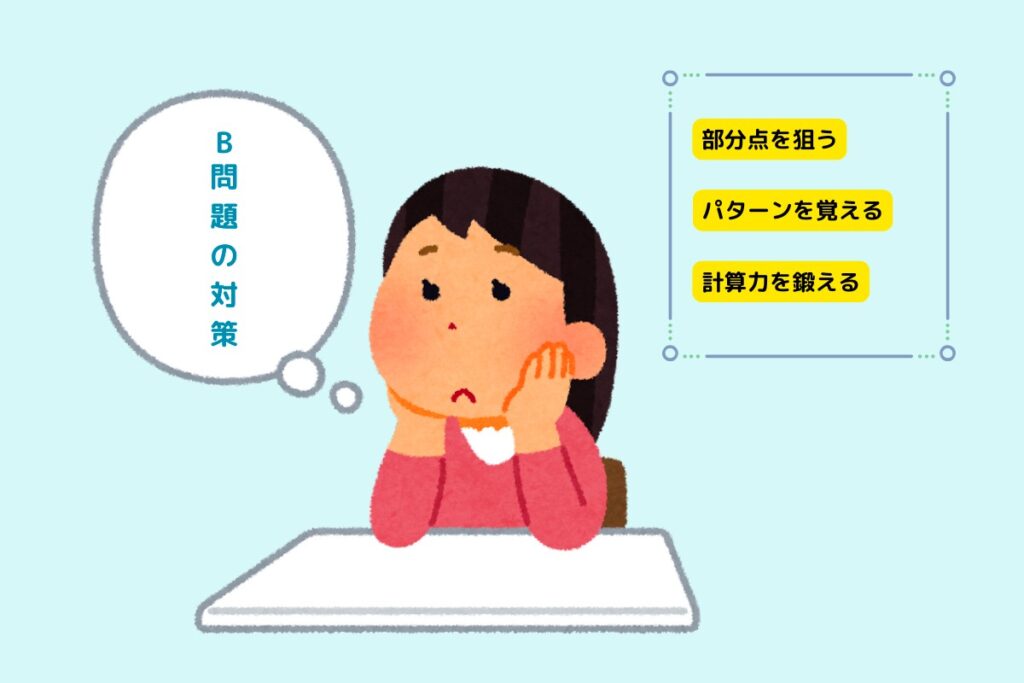
出題形式が違うので、B問題を解くことにも慣れておく必要があります。
一見したところ難しく感じる問題でも、よく読むと(a)の問題だけでも解ける可能性があります。(b)が難しいと感じたら、(a)だけ解けるようにしておきましょう。勉強しているうちに、(b)も理解出来るようになります。
合格点のボーダーラインにいる場合、1問正解出来るか出来ないかで合否が決まります。あきらめずに最後まで食らいついていきましょう。
B問題は応用力を試されるため、対策が必要です。
- 部分点を狙う:難しい問題に挑む際、(b)が難解であっても(a)だけでも解けるようにしましょう。
- パターンを覚える:過去問を通じて、頻出の計算パターンや解法を暗記します。
- 計算力を鍛える:特にB問題では複雑な計算が求められることが多いため、電卓の使い方に慣れることも大切です。(実際に私は、計算式は正解していたが電卓の打ち間違いにより、B問題で失点した経験があります。)
過去問は1回解くだけでなく、間違えた問題を復習し、何度も解き直すことで理解を深めましょう。
4.【科目別】A問題・B問題の配点と選択・必修の違いを一覧表で確認!
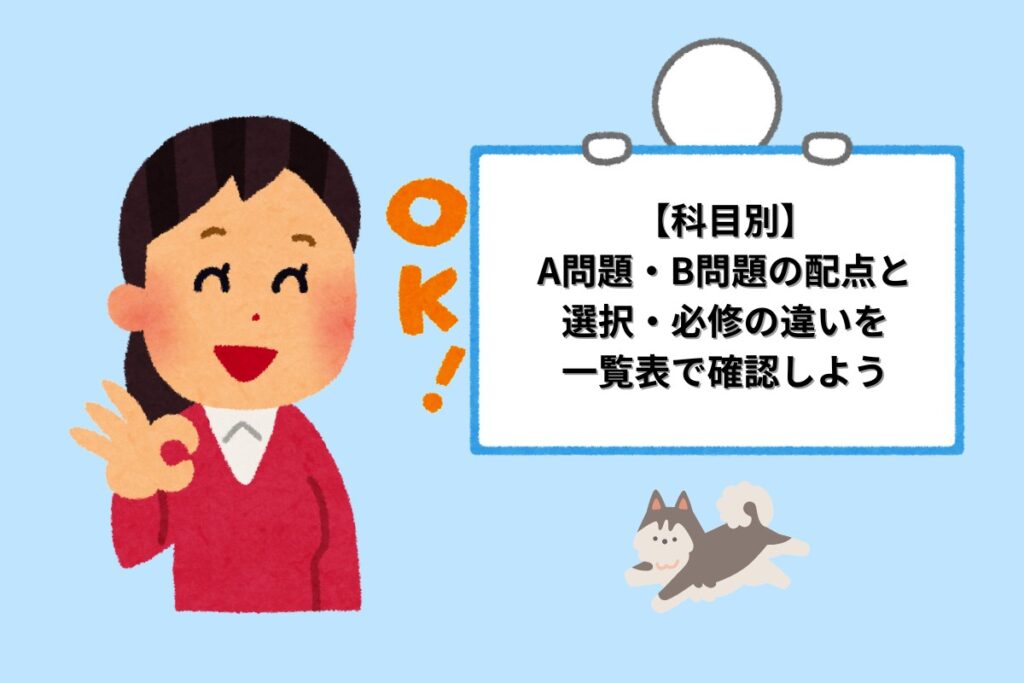
電験三種に合格するためには、各科目のA問題とB問題の配点や出題形式(必修・選択の違い)を理解し、効率的に学習することが重要です。
各科目の配点や出題形式を正しく理解していないと、試験本番で効率的に得点を稼げない可能性があります。特に、B問題の必修・選択問題の扱いを誤ると、不必要に時間を浪費する原因になります。
この表は、各科目のA問題・B問題の配点と、B問題が必修なのか選択可能なのかを整理したものです。
| 科目名 | A問題 | B問題 | B問題選択・必修の区分 |
| 理論 | 各5点×14問(70点満点) | (a)(b)各5点(30点満点) | 問17または問18を選択 |
| 電力 | 各5点×14問(70点満点) | (a)(b)各5点(30点満点) | 必修 |
| 機械 | 各5点×14問(70点満点) | (a)(b)各5点(30点満点) | 問17または問18を選択 |
| 法規 | 各6点×10問(60点満点) | 問11,問12(a)6点(b)7点 問13(a)7点(b)7点(40点満点) | 必修 |
試験のA問題・B問題の配点や出題形式を理解することは、合格に直結する重要な過程です。この表を活用し、効率的に学習を進め、試験本番に役立ててください。
5.理論 A問題・B問題の対策
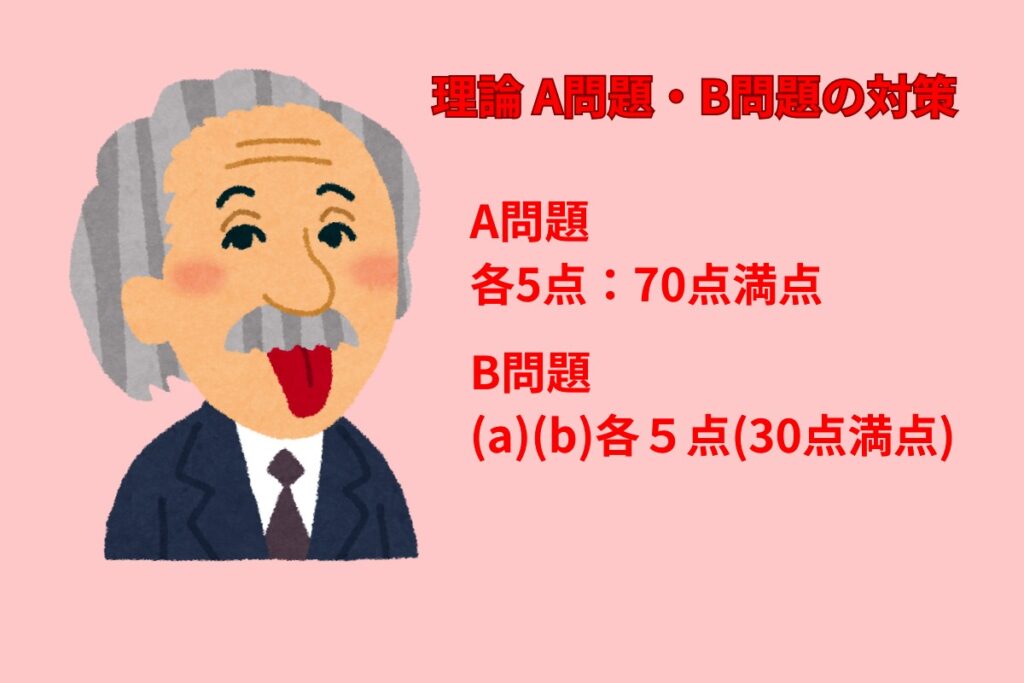
理論は、問1から問14までがA問題です。各5点(70点満点)です。
B問題は問15(a),(b)、問16(a),(b)が必修問題で、問17(a),(b)と問18(a),(b)が選択問題です。各5点(30点満点)です。
選択問題は、パッと見て解きやすい方を選択します。私の場合、片方が明らかに苦手な問題であり、どちらを解くのかはどの年度も大抵一瞬で決まります。
- 両方解けそうな場合は、解答までの道筋が簡単な方を選びましょう。
- 両方難しいと感じた場合、(a)だけでも確実に解ける問題を選びましょう。
結果的に合格点を取れていれば良いのですが、両方落とすと合否に影響を及ぼす可能性があります。A問題を満点取れれば70点ですので、それだけでも合格することは出来ます。しかしケアレスミスやマークミスをする可能性もあります。また、A問題は基本問題と言いつつ、いくつか難易度の高い問題が出題される場合もあります。
点を取れる問題はきちっと取りにいきましょう。
- 問1〜問14で構成され、70点満点です。
- 基礎的な問題が多くなっています。
- 必修2題、選択1題(2題中1題選択):合計30点満点。
- 選択問題では、得意な分野を選ぶことが得策です。
- 頻出分野を優先的に学習します。
- 計算問題に強くなることで、B問題の得点率を上げられます。
「理論」について以下の内容を知りたい方は、私のこちらの記事をクリックし、読んで下さい。
6.電力 A問題・B問題の対策
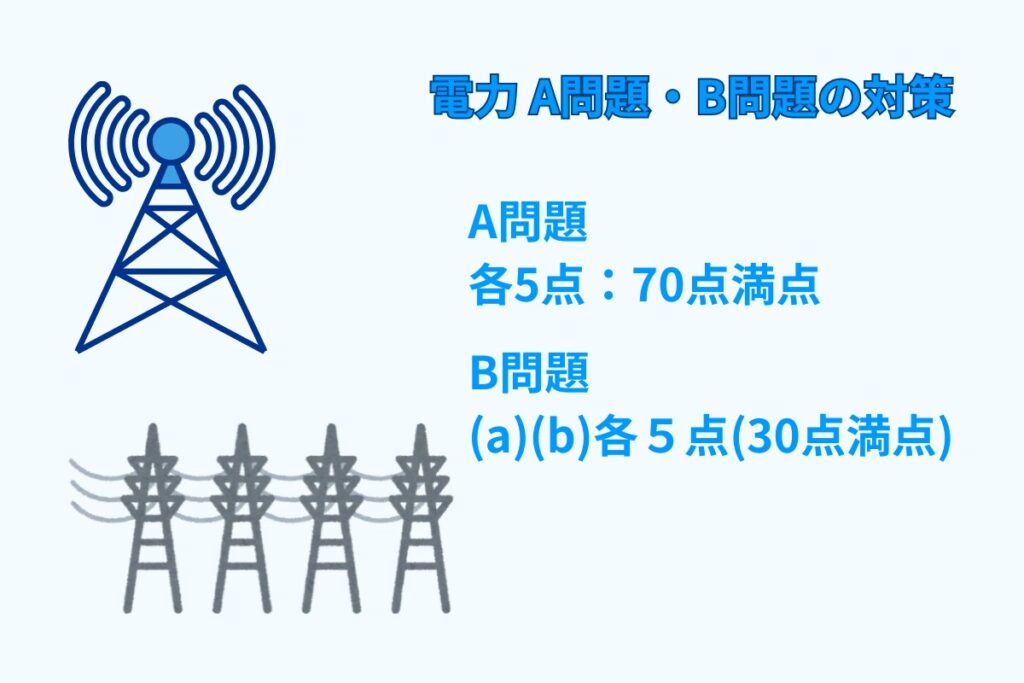
電力は、問1から問14までがA問題です。各5点(70点満点)です。
B問題は問15(a),(b)、問16(a),(b) 、問17(a),(b)全て必修問題です。各5点(30点満点)です。
電験三種は、A問題は基本問題と言いつつ、難易度の高い問題も出題されます。A問題があまり出来なかったと感じても、B問題でしっかり得点出来れば合格することが可能です。
合計点で合格基準点の60点以上取ればいいので、試験中は最後まで諦めずに問題を解きましょう。試験時間中の途中退出はおすすめしません。例え早く問題が解き終わったと感じたとしても、「検算」や「マークミスがないかの再確認」を時間いっぱいまで行いましょう。
- 問1〜問14で構成され、70点満点です。
- 知識を問う基本問題が多いです。
- 全て必修問題で合計30点満点。
- 比較的難易度の高い計算問題が出題されます。
- 頻出分野を優先的に学習します。
- 電力は、暗記と計算問題の割合がおおよそ5割ずつです。計算問題はある程度パターンが決まっているので、公式は勿論のこと解き方をしっかりと覚えましょう。
「電力」について以下の内容を知りたい方は、私のこちらの記事をクリックし、読んで下さい。
7.機械 A問題・B問題の対策
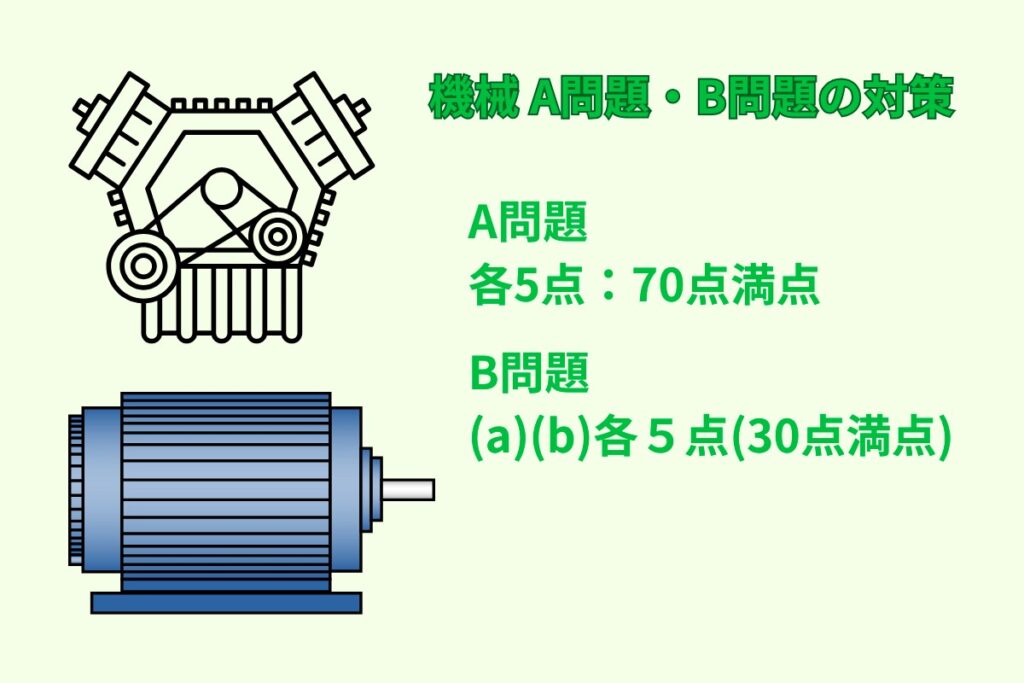
機械は、問1から問14までがA問題です。各5点(70点満点)です。
B問題は問15(a),(b)、問16(a),(b)が必修問題で、問17(a),(b)と問18(a),(b)が選択問題です。各5点(30点満点)です。
機械は考え方を一度マスターすれば、得意科目にすることが可能です。繰り返し学習し機械の問題に慣れましょう。
私自身、機械科目は最初取り掛かり辛かったですが、繰り返し学習することで苦手意識はなくなりました。
理論と同様の配分となっています。
- 問1〜問14で構成され、70点満点です。
- 基礎知識を問われます。
- 必修2題、選択1題(2題中1題選択):合計30点満点。
- 選択問題では、得意な分野を選ぶことが得策です。
- 応用力が必要な問題が出題されます。
- 機械科目は解法パターンがほぼ同じですので、何度も繰り返し学習すれば得意科目にすることも可能です。
- 図に書いて計算する手法を身に付け、機械を得意科目にしましょう。
「機械」について以下の内容を知りたい方は、私のこちらの記事をクリックし、読んで下さい。
8.法規 A問題・B問題の対策

法規に関しては、理論・電力・機械とは配点が違います。
法規はA問題が各6点で10問(A問題:60点満点)、B問題は問11、問12が(a)6点(b)7点、問13は(a)7点(b)7点(B問題:40点満点)となっています。全て必修問題です。
基本的に、A問題が暗記問題、B問題が計算問題です。まれに、試験年度により違うパターンもあります。
A問題:暗記問題ですので、過去問を中心に学習し暗記しましょう。過去問題で出題されている内容については全て暗記してください。
B問題:計算問題が中心であり、パターンが決まっています。解法パターンを全て暗記し、満点を狙いましょう。
計算問題を満点取れば40点となります。B問題で半分程度の得点が出来れば30点となり、合計で70点で合格となります。ただし、暗記も怠らずに勉強してください。
私自身、B問題満点狙いで、A問題は半分程度取れれば合格出来るであろうと考え、その作戦で試験を受験したことがありました。その結果、B問題で1問落とし33点、A問題で3問しか得点できずに18点。合計51点で不合格になった年度がありました。
B問題40点満点狙いはもちろん良い作戦ですが、暗記をおろそかにすると不合格になります。当時の私が悪い見本です。最終的には総合力で合格することを心がけて勉強してください。
- 問1〜問10で構成され、各6点(60点満点)。
- 暗記を中心とした基礎的な知識問題が多いです。
- 問11〜問13で構成され、合計40点満点。
- 計算問題が出題されます(まれに暗記問題の出題あり)。
電気事業法や電気設備の技術基準・解釈などを暗記するとともに、計算問題のパターンを暗記します。
以下の戦略を実践してください。
- A問題は過去問題を中心に暗記する。
- B問題の計算問題で満点を目指す。
「法規」について以下の内容を知りたい方は、私のこちらの記事をクリックし、読んで下さい。
9.まとめ
電験三種に合格するためには、科目ごとにA問題とB問題の特徴を理解し、各科目の得点戦略を立てることが大切です。この記事で解説した内容を参考に、効果的な学習計画を作成してください。過去問の活用や復習を徹底することで、合格基準点を超える力を養いましょう。
A問題とB問題の違いを理解し、戦略的に勉強しよう!
- 基本的な知識を問う問題で構成。
- なるべく点数を稼ぐ。
- 応用力や深い理解が求められるので、過去問題を繰り返し解くことで応用力を鍛える。
- 部分点の得点を狙うことや、得意な選択問題を選ぶなどして得点を伸ばす。
- 法規に関しては、過去問のB問題を全て理解・暗記し満点を狙う。
- 時間配分を徹底し、試験時間を最大限活用する。
- 過去問を繰り返し解き、試験形式に慣れる。
電験三種は決して簡単ではありませんが、正しい対策と継続的な勉強をすることで合格は可能です。この記事でA問題、B問題の違いを理解し、合格目指して学習を進めてください。
電験三種のおすすめのテキストについて詳しく知りたい方は、こちらの記事をクリックし、読んで下さい。