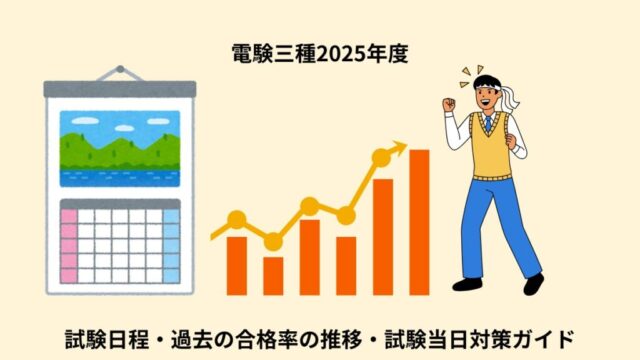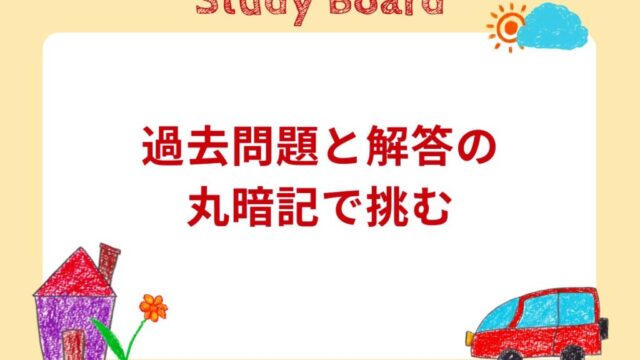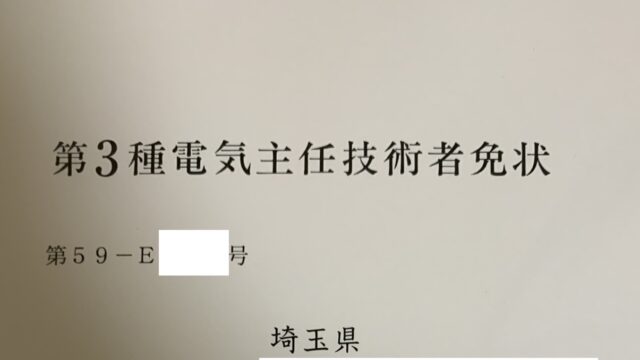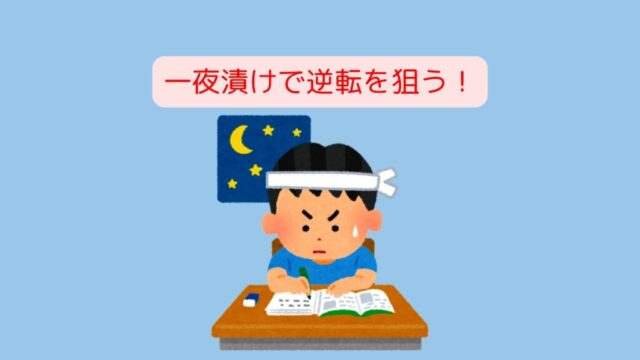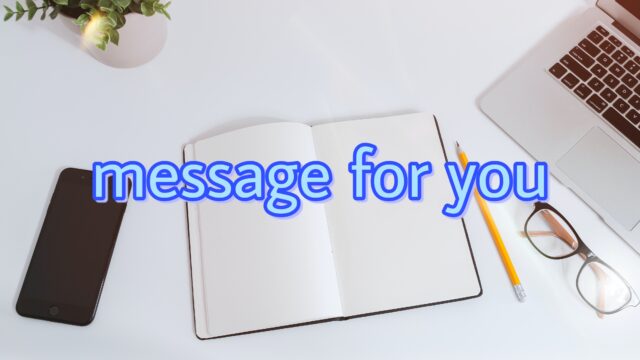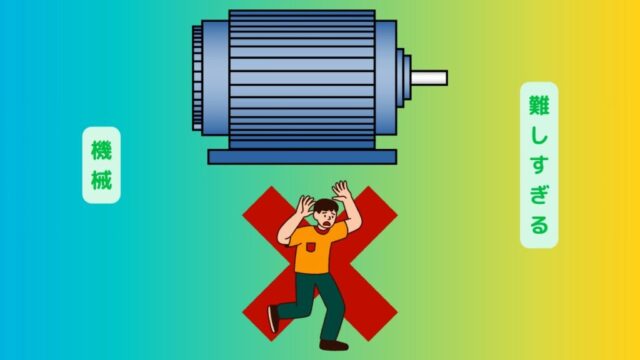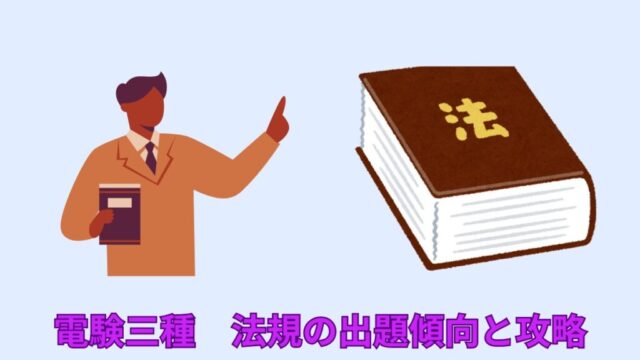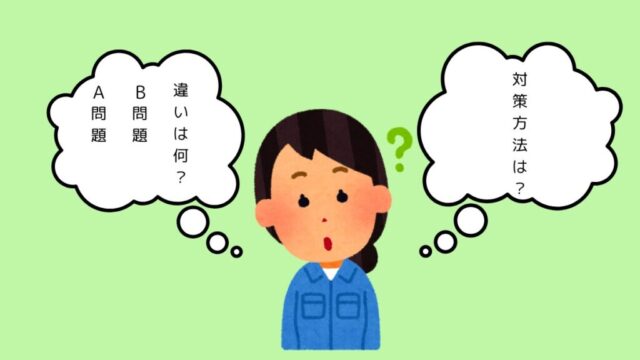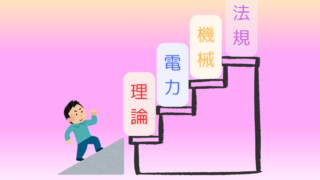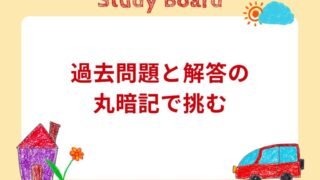【電験三種】初心者向け | どの科目から勉強したらいいの?受ける順番は?

- 電験三種試験の勉強をはじめようと思っていて
- 合格するためには4科目勉強する必要があるんだけど
- どの科目から勉強をはじめたらいいの?
電験三種試験に合格するためには、「理論」「電力」「機械」「法規」という4科目を合格する必要があります。
電験三種の資格を取得するために勉強をはじめようと思ってはみたものの、4科目あってどれから手を付けていいのか迷うことは、初心者にとってよくある悩みです。
この記事を読むことにより、分かること。
- 効率的に学習を進めるための、勉強する科目の順番
- その科目から勉強をはじめるべき理由
勉強の道筋が見えることで、迷わず自信を持って学習を進められるようになります。どの科目から勉強していくのが効率的なのか知りたい方は、この記事を最後まで読んで下さい。
1.勉強する順番 『電気の基礎⇒理論⇒電力⇒機械⇒法規』
まず、効率よく学習を進めるための順番
- 「電気の基礎」(数学)
- 「理論」
- 「電力」
- 「機械」
- 「法規」
この順に勉強しましょう。

この順序である理由は、各科目が次の科目の理解を支える基礎になっているためです。電験三種の試験範囲は非常に広いため、基礎から一歩ずつ積み重ねることで理解が深まり、難しい問題にも対応できるようになります。
例えば、「理論」は電験三種全体の基礎となる科目であり、「電力」や「機械」の理解にも必要です。また、法規は暗記科目であるため、最後に取り組むことで効率的に記憶に定着させられます。
「数学の基礎力」から「法規」まで、順を追って勉強することで、全科目を無理なく学習できます。
2.【STEP1】初心者の方は「電気の基礎」(数学)から勉強スタート
まずは電気の基礎(数学)からマスターしましょう。
電験三種では、電気の基礎(数学)を理解していないと、そもそも参考書・問題集を読んでも理解出来ません。
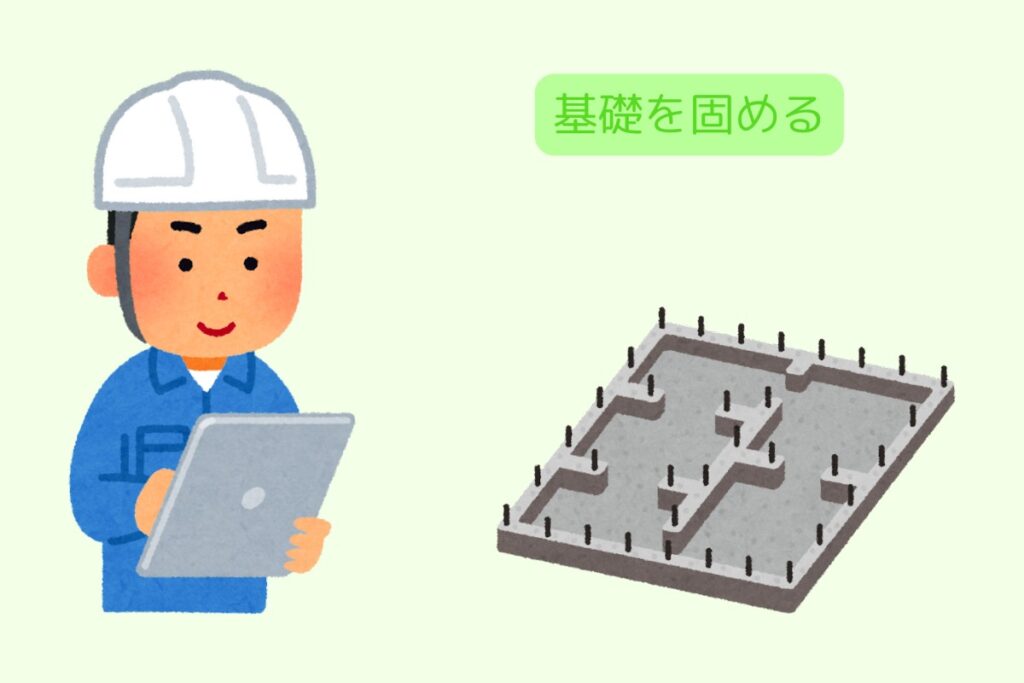
電気の基礎が固まっていると、後の科目を学ぶときにも自信を持って取り組めるようになります。
計算問題では数式の理解や計算力が求められますが、これらの基礎が分かっていないと、解説を読んでも理解することが出来ません。
電気の基礎をしっかりと身につけてから理論の勉強に進むことで、理解がスムーズになり、合格に向けての力をしっかりとつけることができます。
はじめて「電気の基礎」を学習するあなたのための、おすすめのテキストになります。
「みんなが欲しかった! 電験三種 合格へのはじめの一歩 第3版」が発売されています。最新のものを購入しましょう。
まずはこのテキストで学習を始め、あなたの基礎力を身に付けましょう。
3.【STEP2】全ての科目の基本である「理論」の勉強を進める
「電気の基礎」をマスターしたら、次に取り組むべき科目は「理論」です。
理論は電験三種の全科目の基本となり、理解の基礎になります。
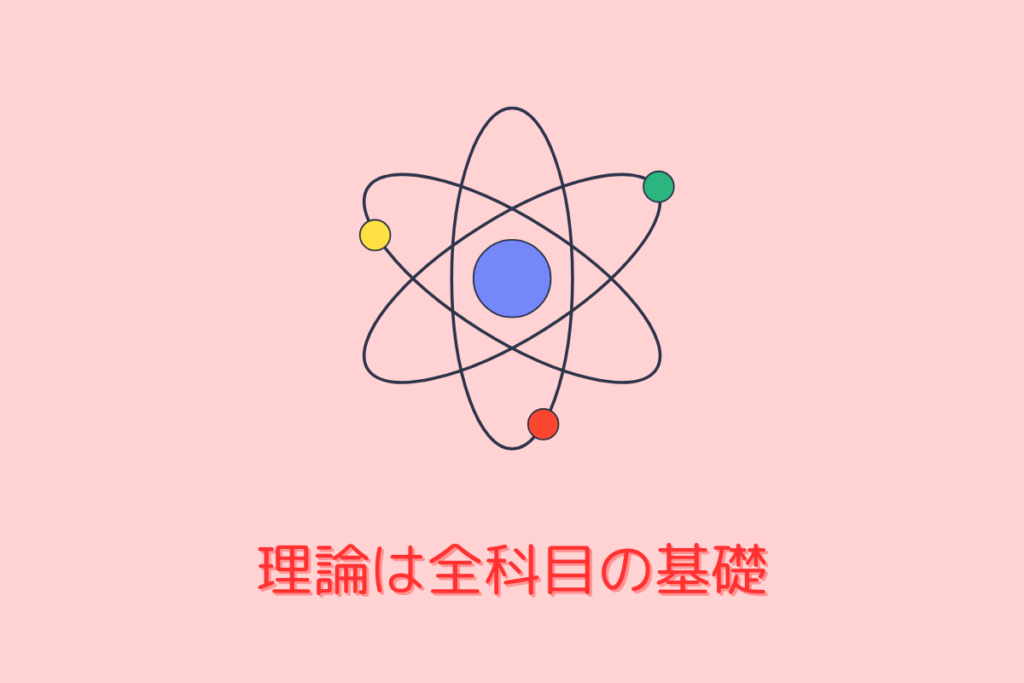
理論を理解していないと、他の科目である「電力」や「機械」、「法規」に進んだときに難しさを感じ、勉強が行き詰まる可能性もあります。
「理論」は4科目の基礎ですので、時間をかけて学ぶ価値があります。根気よく勉強していきましょう。
何度も繰り返して学習しているうちに、徐々に理解が進み、問題を解く際の自信がついてきます。また、「理論」をしっかりと学んでおくと、「電力」や「機械」の内容が理解しやすくなります。
最初は難しく感じるかもしれませんが、何度も繰り返し根気よく学び続けることで理解出来るようになります。
「理論」を学び理解することにより、他の科目もスムーズに学べるようになるメリットがあります。
はじめて「理論」を学習するあなたのための、おすすめのテキストになります。
4.【STEP3】イメージしやすい電力の学習を進める
「理論」の次は「電力」に進みましょう。
電力は内容が比較的イメージしやすいので勉強を進めやすいです。「電力」は勉強していて楽しい科目です。

理論の勉強をした後は、「電力」と「機械」はどちらからはじめても問題ありませんが、はじめて「機械」の勉強をする時、テキストの内容を具体的にイメージしにくいので取り掛かりづらいです。
「機械」科目ではモーターの動きを理解する必要があるのですが、勉強したことのない人ですとなかなか理解しづらいです。
「機械」が難しく挫折してしまう可能性があります。
イメージしやすく理解が進みやすい「電力」を「理論」の次に学習するのが望ましいでしょう。
はじめて「電力」を学習するあなたのための、おすすめのテキストになります。
5.【STEP4】難易度の高い「機械」にじっくり取り組む
「電力」の次は「機械」に取り組みましょう。
「機械」は、最初はイメージするのが難しいです。じっくり腰を据えて勉強しましょう。
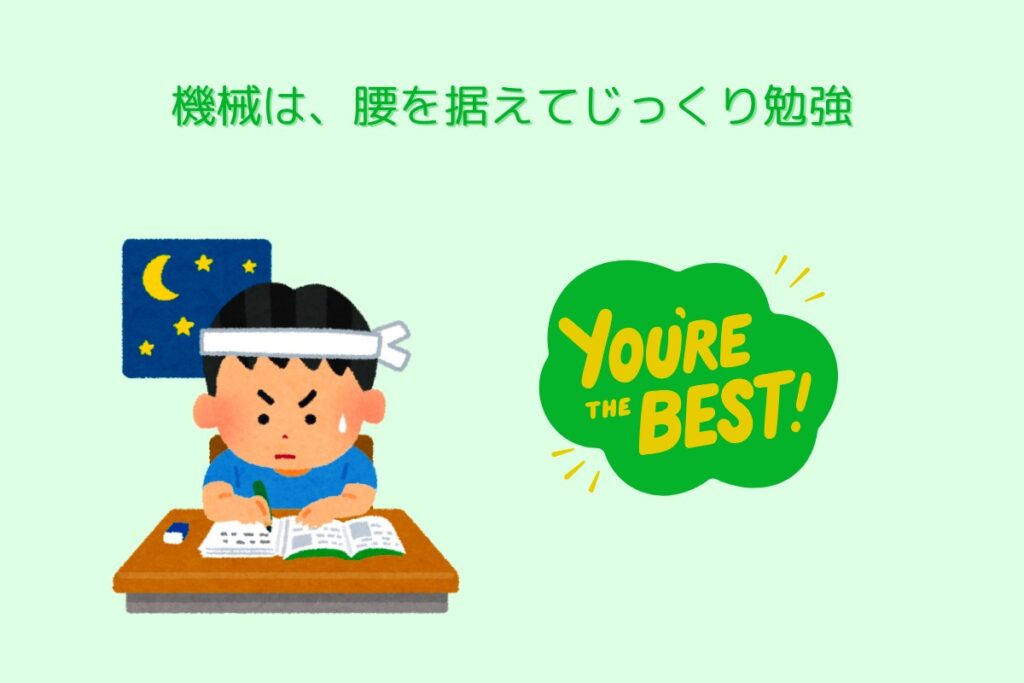
機械は、「電動機」や「発電機」の動作を理解する必要があるため、初心者にはとっつきにくいです。しかし、理解が進むと問題のパターンがつかめるようになり、得点源にしやすい科目でもあります。
「機械」は一度理解してしまうと、簡単に感じます。問題パターンが同じだからです。機械は慣れてしまえば大抵の問題は解けるようになります。
はじめて「機械」を学習するあなたのための、おすすめのテキストになります。
6.【STEP5】最後は暗記科目の「法規」に取り組む
「法規」は最後に勉強しましょう。
暗記は時間が経つと忘れてしまいます。「法規」は、試験が近くなってから学習するのが効果的です。

法規は、計算問題で電力と似た内容の問題も過去に出題されています。
過去問題を分析すると、「法規」のA問題はほとんどが暗記問題となっています。試験前に集中的に覚えれば得点につながりやすくなります。最後に取り組むことで知識が定着しやすくなります。
「法規」は最後に学習することで、しっかりと記憶に残すことができます。
はじめて「法規」を学習するあなたのための、おすすめのテキストになります。
7.まとめ
電験三種の勉強の順番です。
- 【STEP1】電気の基礎(数学)
- 【STEP2】理論
- 【STEP3】電力
- 【STEP4】機械
- 【STEP5】法規
電験三種の勉強では、順序を工夫することで効率的に理解を深めることができます。数学の基礎から始め、理論、電力、機械、そして法規と進めることで、知識のつながりが強まり、試験合格に向けて着実にステップアップできます。
電験三種は、単に順不同で勉強を始めると、理解が浅くなりがちです。科目ごとの理解が段階的に深まるような順序を取ることで、学習効率が飛躍的に向上します。
特に「理論」科目を先に取り組むことが重要です。「理論」は他の科目理解の基礎となるため、これを先に勉強することで、「電力」や「機械」科目の学習をスムーズに進めやすくなります。
電験三種試験の勉強を成功に導くためには、「数学の基礎力」「理論」「電力」「機械」「法規」の順で進めることが重要です。
各科目が相互に支え合うように組み立てられているため、この順番での学習が試験合格への近道となります。
電験三種のおすすめのテキストについて詳しく知りたい方は、こちらの記事をクリックし、読んで下さい。