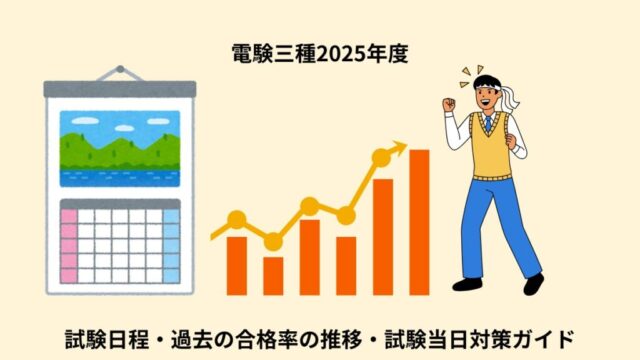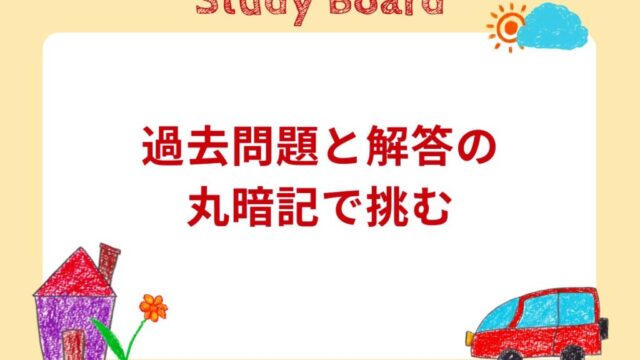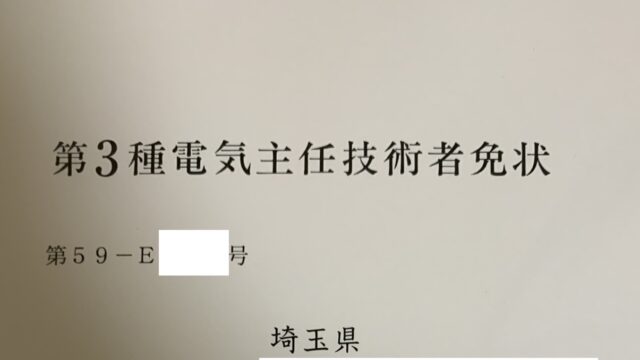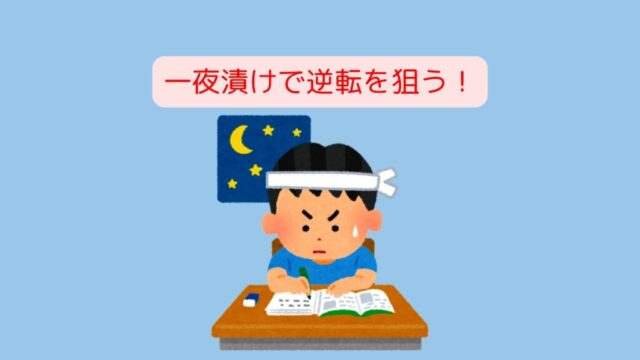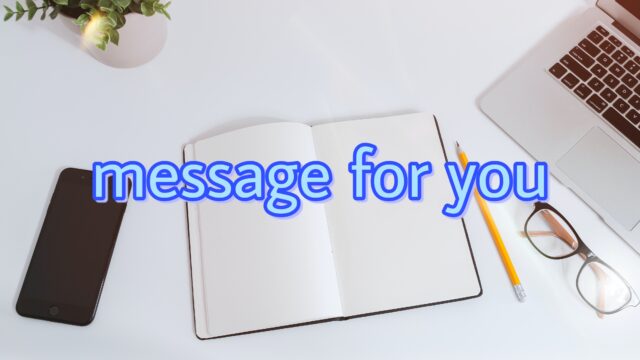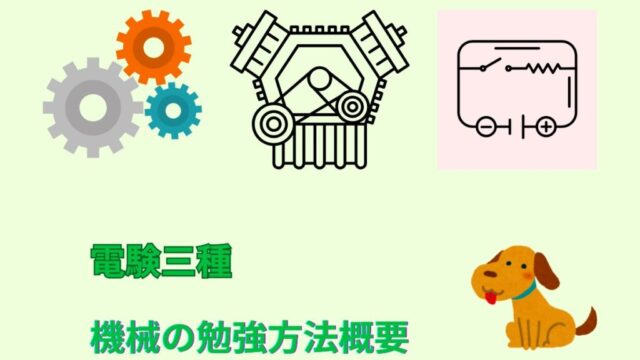【初心者用】電験三種 法規の出題傾向と攻略

- 今から電験三種 法規の合格を目指して勉強するんだけど
- どうやって勉強したらいいのか分からない
- 法規の出題傾向と攻略法が知りたい
- 勉強をコツコツと頑張るから、法規科目の合格出来る方法を教えて
法規の勉強を始めようとした初心者が、参考書・問題集を手に取ってみたものの何から始めたらいいのか分からずに挫折してしまうケースは非常に多いです。
私は電験三種の合格を目指す者として、初心者の立場からスタートしました。3年8ヶ月と4回の受験を経て、合格を勝ち取りました。しかしその3年8ヶ月の間、勉強方法について悩み様々な方法を実践し、たくさんの遠回りをしてきました。
この記事では、初心者向けに電験三種の法規の出題傾向と効果的な攻略法を解説します。出題傾向を分析することにより、合格へ大いに近づくことができます。法規科目は、年度によっては難易度が高く感じられます。しかし正しい学習方法を身につければ、合格は十分に可能です。
合格に向けたステップをスムーズに踏み出せるよう、詳しく解説していきます。法規の出題傾向と攻略方法を知りたい方は、最後まで読んで下さい。
1.法規の出題傾向を把握する

A問題については、過去の出題内容を覚えることが大切で、できる限り過去20年分の問題を解くことをおすすめします。多くの過去問を解くことにより、法規科目の合格に近づくことが出来ます。
1-1.分野別の出題傾向
毎年の分野別の大よその出題傾向になります。
出題分野と出題数をご紹介します。
| 分野 | 出題数 |
| 電気事業法とその他法規 | 2~3 |
| 電気設備と技術基準 | 7~8 |
| 電気設備技術基準計算 | 1~4 |
| 電気施設管理 | 1~4 |
| その他 |
法規の出題傾向を理解し、効果的な対策を講じることは、非常に大切です。
- 出題分野と出題数は分かったけれど、それからどうしたらいいの?
- どのように対策をしたらいいのか分からない。
このような疑問をお持ちのあなたへ、出題傾向を把握したあとにやるべき内容をお教えします。
- 計算問題(B問題)から勉強する。
- 計画的な学習を行う。
合格を目指して、着実にステップを進めていきましょう。
合格のためのおすすめのテキストが知りたい方はこちらの記事を読んで下さい ⇒ 【電験三種】合格のためのおすすめ参考書・問題集・過去問題集
1-2.A問題(暗記中心)60点、B問題(計算中心)40点
法規の試験はA問題(暗記中心)60点、B問題(計算中心)40点で構成されています。B問題は出題パターンが決まっています。過去問を中心に学習し、解き方を理解しましょう。
- 形式:6点×10問=60点満点
- 特徴:法令に関する暗記問題が中心
- 対策:過去問の反復学習+法令の条文を覚える
A問題は、知識を正確に覚えていれば確実に得点できるので、暗記の質と反復が重要になります。
- 形式:問11・問12(a)6点(b)7点、問13(a)7点(b)7点=40点満点
- 特徴:計算問題が中心
- 対策:計算問題のパターンを理解し、過去問を繰り返し解く
B問題は、パターン化された計算問題が多いため、公式を覚え、過去問で解き方を身につけることが重要です。
A問題とB問題の違いについて、詳細はこちらの記事を読んで下さい。
1-3.1問あたりの配点は高いが、合格基準点は変わらない
法規科目は、理論・電力・機械に比べて1問あたりの配点が高いです。しかし合格基準点は60点と変わりません。
※理論・電力・機械:1問5点×20問
1問あたりの配点が高いので、1問のミスで、そのまま合否を左右する結果につながる可能性があります。
| 科目 | A問題の配点 | B問題の配点 |
| 法規 | 6点×10問:60点 | 問11・問12(a)6点(b)7点、問13(a)7点(b)7点:40点 |
| 理論・電力・機械 | 5点×14問:70点 | 5点×6問(大問3問×2):30点 |
※合格基準点:各科目60点
2.法規の対策としてB問題から学習する
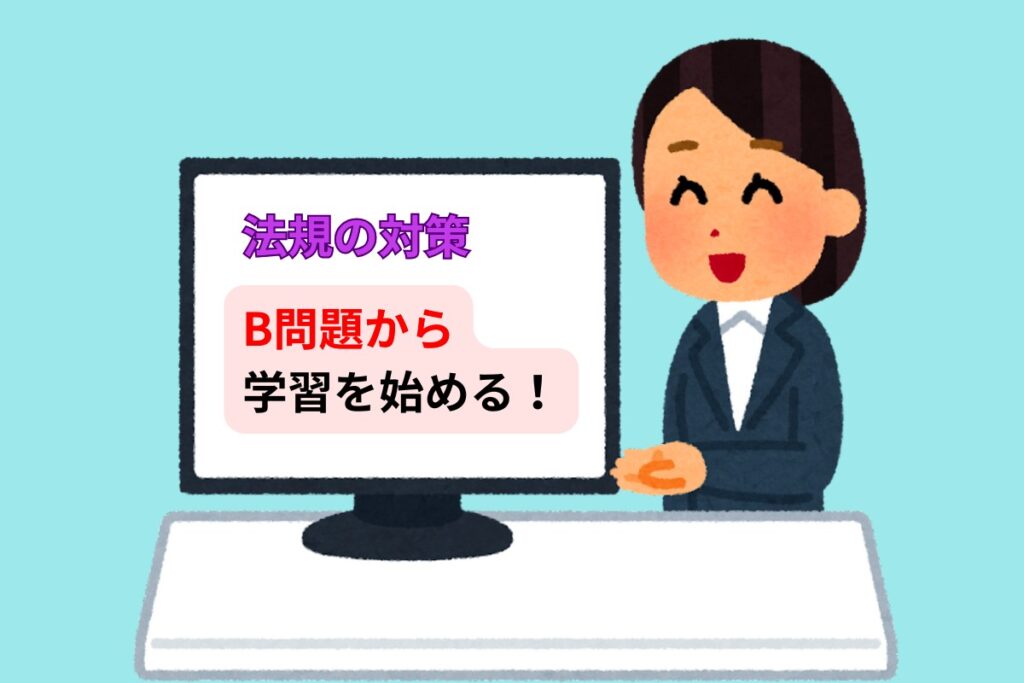
B問題の得点が比較的容易なため、まずB問題から学習を始め、A問題に取り組むのが効果的です。
- B問題:計算問題に精通するために過去問題を徹底的に練習し、実力を高めましょう。
- A問題:過去問を解き、重要なポイントを暗記することが効果的です。
2-1.B問題の計算力を高める
計算式の公式を正確に把握することがポイントです。法規の公式は、試験に合格するためであれば丸暗記でも問題ありません。
電力科目と法規科目は関連性があるため、電力科目を先に学んだ方が法規の計算問題の理解が進むことがあります。電力を習得してから法規の計算に取り組むことで、より深い理解が得られるでしょう。
B問題は計算問題が中心です。関連する法規をしっかり理解し、過去問を繰り返し解くことで、計算スキルを向上させましょう。
2-2.A問題の過去問を解き暗記する
空欄部分の暗記は勿論のこと、文脈から重要なキーワードやポイントを理解し、頭に入れておく方が記憶に定着します。
現在、電験三種は過去問題を中心に出題されています。過去問を解いて、過去問の内容を暗記しましょう。
ブログ内の「法規の勉強方法と概要」も併せてチェックしていただくことをお勧めいたします。その記事では、法規科目に特化した勉強方法の概要を解説しています。こちらからどうぞ ⇒ 「法規の勉強方法概要」
「3.法規の攻略」では、頻出頻度の高い問題をピックアップしました。現在、電験三種は過去問題を中心に出題されています。過去問題を完璧に近い状態になるまで繰り返し学習しましょう。
※過去20年分以上の過去問題を、10回以上繰り返し解くことをおすすめします。
3.法規の攻略

出題傾向に対する主な分野についての具体的な攻略を解説します。お手元の参考書と照らし合わせながら内容を確認してみましょう。
具体的な公式・解法については、ご自身の教材でご確認ください。
3-1.電気事業法とその他法規
①標準電圧と維持すべき値(電気事業法施行規則第38条)
| 標準電圧 | 100V | 200V |
| 維持すべき値 | 101V±6V | 202V±20V |
②電気工作物(電気事業法第38条)
一般用電気工作物と事業用電気工作物、さらに自家用電気工作物について、理解し覚えましょう。
③小出力発電設備と出力(電気事業法施行規則第48条)
各種発電設備と出力について、覚えましょう。
④電気主任技術者の免状種類と、保安監督できる範囲(電気事業法施行規則第56条)
第三種電気主任技術者 電圧5万ボルト未満の事業用電気工作物(出力5000kW以上の発電所を除く)
⑤電気工作物について事故が発生した時の報告内容と報告するまでの日数(電気関係報告規則第3条)
⑥特定電気用品と特定電気用品以外の電気用品(電気用品安全法題2条1項)
⑦電気工事士の資格と作業範囲
3-2.電気設備と技術基準
用語の習得と暗記が重要です。過去の試験問題を中心に万遍なく学習し、誤答した問題には参考書で解説を確認しましょう。この反復学習を通じて、理解が深まります。
正誤情報を過去問集に記録すると、自身の得意分野と苦手分野が明確になります。試験直前には、「×」のついた問題に重点を置いて学習しましょう。
3-3.電気設備技術基準計算
①許容引張荷重、たるみ、安全率
許容引張荷重=引張強さ/安全率
電線のたるみ
D=WS²/(8T)
D:電線のたるみ(m) W: 電線1mあたりの合成荷重(N/m) S: 経間(m) T: 電線の水平張力(N)
②架空電線の最大荷重や支線の条数算出
③高温季、低温季の風圧荷重の算出
甲種、乙種、丙種風圧荷重とそれぞれの計算式について理解しましょう。
3-4.電気施設管理
①需要率・不等率・負荷率
公式は理解し、暗記しましょう。
これらを覚えてないと、問題を解くことが難しくなります。
負荷率=平均需要電力/最大需要電力 ×100
需要率=最大需要電力/設備容量 ×100
不等率=最大需要電力の総和/合成最大需要電力
②日負荷曲線
損失電力量の計算
③水力発電所の出力の計算
公式をしっかり理解しましょう。過去問を勉強することで、理解が深まると考えられます。
④地絡故障電流の計算
⑤高調波電流の計算
3-5.過去問題を攻略する
その他の問題も過去問題集は全て解いて、知識を深めておきましょう。
繰り返しのご説明になりますが、20年分以上の過去問題を繰り返し解くことにより、合格に大いに近づきます!

| おすすめ順 | 過去問題集 | おすすめ度 |
| 1 | 「電験三種 法規の20年間」 | ★★★★★ |
| 2 | 「みんなが欲しかった!電験三種の10年過去問題集」 | ★★★★ |
1.「電験三種 法規の20年間」(電気書院)を攻略する
私自身、こちらの過去問題集を10回以上繰り返しています。分野別にまとめられているので、弱点の克服に最適な教材となっています。
1⃣分野別にまとめられている過去問題集
この教材は分野別に過去問題をまとめて提供しています。特定の分野について集中的に学習を進めることができます。苦手分野の克服には最適な教材と言えるでしょう。
2⃣過去問の解説が詳細
過去問の解説が詳細に記載されており、問題の理解を深めるのに役立ちます。
2.「みんなが欲しかった! 電験三種の10年過去問題集」(TAC出版)を攻略する
本を切り離しで分冊できる便利な形式です。移動時間などを活用して学習することができます。
構成は
- 過去問題集
- 理論(解答解説編)
- 電力(解答解説編)
- 機械(解答解説編)
- 法規(解答解説編)
計5冊に分冊できます。
1⃣解答解説編
②③④⑤の解答解説編には、小さな文字ですが問題文は記載してあります。勉強したい分野1冊を持ち歩いて学習することが可能です。
2⃣過去問題集
過去問題集を利用し、時間内に問題を解き、自己採点を行い、自分の実力を評価しましょう。
答案用紙の記入シートも付属しており、本番さながらの状況で実際に問題を解くことができます。
※私は答案用紙の記入シートをコピーして使用しました。
3⃣分冊形式教材の有効活用
電験三種の学習において、この分冊形式教材は効率的で便利な選択肢と言えるでしょう。
- 移動時間やスキマ時間を活用して、効果的な学習を実現しましょう。
- 出題傾向を理解し、合格に向けて自信をつけていきましょう。
2026年度版は2024年12月24日より販売予定です。Amazon、楽天市場、Yahoo! ショッピングにて予約受付中です。
お急ぎの方は、2025年度版も販売しています。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
3.過去問を読んでも分かりづらい場合、「みんなが欲しかった!法規の教科書&問題集」を攻略する
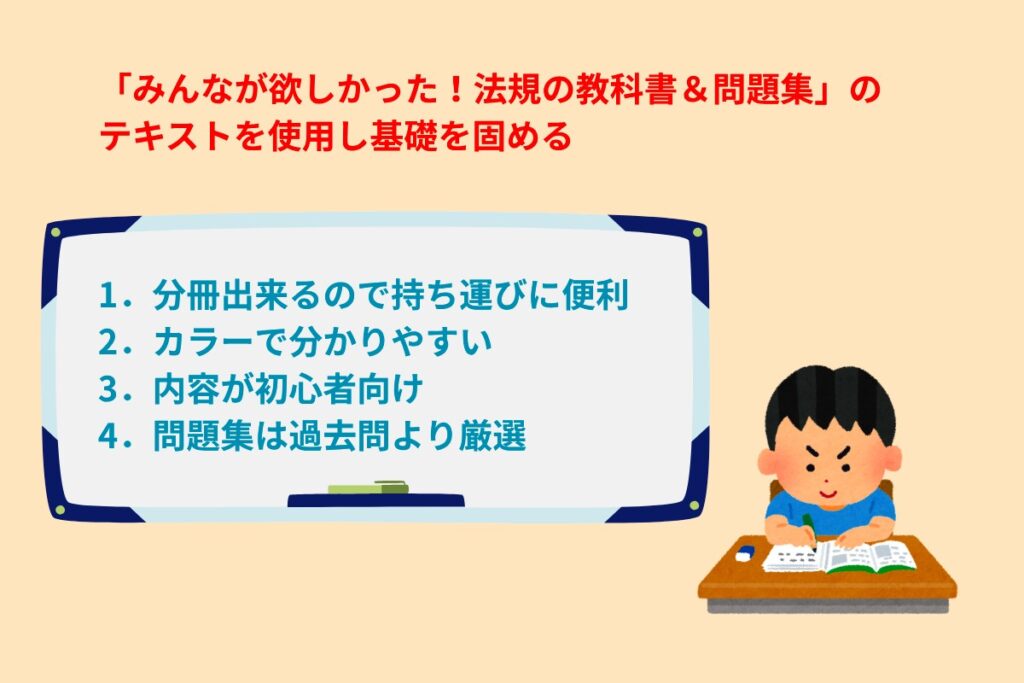
「みんなが欲しかった!法規の教科書&問題集」は図解が豊富で理解しやすい構成となっています。法規の勉強方法として、問題集を解きながら、法令を参考書と見比べて勉強を進めて行きましょう。
①持ち運びに便利
分冊することにより荷物の負担が減るメリットがあります。電車やバスでの通勤時に持ち歩き、スキマ時間を利用して勉強することが出来ます。
②参考書は、カラーで分かりやすい説明
視覚的に理解しやすくなっています。初心者には取り掛かりやすい参考書&問題集となっています。
③他の参考書と比べ、内容が初心者向けとなっています。
④問題集は、過去問題より厳選したものとなっています。
4.出題の傾向を掴んで合格へ近づく
法規科目の攻略には、出題の傾向を知ることが不可欠です。過去問を解き、暗記し、理解しましょう。そして、最終的な合格への近道として、出題のポイントを押さえて臨みましょう。
合格への努力と向き合う日々は大変かもしれませんが、諦めずに前進しましょう。電験三種試験は挑戦的なものですが、適切な学習戦略と継続的な努力で克服できます。
自分のペースで着実に進んでいくことが大切です。時にはつまずくこともあるかもしれませんが、そのつまずきこそが成長への一歩です。過去問を解き、知識を深め、自信をつけていきましょう。
成功への道は一筋縄ではいかないこともありますが、継続的に勉強することにより最終的には目標を達成することができます。
合格への近道は、正しい方法で学び、自己評価をしっかり行い、最後まで諦めないことです。一歩一歩進んでいけば、必ず目指す合格へ到達できるでしょう。応援しています!