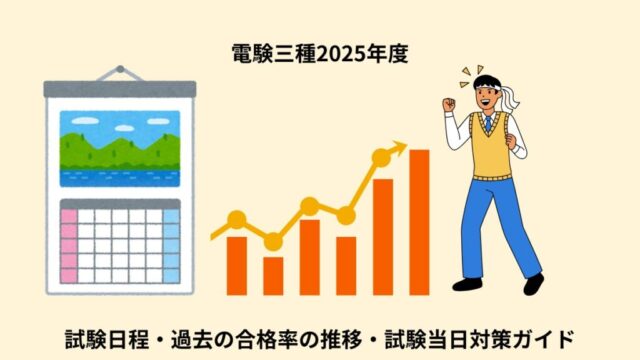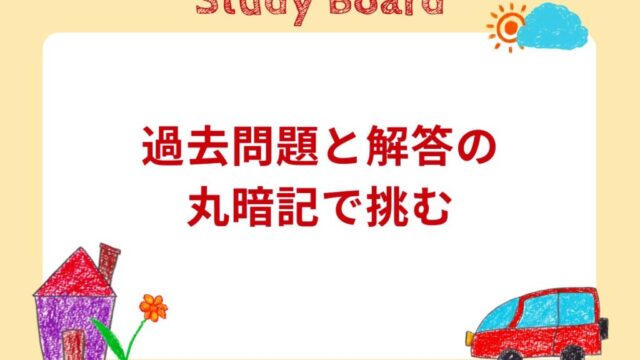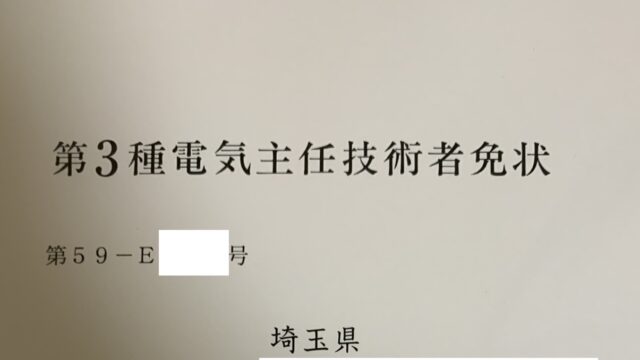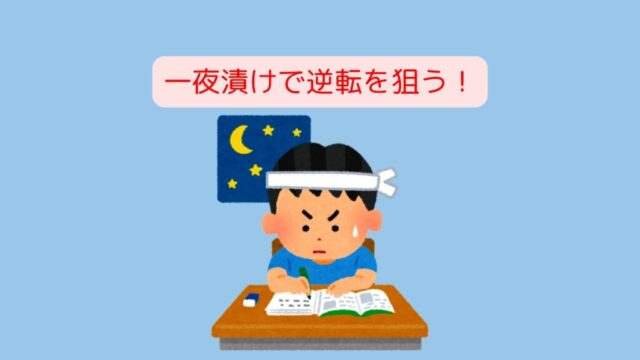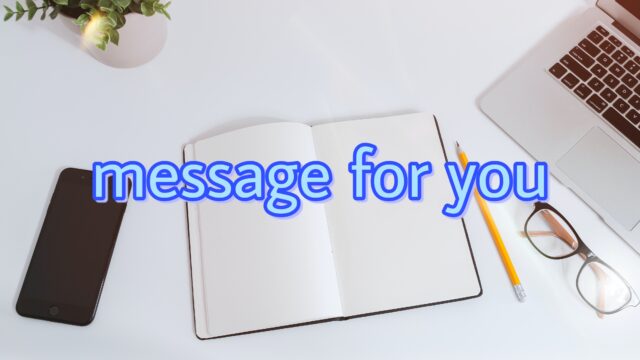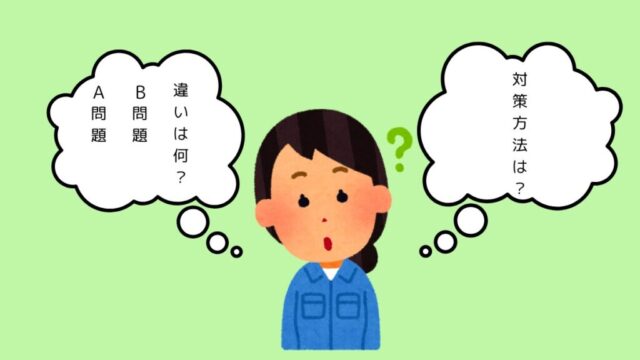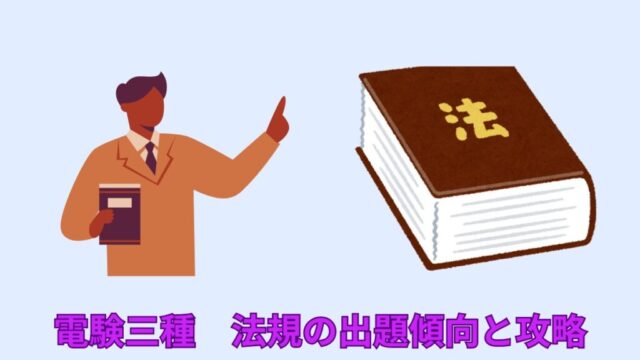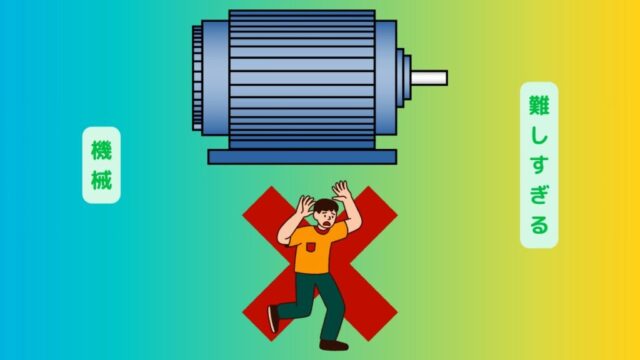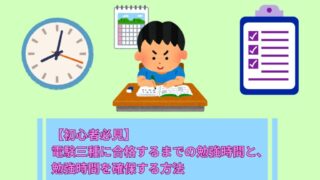【初心者用】電験三種 理論の出題傾向と攻略

- 今から電験三種 理論の合格を目指して勉強するんだけど
- どうやって勉強したらいいのか分からない
- 理論の出題傾向と攻略法が知りたい
- 勉強をコツコツと頑張るから、理論科目の合格出来る方法を教えて
理論の勉強を始めようとした初心者が、参考書・問題集を手に取ってみたものの何から始めたらいいのか分からずに挫折してしまうケースは非常に多いです。
私は電験三種の合格を目指す者として、初心者の立場からスタートしました。3年8ヶ月と4回の受験を経て、合格を勝ち取りました。しかしその3年8ヶ月の間、勉強方法について悩み様々な方法を実践し、たくさんの遠回りをしてきました。
この記事では、初心者向けに電験三種の理論の出題傾向と効果的な攻略法を解説します。出題傾向を分析することにより、合格へ大いに近づくことができます。合格に向けたステップをスムーズに踏み出せるよう、詳しく解説していきます。
理論の出題傾向と攻略方法を知りたい方は、最後まで読んで下さい。
1.理論の出題傾向

電験三種理論試験において、出題傾向を知ることは合格への第一歩です。毎年の分野別の大よその出題傾向になります。
| 分野 | 出題数 |
| 直流回路 | 2~5 |
| 静電気 | 2~5 |
| 単相交流 | 1~5 |
| 三相交流 | 約2 |
| 電子理論 | 約2 |
| 電子回路 | 約2 |
| 電気計測 | 約2 |
| 電磁気 | 約2 |
| 過渡現象 | 約1 |
| その他 |
理論の出題傾向を理解し、効果的な対策を講じることは、非常に大切です。
- 出題分野と出題数は分かったけれど、それからどうしたらいいの?
- どのように対策をしたらいいのか分からない。
このように考えるのは良くあることです。出題傾向を把握したあとやるべきことになります。
- 出題数の多い分野から勉強する。
- 計画的な学習を行う。出来れば、毎日コツコツ勉強する。
合格を目指して、一歩ずつステップを進めていきましょう。
次に、出題傾向に対する主な分野についての具体的な攻略を解説します。お手元の参考書と照らし合わせながら内容を確認してみましょう。
具体的な公式・解法については、ご自身の教材で勉強してください。
合格のためのおすすめのテキストが知りたい方はこちらの記事を読んで下さい ⇒ 【電験三種】合格のためのおすすめ参考書・問題集・過去問題集
2.理論の攻略

出題傾向に対する主な分野についての具体的な攻略を解説します。お手元の参考書と照らし合わせながら内容を確認してみましょう。
具体的な公式・解法については、ご自身の教材でご確認ください。
2-1.直流回路
直列と並列の抵抗を組み合わせた問題が、ほぼ毎年出題されます。
電源が複数ある問題も2年に1度程度の割合で出題されます。こちらに関してはテブナンの定理・ミルマンの定理を繰り返し勉強し、使いこなせるようにしましょう。
①基本的な理解
直流回路の基本的な概念を理解しましょう。
直流回路では、電流が一方向に流れ、電圧は一定です。電源、抵抗、電流の流れ方などの基本的な要素を把握しましょう。
②オームの法則
直流回路内でオームの法則を適用する方法を理解しましょう。
抵抗値と電流、電圧の関係を正確に理解し計算できることが重要です。
③公式の活用
キルヒホッフの法則、テブナンの定理、ミルマンの定理を理解しましょう。
どの問題にはどの定理を使用すると速く解くことが出来るか、考えながら勉強を進めましょう。効率的に問題を解くことにより、時間短縮が図れます。
④電力とエネルギー
直流回路内での電力とエネルギーの計算方法を理解しましょう。
2-2.静電気
①クーロンの法則
クーロンの法則は電荷同士の相互作用を記述する重要な法則です。
クーロンの法則を理解し、電荷同士の引力と反発力を考察し、異なる電荷の力、同じ電荷の力を区別し計算出来るようにしましょう。
②コンデンサー
コンデンサーの基本的な原理と動作について学習しましょう。コンデンサーの容量(キャパシタンス)や充電および放電のプロセス、エネルギー蓄積に焦点を当てます。
平行板コンデンサーはほぼ毎年出題されますので、しっかり学習しましょう。
③電位の概念
電位の概念を理解しましょう。
電位差(電圧)の計算方法やポテンシャルエネルギー(位置エネルギー)について学習します。
④静電遮蔽
静電遮蔽の基本的な原理と目的について学習しましょう。
静電遮蔽は電磁干渉を制御し、外部からの電磁波やノイズの影響を軽減するために使用されます。
2-3.単相交流
①基本的な理解
単相交流の基本的な概念を理解しましょう。これには、電圧、電流、位相差、周期などの基本的な用語と概念が含まれます。
単相交流の波形である正弦波はしっかり把握しておきましょう。(正弦波は、三相交流の波形を考える時にも重要になります)
②オームの法則
単相交流回路内でオームの法則を適用する方法を理解しましょう。
電圧、電流、抵抗の関係を正確に計算できるようになることが重要です。
③インダクタンスとキャパシタンス
インダクタンス(コイルの特性)とキャパシタンス(コンデンサの特性)について学習し、単相交流回路内での動作と計算方法を習得しましょう。
RLC回路の大きさ、位相差について理解し、ベクトル図を書けるようにして直列接続、並列接続、共に計算出来るようにしておきましょう。
RLCとは
R:抵抗 L:インダクタンス C:キャパシタンス(静電容量)
④電力とエネルギー
単相交流回路における電力とエネルギーの計算方法を理解しましょう。有効電力、無効電力、皮相電力などについて学び、計算スキルを向上させましょう。
2-4.三相交流
理論科目の難関分野です。ほぼB問題で出題されますので、得点出来れば2問で10点となります。
三相交流に関する問題の対策は非常に重要です。
①基本的な理解
三相交流の基本的な概念を理解しましょう。
三相交流は、3つの交流電圧または電流が同じ周波数で発生し、位相差を持つものです。各相の波形の位相差が120度(2π/3ラジアン)であることを把握しておきましょう。
②相間関係の理解
三相交流では、各相の電圧や電流が位相差を持っているため、相間関係を理解することが重要です。
特に、Y接続(星形接続)と△接続(三角形接続)の回路の相間関係を把握しましょう。
③電力計算
三相交流回路の電力計算は重要なスキルです。有効電力(W)、無効電力(var)、皮相電力(VA)など、各種電力の計算方法を学びましょう。
- 力率の概念を理解しておきましょう。
- Y結線とΔ結線の違い、YをΔ結線に変換すると大きさ、位相差はどのように変化するのか、電流、電圧、RLCについてそれぞれ考え、計算出来るようにしましょう。
2-5.電子理論、電子回路
基本的な概念が重要ですので、以下の内容について理解を深めましょう。
①電子の基本的な性質
電子の電荷、質量、運動などの特性を理解しましょう。
②半導体の特性
n型半導体、p型半導体、pn接合、ダイオードなどに関する基本的な知識を理解しましょう。
半導体は頻出分野ですので、しっかり理解し覚えましょう。
合わせて、太陽電池も時々出題されますので、理解しておきましょう。
③トランジスタの動作原理
npnトランジスタ、pnpトランジスタ、電界効果トランジスタ(FET)などを理解しましょう。
④トランジスタ増幅回路
こちらも頻出で2年に1回以上出題されています。難易度は高いので、繰り返し過去問を解きマスターしましょう。
⑤オペアンプ
オペアンプは解法パターンがほぼ決まっており、一度マスターしてしまえば得点源となるでしょう。
2-6.電気計測
①誤差率と補正率
誤差率と補正率について公式を覚え、この二つの違いを理解しましょう。
※例えば、誤差率を答えさせる問題など出題される場合があります。誤差率と補正率を、混同しないようにきちんと覚えましょう。
②電圧計、電力計、電力量計
難易度は高く理解するまでに時間がかかります。最近の電験三種の傾向として過去問中心の出題ですので、難しい場合は解説をそのまま覚えましょう。
③指示電気計器
出題頻度は少ないですが、記号と名称、使用回路を覚えれば、得点できます。
そのまま暗記しましょう。
④倍率器、分流器
過去問を通じて理解しましょう。解き方に慣れてしまえば得点源になります。
公式もありますが、理解すれば公式を覚えていなくても解くことは可能です。(私は、倍率器、分流器の公式は暗記しませんでした)
2-7.電磁気
①磁界の計算
アンペアの周回路の法則や磁界、磁束密度、磁気回路に関する問題が出題されることもあります。
磁気回路のオームの法則は理解し、使いこなせるようにしておきましょう。(磁性体の性質や特性も理解しておきましょう)
②電磁誘導に関する問題
ファラデーの法則、自己誘導と相互誘導、誘導電流の発生に関する知識が求められます。
③インダクタンス
インダクタンスに関する基本的な知識は理解しておきましょう。
コイルの誘導起電力、自己インダクタンスに関する計算が出題されることがあります。公式を理解しておきましょう。
2-8.過渡現象
定常状態と過渡状態
電気回路やシステムは通常、定常状態と呼ばれる安定した状態にあります。回路に変化が生じたり、スイッチが切り替えられたりすると、過渡状態が発生します。過渡状態は一時的な状態であり、時間の経過とともに安定状態に戻ります。
コンデンサーとコイルの、過渡現象の動きを良く理解しましょう。最初は取り掛かり辛いですが、一度理解すると得点源になります。
2-9.その他
その他の問題も過去問題集は全て解き、知識を深めておきましょう。
3.理論の出題傾向と対策のまとめ
電験三種の理論試験を成功させるためには、継続的に学習し、着々と準備をすることです。基本的な理論と公式をしっかりと勉強しましょう。
出題傾向を把握し、適切な対策を講じることが重要です。関連する問題集や過去の試験問題を解答し、出題傾向や解答方法を習得しましょう。
最後に、電験三種の試験合格は大きな成就です。合格すれば、電気技術の分野でのキャリアが一歩前進します。
こちらの記事が、あなたのお役に立つことが出来たら幸いです。